水稲のロングマット水耕育苗における省力的な培養液管理法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
水耕栽培用の培養液の1種である大塚A処方に、水稲播種プラント用肥料を混ぜて、水稲の草丈が2~3cmになった時に1回だけ施用する省力的な培養液管理で、草丈が高く葉色の濃いロングマット水耕苗が育苗できる。
- 担当:農業研究センター・プロジェクト研究第3チーム(中央農業総合研究センター・関東東海総合研究部・総合研究第2チーム)
- 連絡先: 0298-38-8822
- 部会名: 総合研究,作物生産
- 専門: 栽培
- 対象: 稲類
- 分類: 指導
背景・ねらい
ロングマット水耕苗による移植栽培は、種蒔きから田植までを簡略化・軽作業化でき、大規模経営にも適する省力化技術として期待される(平成8年 成果情報)。この技術の特徴の一つは水耕で育苗する点にある。だが、野菜用の培養液である大塚A処方による培養液管理では、毎日ECを測定し低下したら原 液を追加しECを元に戻す(毎日EC管理)方法を採っており、調整に労力を要すると共に苗の葉色が淡いなどの問題を抱える。そこで、ロングマット水耕育苗 における省力的な培養液管理法について明らかにする。
成果の内容・特徴
- 大塚A処方に水稲播種プラント用肥料(全窒素10% 内アンモニア性窒素9.7%)を2割程度混ぜる培養液処方により、大塚A処方のみ(慣行)に比べて、草丈が高く、葉色の濃い苗が育苗できる(表1)。
- 育苗中に1回または2回だけ施肥した場合でも、毎日EC管理(慣行)と比べて、葉令や地上部重など生育に殆ど差はなく、発根量など活着の面でも問題ない(表2)。
- 1回施肥の場合、早い時期の施用では葉色が淡く安定せず遅いと生育が劣るため、施肥時期は、草丈が2~3cm前後に達する(加温条件下なら播種5日目)頃が妥当である(図1)。培養液濃度(施肥量)としては、水道水よりECで+2.5dS/m高い値(=毎日EC管理の総量)が適当で、低いと生育が劣り、高いと培養液中に肥料が多く残存する。
- 上記の培養液管理を行った場合、pHはいったん下がった後7前後に上昇し、一方、ECはほぼ直線的に減少し、育苗完了時には水道水よりやや高い程度の値となる(図2)。
成果の活用面・留意点
- ロングマット水耕苗の育苗技術の安定化が図られる。
- 上記の成果は、水耕育苗装置でロングマット稚苗を育てるため、1ベンチ(6m×4ベッド)当たり水道水(pH:7.4、EC:0.39dS/m)160リットル を用いて、初期は昼30℃夜20℃、それ以降は徐々に気温を下げ、育苗後期には外気温に慣らす育苗条件下で得られたものである。
- 苗の生育は、その時の温度条件などにより変わるため、高品質苗の安定生産のためには温度管理技術の確立が必要である。
具体的データ
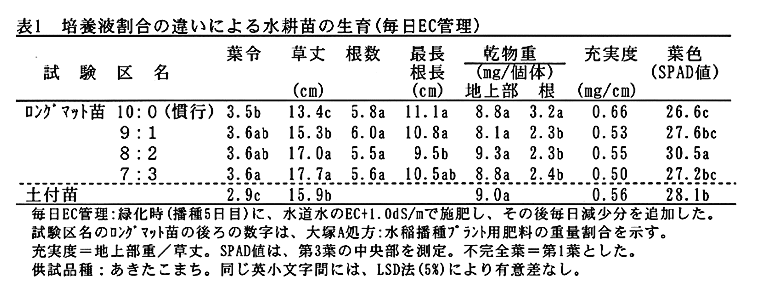
表1:培養液割合の違いによる水耕苗の生育(毎日EC管理)
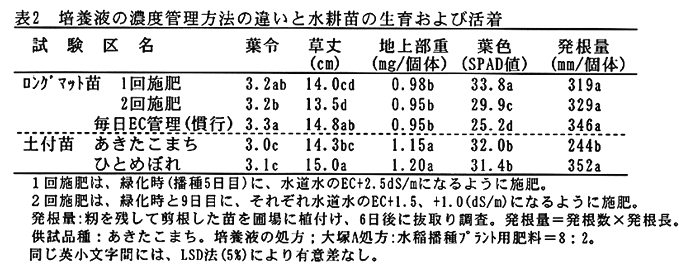
表2:培養液の濃度管理方法の違いと水耕苗の生育および活着
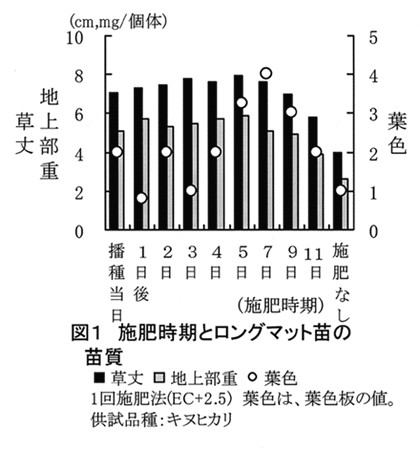
図1:施肥時期とロングマット苗の苗質
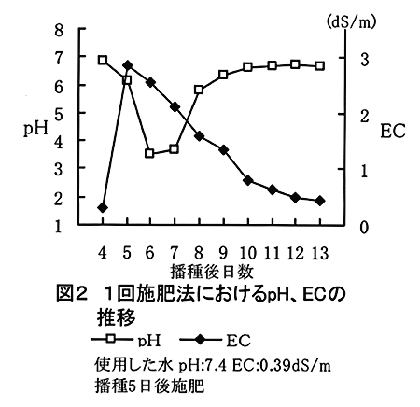
図2:1回施肥法におけるpH、ECの推移
その他
- 研究課題名:ロングマット水耕苗の安定育苗・移植技術の開発
- 予算区分 :地域総合
- 研究期間 :平成12年度(平成10~12年)
