降雪に対する各種降水量計の捕捉率
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
降雪に対する降水量計の捕捉率(測定値/真の値)は、風速が増すにつれて大きく低下する。低下の割合は測器の形状によって異なる。国内で一般に用いられる3種類の降水量計の捕捉率は、高い方から順に溢水式>転倒ます式>温水式である。
- キーワード:降水量計、降雪、捕捉率、補正、風速
- 担当:中央農研・北陸水田利用部・気象資源研究室
- 連絡先:0255-26-3234
- 区分: 関東東海北陸農業・北陸・生産環境
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
北陸地域は世界でも有数の豪雪地帯であり、降雪、積雪は、利益・不利益両面で農業をはじめ地域の産業、社会、生活等に大きく関わっている。したがって積雪の増減や雪資源の賦存量を把握することは特に重要であり、そのためには冬期間の降水量、特に雪など固体の降水量の正確な値が必要である。しかし降水量計が捕捉する降水の量は風の影響などにより一般に真の降水量よりも小さい。特に雪の場合にはこの影響が大きいため、降水量計の捕捉特性を明らかにし、それに基づいて測定値を補正する方法が必要である。
成果の内容・特徴
- 各種降水量計の比較観測を、WMOの勧告に沿った方式で、北陸研究センターにおいて6寒候期にわたって行い、その結果から降水量計の捕捉率を求めた。
- 準器として二重柵基準降水量計(Double Fence Intercomparison Reference、DFIR)を一部改良して設置した。比較対象測器は、国内で一般的に用いられている3機種、すなわち転倒ます式(ヒーター付き)、温水式、溢水式で、いずれも電気により加温し降雪を融かして計測する。溢水式は風よけ付きである。降水量計の開口部は全て地上3.5mとし、風速は全て開口部の高さに換算した値を用いる。
- 降水量の積算が10mm程度以上の降水事象を切り出し、Yangらの式を用いて10分毎のDFIRの測定値と風速から真の降水量を推定し、事象単位で合計した。各降水量計の測定値を推定した真値で除した値を、事象毎の捕捉率とした。これに対応する風速は事象の間の平均風速を用いた。
- 捕捉率は、いずれの測器も風速が増すとともに大きく低下する(図1)。
- 測器によるちがいは、捕捉率の高い方から順に、溢水式>転倒ます式>温水式である。これには風よけの有無、測器の形状が影響している(表2)。
- 捕捉率CRと開口部の高さにおける風速U(m/s)の関係が式1にしたがうとして回帰分析し、測器の特性を示す係数mを求めた(表1)。
CR=1/(1+mU)・・・・・式1
この式により、風速の値を用いて降水量の測定値を補正できる。 - 式1に基づいて計算した捕捉率の観測値に対する平均二乗誤差は、転倒ます式が0.119、温水式が0.157、溢水式が0.116である。
成果の活用面・留意点
- 式1は、降雪の場合に、降水量測定値に対する補正式として利用できる。
- 測定値を補正することにより、降積雪資源賦存量の把握、積雪推定モデル、流出解析、流域水利用計画等に対して正確な入力データとなる。
- 式1の適用範囲は、風速8m/s程度までである。
- 捕捉率は降雪粒子の形状等の特性により変化すると考えられる。このため、温度条件などが違う地域への適用には注意が必要である。
具体的データ
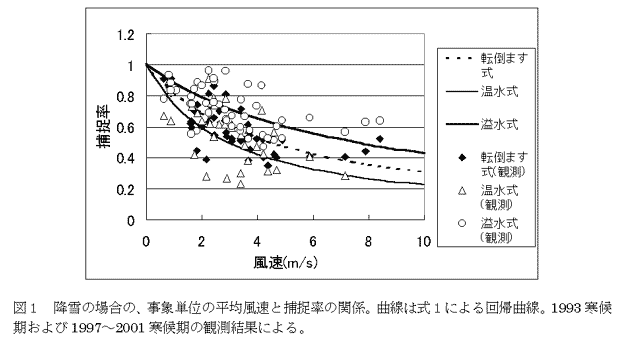
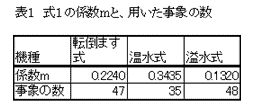
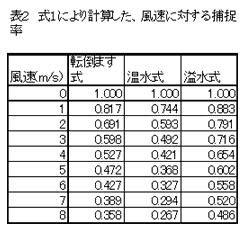
その他
- 研究課題名:寒候期における降水量計の捕捉特性の解明、降積雪資源賦存量の評価方式の確立
- 予算区分:交付金
- 研究期間:1997~2000年度、2001~2004年度
- 研究担当者:横山宏太郎、大野宏之、小南靖弘、川方俊和、井上 聡、高見晋一、Thomas Wiesinger
- 発表論文等:1)大野ら(1998)雪氷60巻3号 225-231
2)横山ら(2001)2001年度日本雪氷学会全国大会講演予稿集28
