大規模稲作経営の収益性と水稲作業受託の導入効果
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
水稲単一経営の所得変化(平成7年対11年)を規模別でとらえると、5ha以上は30%の減少を、15ha以上では11%の減少率を示している。次いで、水田作複合経営における水稲作業受託の導入効果をモデル分析によってとらえると、経営内で4.5人の労働力が確保されている場合、面積規模が40ha(うち水田面積25ha前後)までは経営収益が増大し有利に展開する。
- キーワード:農業所得、大規模水田作複合経営、借地、作業受託、雇用労働
- 担当:中央農研・経営計画部・耕種経営研究室
- 連絡先:0298-38-8420
- 区分:関東東海北陸農業・関東東海・経営
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
水田作経営は米価下落による経営収益の低下傾向から、経営全体のコスト低減と所得向上を目指した経営の確立が強く求められている。ここでは、先ず、水稲作経営における収益性の推移を統計分析によって検討する。次いで、借地および水稲作業の委託希望が多い地域では受け手となる受託農家の確立が重要であり、この点から、借地・作業受託を指向する大規模水田作複合経営を対象に水稲作業受託の導入効果をモデル分析によって検証する。
成果の内容・特徴
- 水稲単一経営における農業所得の推移を平成7年対11年の変化割合でとらえると、5ha以上の規模層で約30%の減少率を示している。しかし、15ha以上(平均:25.6ha)のより大規 模な階層における減少率は10%前後にとどまっている。この較差要因は、大規模層では固定資本額の新たな投入を抑制し、それが経営費の減少に作用しているためと考えられる。
- 借地および作業委託の受け手となる受託農家は、面積規模の大きさに対比して保有労働力の確保が前提となることから、雇用労働有無の面から水稲作業受託の導入の有利性を検討した。分析モデルの制約として、自作地+水田借地:15ha~25ha、畑借地:12.0ha、作業受託:10.0ha(最大)、家族労働:2.5人、雇用労働:2人/日、等を設定した。受託作業は、 ① 播種・育苗、 ②耕耘・代かき、 ③田植え、 ④収穫・乾燥・調整、である。雇用労働が有る場合の結果は、水田借地面積20ha規模までは受託制約面積の10haの作業受託は有利であり、25ha規模では7.9ha水準に減少する。一方、雇用労働が無い場合の結果では、15ha規模で1.9haまでの作業受託が有利であるが20ha規模では選択されない(表2)。
- 作業受託の導入による経営の収益性を未導入の場合に比べてみると、水田借地面積が15ha規模で380万円、20ha規模で620万円、25ha規模では810万円の収益増加が期待できる。この結果から、水稲の作業受託は、通常の家族労働に雇用労働2人/日の労働力が確保されている場合、経営面積規模がほぼ40ha(うち水田面積25ha前後)までは有利に展開しその導入効果が確認される(表2)。
成果の活用面・留意点
- 統計分析による結果は、都府県における水稲作5ha以上の経営を対象としているが、面積規模が大きくなるにしたがい集計戸数が少なくなることに留意する必要がある。
- 作業受託のモデル分析は、茨城県西部地域の水田・畑作複合経営を対象としていることから、分析結果は水稲+畑作の借地型大規模水田作複合経営に適用される。
具体的データ
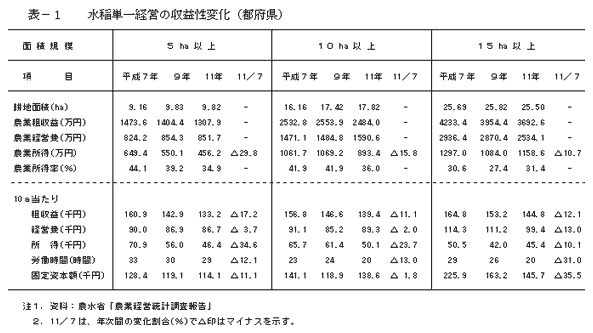
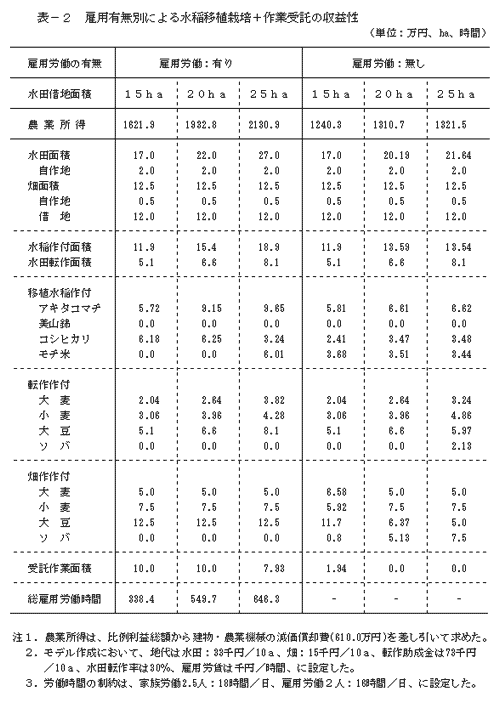
その他
- 研究課題名:高収益輪作営農の定着条件の解明
- 予算区分:21世紀7系
- 研究期間:2001~2003年度
- 研究担当者:佐々木東一
