ジャガイモヒゲナガアブラムシが媒介するダイズわい化病の1次感染時期
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ジャガイモヒゲナガアブラムシが媒介するダイズわい化病の1次感染は、北海道と東北地方北部の異なる地点において毎年ほぼ同時期(5月と6月)に起きる。その原因はウイルス保毒虫の飛来時期が限定されているためである。1次感染がこの時期が限られるため、圃場での茎葉散布の適期は6月末までである。また播種時期を遅らせることにより、わい化病の1次感染を回避することが可能になる。
- キーワード:ダイズわい化ウイルス、SbDV、ダイズわい化病、媒介アブラムシ、1次感染時期
- 担当:中央農研・虫害防除部・害虫生態研
- 連絡先:電話029-838-8939、電子メールkhonda@affrc.go.jp
- 区分:共通基盤・病害虫(虫害)
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
わい化病はダイズの重要な生産阻害要因の一つである。北海道と東北地方北部では、ジャガイモヒゲナガアブラムシが媒介するダイズわい化ウイルス(SbDV-YS)が多発しており深刻な問題となっている。SbDVはLuteoviridaeに属し、媒介様式は循環型・非増殖型である。ダイズへのSbDV-YSの1次感染は、ウイルス保毒クローバ類からダイズ幼苗へ飛来するジャガイモヒゲナガアブラムシ有翅虫によって引き起こされる。わい化病の多発地帯ではこの1次感染を回避するためにダイズ発芽後から殺虫剤の茎葉散布が繰り返されており、生産コストと環境への負荷を増加させている。不要な殺虫剤散布を削減し、的確な防除を行うためには、媒介アブラムシによるウイルスの感染時期を精確に把握し、回避するための技術開発が重要となっている。
成果の内容・特徴
- ダイズ幼苗を一定期間野外に設置しダイズわい化病に感染させる方法で、わい化病の1次感染時期がわかる。
- 北海道と東北地方北部におけるダイズわい化病の1次感染は、異なる地点や年次であっても5月と6月に限定され、7月には起きない(図1)。
- 芽室町と鹿追町で5月から7月までの時期に捕獲されたジャガイモヒゲナガアブラムシ有翅虫のうち、ウイルス保毒虫と判定される個体は5月と6月の捕獲虫にほぼ限られる(表1)。このことから、ダイズわい化病の1次感染時期はクローバ等のウイルス源から保毒虫が飛来する時期によって決まると言える。
- アブラムシ保毒虫によるわい化病の1次感染時期が5月と6月に限定されるため、保毒虫による感染防止のための殺虫剤茎葉散布の適期は6月末までである。また、この時期を避けてダイズを遅播きすれば、わい化病の1次感染を回避することが可能となる。
成果の活用面・留意点
- わい化病多発地帯では1次感染を回避しても圃場内でのアブラムシ増殖による2次感染が起きるため、播種時の粒剤処理は不可欠である。
具体的データ
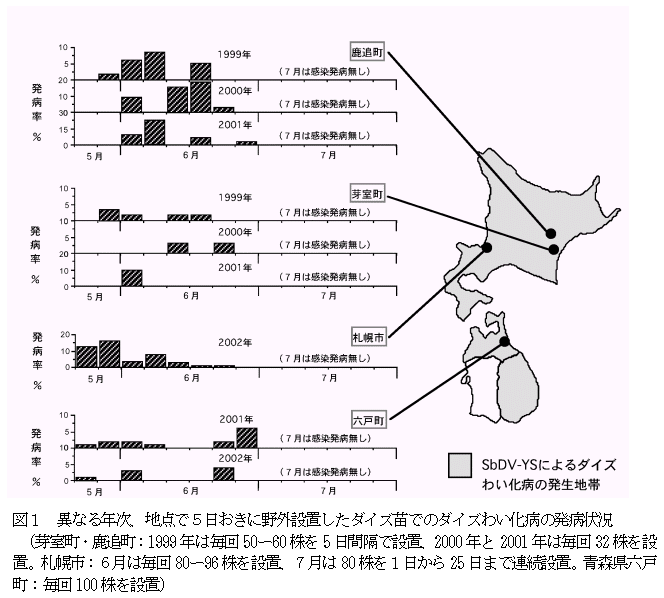
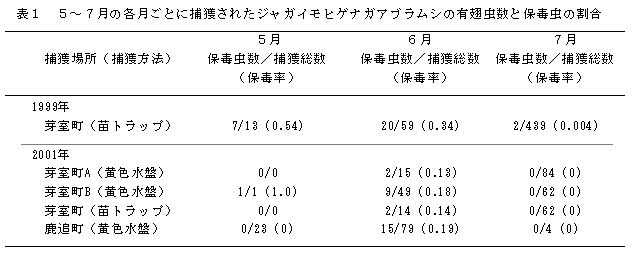
その他
- 研究課題名:ウイルス保毒虫の高精度予殺技術等による害虫防除技術の実証
- 予算区分:IPM
- 研究期間:2002~2003年度
- 研究担当者:本多健一郎、御子柴義郎(畜草研)、渡辺治郎(北農研)、小野寺鶴将(十勝農試)、石谷正博、
松田正利、忠英一、北野のぞみ、桑田博隆(青森畑園試) - 発表論文等:1) 本多ほか(2002)北日本病害虫研究会報, 53: 314
2) 本多(2001)植物防疫, 55: 206-210
