マメアブラムシによるレンゲ萎縮ウイルスの媒介条件とウイルス感染に抵抗性を示すダイズ品種
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
マメアブラムシがレンゲ萎縮ウイルス(MDV)を媒介するためには、15℃で3. 4日以上の獲得吸汁を要する。スズカリなど一部のダイズ品種は、マメアブラムシを使ってウイルスを接種しても感染が起こらず、抵抗性を示す。
- キーワード:レンゲ萎縮ウイルス、MDV、ダイズわい化病、マメアブラムシ、抵抗性品種
- 担当:中央農研・虫害防除部・害虫生態研
- 連絡先:電話029-838-8939、電子メールkhonda@affrc.go.jp
- 区分:共通基盤・病害虫(虫害)
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
わい化病はダイズの重要な生産阻害要因の一つである。わい化病の病原ウイルスにはダイズわい化ウイルス(SbDV)とレンゲ萎縮ウイルス(MDV)が知られており、いずれも限られた種類のアブラムシによって永続的に媒介される。関東地方以西ではMDVによるダイズわい化病の発生が多く、早期栽培のエダマメなどで被害が問題となっている。MDVはNanovirusに属し、媒介様式は循環型・非増殖型である。MDVを媒介するアブラムシとして、マメアブラムシ、マメクロアブラムシ、エンドウヒゲナガアブラムシ、ソラマメヒゲナガアブラムシ、ワタアブラムシが確認されている。ダイズへのMDVの感染は、MDV罹病ソラマメからダイズ幼苗へ飛来するマメアブラムシ有翅虫によって引き起こされる。ウイルス病は一度感染すると治療は不可能であるため、被害を回避するためには媒介虫の徹底防除によるウイルス感染の防止や抵抗性品種の開発が必要である。
成果の内容・特徴
- マメアブラムシがMDVを媒介するためには、15℃の条件下では罹病植物(ウイルス源)上で3. 4日以上の獲得吸汁が必要である。また、80%以上の媒介率を確保するためには、それぞれ6日以上の獲得吸汁と接種吸汁が望ましい(図1)。
- 図2で示した手順により、罹病ソラマメとマメアブラムシを使って実験室条件下でMDVをダイズ苗に接種し、わい化病を発病させることができる。
- ダイズ17品種にマメアブラムシを使ってMDVを接種したところ、12品種ではMDVの感染が起きるが、残り5品種では感染が認められない(図3)。
- MDV感染が起きる品種と起きない品種で媒介虫(マメアブラムシ)の生存率は差がない。したがってウイルスを接種しても感染が起きない品種には、MDVの感染に対する抵抗性が存在すると思われる。
成果の活用面・留意点
- MDVの感染に抵抗性を示すダイズ品種は、今後MDVが病原となるわい化病に対する抵抗性品種を育成するための重要な遺伝資源になりうる。
- 今回発見されたMDV抵抗性を品種育成に活用するためには、その遺伝様式を明らかにする必要がある。
具体的データ
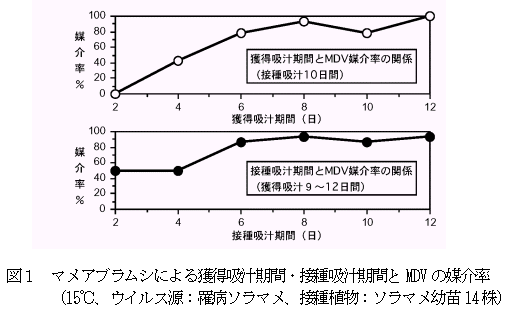
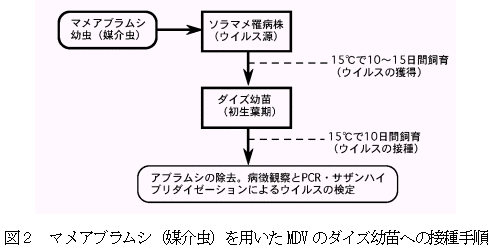
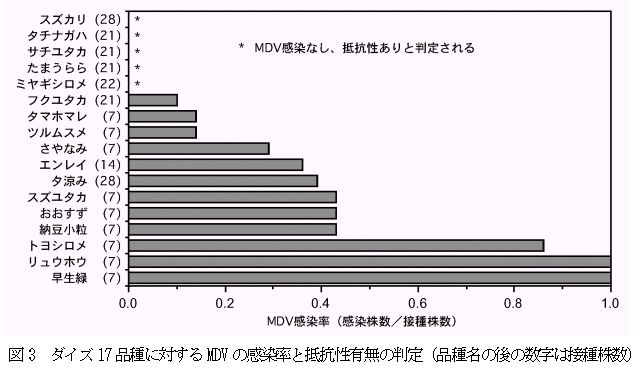
その他
- 研究課題名:ダイズわい化病媒介アブラムシの発生動態の解明
- 予算区分:交付金
- 研究期間:1998~2002年度
- 研究担当者:本多健一郎、御子柴義郎(畜草研)、佐野義孝(新潟大学)
