BIO-PCRによる土壌中からのナス科作物青枯病菌の高感度検出法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
液体選択培地で土壌中のナス科作物青枯病菌を増殖させた後、特異的プライマーを用いてnested PCR(BIO-PCR)を行うことにより汚染圃場から本菌を101cfu/g乾土レベルで検出できる。
- キーワード:ナス科作物青枯病、Ralstonia solanacearum、BIO-PCR、土壌、検出法
- 担当:中央農研・病害防除部・土壌病害研究室
- 連絡先:電話029-838-8836、電子メールnakaho@affrc.go.jp
- 区分:共通基盤・病害虫(病害)
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
Ralstonia solanacearumにより生じる青枯病は土壌伝染性の難防除病害であり、ナス科作物に重大な被害をもたらしている。本病の効果的な防除には土壌中の青枯病菌密度を正確に把握することが重要であるが、選択培地を用いた検出・定量では103cfu/g乾土未満の汚染土壌では青枯病菌を安定的に検出できない。そこで液体選択培地で土壌中の青枯病菌を増殖させた後、特異的プライマーを用いたPCRを行うことにより101cfu/g乾土レベルの汚染圃場から本菌を高感度に検出する方法を確立する。
成果の内容・特徴
- 青枯病菌の病原性関連性遺伝子hpx2の配列からプライマーセットhpx2-A&-B、hpx2-C&-Dを作製した(図1)。hpx2-A&-Bを用いたPCRにより青枯病菌(レース1、生理型3、4)は988bpの産物が認められる。他の植物病原細菌(Pseudomonas、Burkholderia、Herbaspirillum、Acidovorax属細菌)21菌株、植物体及び土壌から分離された細菌7菌株、青枯病菌選択培地(改変SMSA培地)で出現する土壌細菌15株ではPCR産物が認められない。
- 青枯病菌の検出はhpx2-A&-Bを用いた場合、103cfu/mlレベルで、またhpx2-C&-Dを用いたnested PCRでは100cfu/mlの低濃度レベルで可能である(図2)。
- 汚染土壌10g(101cfu/g乾土レベル)を改変SMSA液体選択培地100mlに加え10分間振とうした懸濁液10mlを試験管に移し28°Cで12~24時間浸とう培養する(図3)。培養液90μlに10μlの0.5N NaOHを加え5分間煮沸したものをPCR試料とする。hpx2-A&-Bとhpx2-C&-Dを用いたnested PCRでは12時間以上の培養液で青枯病菌に特異的な145bpの産物が確認される(図4)。
成果の活用面・留意点
- 腐植酸等のPCR反応阻害物質を多く含む土壌ではBIO-PCR法が利用できない可能性がある。
- 土壌中の青枯病菌の定量は既存の選択培地とBIO-PCRを組み合わせることにより可能になる。
具体的データ
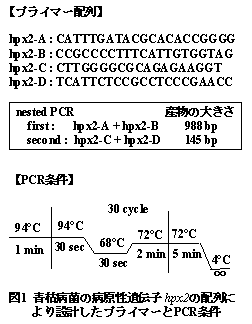
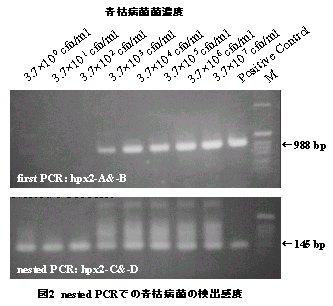
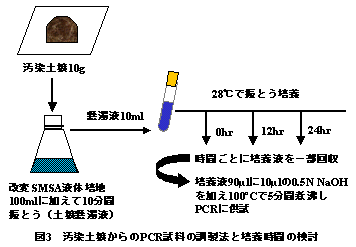
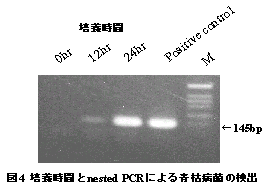
その他
- 研究課題名:青枯病抵抗性誘導因子の特定と発現様式の解明
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2002~2005年度
- 研究担当者:中保一浩、根本和俊(福島県たばこ試)、向原隆文(岡山県生科総研)、井上博喜(近中四農研)、
高山智光(近中四農研)、宮川久義(近中四農研)、竹原利明、仲川晃生
