2種の導入寄生蜂を併用するマメハモグリバエの生物的防除のモデルによる評価
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ハウストマトに発生したマメハモグリバエに対して、導入寄生蜂イサエアヒメコバチとハモグリコマユバチを併用しても種間競争による悪影響は少なく、同じ放飼密度で単独放飼と同様の防除効果が得られることがモデルから予測される。
- キーワード:マメハモグリバエ、トマト、イサエアヒメコバチ、ハモグリコマユバチ、生物的防除、モデル、寄生蜂
- 担当:中央農研・虫害防除部・生物防除研究室
- 連絡先:電話0298-38-8846、電子メールyano@affrc.go.jp
- 区分:共通基盤・病害虫(虫害)
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
施設トマトの主要害虫であるマメハモグリバエに対して、2種の導入寄生蜂イサエアヒメコバチとハモグリコマユバチによる防除技術が殺虫剤の代替技術として実用化されつつある。これら2種はしばしば併用されるが、寄生者間の相互作用が研究されておらず、最適な利用技術は検討されていない。マメハモグリバエを攻撃する両種の寄生蜂の相互作用を組み込んだ個体群相互作用モデルを作成し、天敵の最適利用技術を開発する。
成果の内容・特徴
- モデルはVisual Basicでマメハモグリバエと2種寄生蜂の発育、死亡、産卵過程を記述したシミュレーションモデルである。また寄生蜂の寄主発見率は寄主密度に比例すると仮定されている。
- モデルには、イサエアヒメコバチが遭遇したハモグリバエ幼虫に対して、寄生または寄主体液摂取(一種の捕食行動)を行い、寄主体液摂取により摂取した栄養で蔵卵する過程が組み込まれている。(図1)。また実験結果及び文献情報に基づき、ハモグリコマユバチに寄生されたハモグリバエ幼虫に遭遇したイサエアヒメコバチは、未寄生個体と区別せず寄生または寄主体液摂取により攻撃し、寄主とともに内部に存在するハモグリコマユバチの卵・幼虫を殺すと仮定されている。
- モデルのシミュレーションにより以下のことが予測された。
(1)イサエアヒメコバチやハモグリコマユバチを単独で3回放飼した場合、それぞれを半分の密度で同時に
3回放飼した場合と効果はほぼ同じである。両種の寄生蜂の種間競争による効果の低下は認められない(図2)。
(2)両種の寄生蜂を同時放飼する混合剤を利用する場合の混合比率は、ほぼ半々にすると最も効果が高い。
成果の活用面・留意点
- モデルには温室内の温度変化、トマトの葉面積成長が組み込まれていて、施設トマトの種々の作型における放飼効果の予測ができる。
- モデルに種々の寄生蜂の放飼時期、放飼密度を入力することにより、効果的な寄生蜂の放飼方法が予測できる。
具体的データ
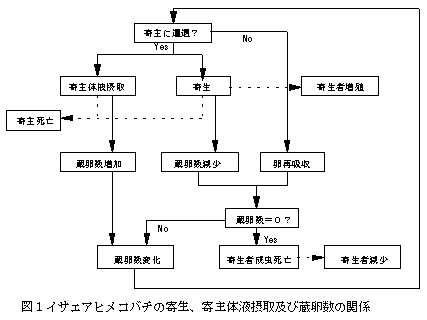
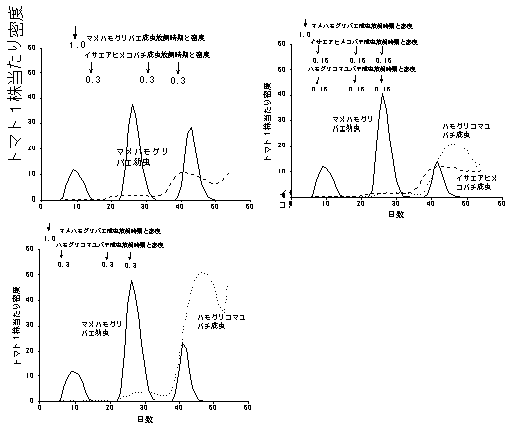
その他
- 研究課題名:寄生性天敵利用等による害虫防除技術の実証
- 予算区分:IPM
- 研究期間:2002~2003年度
- 研究担当者:矢野栄二
