光センサーみかんの認知と表示による消費者評価の向上方策
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
温州みかんに光センサー選果が導入されて5年以上経過するが、その内容を理解している消費者は約3割である。認知していない消費者は、光センサーという表示で評価がマイナスになるため、果実産地は消費者に正確な情報を伝達し評価を高める必要がある。
- キーワード:消費者、認知、選択型コンジョイント分析、マーケティング、光センサー
- 担当:中央農研・経営計画部・マーケティング研究室
- 連絡先:電話0298-38-8851、電子メールkono@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・関東東海・経営
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
熊本県のある産地では、光センサー(糖度・酸度を基準に選別)を導入して選果した温州みかんを「光センサーみかん」のシールを貼って売り出したが、売上げは向上しなかった。その一因として、そうした情報が消費者に伝わらずに、消費者の評価が向上していないことが上げられる。
そこで、消費者に対する選択型コンジョイント分析を用いたアンケート調査に基づき、従来からの卸売市場を中心にしたマーケティング活動では、消費者に十分な情報伝達ができていないこと、情報の伝達が十分か否かがみかんの評価に影響することを明らかにする。なお、調査は、首都圏の茨城県牛久市(本調査)、神奈川県横浜市(補足調査)において、NTTの電話帳を用いて調査対象者を無作為に抽出して郵送でアンケート用紙を配布した。有効回答数は、牛久市は361人、横浜市は245人であった。
成果の内容・特徴
- 温州みかんに光センサーが導入されたのは1996年であるが、首都圏の消費者の認知度は、光センサーを「知っている」、「聞いたことがある」、「知らない」人が1/3ずつであり、十分に浸透しているとは言えない。
- 選択型コンジョイント分析の設問の前に光センサーについての詳細表示(図1左)を行った場合、「知っている」と答えた人の光センサーの評価の推定値は1.10であり、A県産と比較して最も評価の低いB県産のマイナス評価(-0.91)を補えるため、B県産のみ光センサー選果を導入すると、評価が最も高くなる。また、「聞いたことがある」、「知らない」人も、光センサーの評価は推定値でそれぞれ0.82、0.78で、評価の最も低い県が光センサーを導入するとほぼA県と同等の評価になる(表1左)。
- しかし、簡単表示(図1右)のように光センサーとのみ表示し、光センサーの説明を省いた場合は、「知っている」人の光センサーの評価は、0.43と低くなり、B県産のみ光センサーを導入してもA県産の評価に届かない。さらに、「聞いたことがある」、「知らない」人の光センサーの評価は、-0.21、-0.71となり、光センサーと表示することによって評価がマイナスになることが明らかになった(表1右)。
- 以上から、図1のように「光センサーとは?」や「光センサーを使うとどうなるの?」についての内容を店頭等に表示して、消費者の評価を高める必要がある。
- この結果を踏まえて熊本県産の光センサーみかんを販売しているある小売店では、詳細表示を開始し、消費者評価の向上につながっている。
成果の活用面・留意点
新技術を導入した場合には、小売店の店頭POP等で消費者に直接情報を伝達する必要がある。
具体的データ
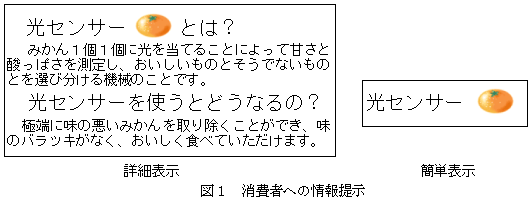
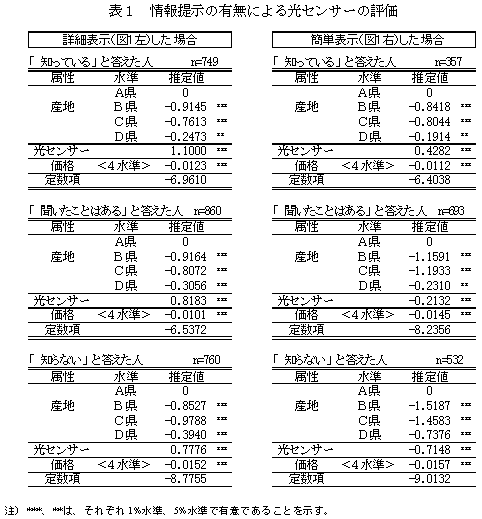
その他
- 研究課題名:都市近郊青果物産地における販売戦略策定支援手法の開発
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2002~2005年度
- 研究担当者:河野恵伸、大浦裕二、合崎英男(農工研)、杉谷将洋(熊本普及センター)
