抗生物質耐性遺伝子を使わない新しい遺伝子組換えイネ選抜技術
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
従来の抗生物質耐性選抜マーカー遺伝子に代わる細胞選抜技術として、イネに内在するアセト乳酸合成酵素遺伝子の変異型を、カルス特異的プロモーターによって駆動し、選抜マーカーに用いる新しい方法を開発した。この方法によって、選抜マーカー遺伝子がカルスでは発現するが、葉や米では発現しない組換えイネを開発することができる。
- キーワード:イネ形質転換、選抜マーカー遺伝子、アセト乳酸合成酵素、カルス特異的プロモーター
- 担当:中央農研・北陸地域基盤研究部・稲育種工学研究室、上席研究官室
- 連絡先:電話025-526-3238、電子メールmohshima@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・北陸・生物工学
- 分類:科学・普及
背景・ねらい
遺伝子組換えは非常に稀にしか起こらない現象であるため、形質転換細胞だけを選抜するマーカー遺伝子の使用が必須である。これまでは選抜マーカー遺伝子としてバクテリア由来の抗生物質耐性遺伝子を植物体の全身で高発現する構造としたものを用いる場合が多く、可食部でも発現するため、遺伝子組換え農作物に対する消費者の懸念の一因になってきた。国際的には安全性への配慮から抗生物質耐性遺伝子の使用を制限する動きがある。このため、特許権が設定された従来の抗生物質耐性遺伝子に代わり、安全性に配慮された新しい選抜マーカー遺伝子による選抜技術の開発が強く求められている。
成果の内容・特徴
- 開発された新規の形質転換用ベクターpTA1は選抜マーカー遺伝子をカルス特異的プロモーターによって駆動することにより、その発現をカルスに限定し、イネの葉や米など、その他の部位では発現しない形に構築したものである(図1)。
- 選抜マーカー遺伝子として使用している変異型アセト乳酸合成酵素(ALS)遺伝子は自然突然変異によって生じたイネの遺伝子であり、プロモーター及びターミネーターもイネ由来のものであって、消費者の安心感の醸成に役立つ。選抜は従来の抗生物質耐性遺伝子の場合と同じ方法により、除草剤であるビスピリバックナトリウム塩(BS,0.5μM)への耐性を指標として行われる。
- 従来の抗生物質耐性遺伝子を用いる選抜法と比較して、形質転換体の出現はやや遅れるものの、形質転換体の選抜効率は従来の抗生物質耐性遺伝子と同等であり、エスケープは認められない(図2)。
成果の活用面・留意点
- この方法はイネに特化した新規の選抜技術として開発されたものであり、イネ以外の作物種への適用については未検討である。
- 目的遺伝子を緑葉特異的プロモーターに接続し、このベクターを使ってイネに導入することによって、目的遺伝子が葉のみで発現し、その他の組織では選抜マーカー遺伝子、目的遺伝子のどちらも発現しない組換えイネを作出することが可能である。
- この成果は中央農業総合研究センター、農業生物資源研究所、クミアイ化学工業株式会社がそれぞれ開発した要素技術を総合化することによって達成されたものであり、それぞれ特許権を取得または申請中であって、実用的利用への支障はない。
- 形質転換体のノーザン解析等によって、選抜マーカー遺伝子はカルス中では高発現しているが、葉及び米粒中では発現していないことが確認された(表)。
具体的データ
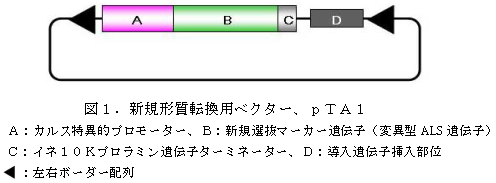
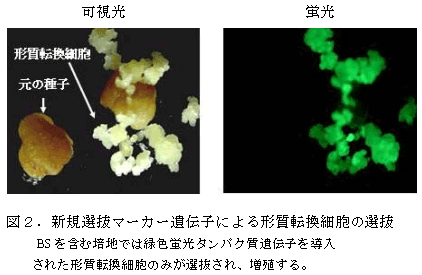
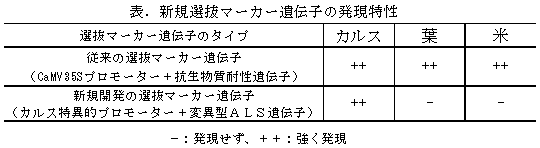
その他
- 研究課題名:安全性に配慮した実用的な病害抵抗性組換えイネ系統の開発
- 予算区分:融合研究
- 研究期間:2001~2002年度
- 研究担当者:大島正弘、吉田均、松村葉子、黒田昌治、大槻寛、黒田秧、田中喜之(生物研)、
田中宥司(生物研)、大竹祐子(生物研)、番保徳(生物研)、井沢典彦(クミアイ化学(株))、
清水力(クミアイ化学(株))、角康一郎(クミアイ化学(株))、永山孝三(クミアイ化学(株))
