大豆用耕うん同時畝立て播種作業技術
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
重粘土転換畑で、耕うんしながら同時に畝を立て、大豆を播種する作業技術である。アップカットによる同時作業のため、作業時間が短縮するとともに所要動力が削減される。さらに土中酸素濃度が高くなり、生育初期の乾物重が増加して大豆収量が多くなる。
- キーワード:重粘土転換畑、耕うん同時畝立て、大豆、土中酸素濃度
- 担当:中央農研・北陸総合研究部・総合研究第2チーム
- 連絡先:電話025-526-3235、電子メールhosoh@naro.affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・北陸・経営作業技術、関東東海北陸農業・北陸・総合研究
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
転換畑で大豆を栽培する場合、北陸地域では重粘土が広く分布しているため、湿害が問題である。とくに、初期の湿害による生育停滞は、生育後期にまで影響するため、播種時期から湿害回避に考慮した土壌環境を整えることが必要である。
そこで、耕うんと同時に畝立てを行い、大豆を播種することにより、湿害を回避する作業技術を開発するとともに、その効果を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 耕うん爪取付方式がホルダー型のアップカットロータリの爪配列を、畝中心に土が移動するように取り付けることにより、1工程で耕うんと同時に75cm×2畝もしくは、150cmの畝を作成することができる(図1)。
- 耕うんと同時に畝を作ることにより、アップカット耕うんのみに比べて所要動力が低減し、砕土率は低下しない。所要動力の低減効果は、150cmの畝よりも75cmの畝で大きくなる(図2)。
- ダウンカット方式では、砕土性を維持するため0.1m/s以下で走行する必要があるのに対し、アップカット耕うんでは、砕土性が高いため0.2~0.4m/sで走行でき、作業時間が短くなる。
- 畝立てを行うことにより、畝表面からの地下水位の低下等により、降雨後の土中酸素濃度の低下が少なくなる。その効果は、150cmの畝よりも75cmの畝で顕著である(図3)。
- 畝立て栽培は、最初に畝を作らない耕うんのみの栽培より大豆生育時期の乾物重が増加し、生育が良好になる。さらに、畝立て栽培は収穫期の主茎長が長く、最下着莢高が高くなるとともに収量が多くなる(表)。
成果の活用面・留意点
- 本試験内容は、前年度水稲を作付けた新潟県上越市の重粘土転換畑(LiC)のデータである。
- 畝立ての有無にかかわらず、中耕培土は1回実施し、その他の作業は、地域栽培指針に準じて実施している。
具体的データ
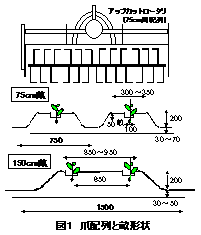
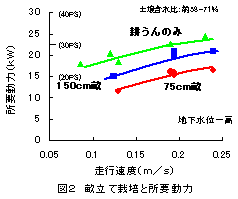
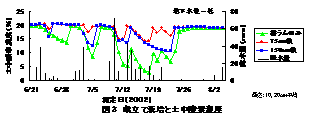
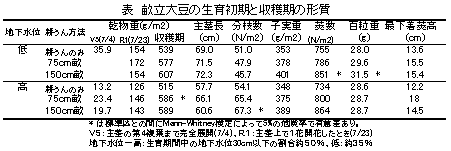
その他
- 研究課題名:畑作物・野菜を組み込んだ転換畑輪作技術の開発
- 予算区分:多雪地帯畑作
- 研究期間:1997~2003年度
- 研究担当者:細川 寿、高橋智紀、松﨑守夫
