トリフルラリン剤処理と播種期移動による麦作のカラスムギ防除
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
麦作の強害草カラスムギに対して,既登録除草剤ではトリフルラリン剤の効果が最も高いが50%程度の抑制で,麦の晩播によるカラスムギの発生密度低減との組合せで防除効果が向上する。
- キーワード:麦作、カラスムギ、播種期、晩播、トリフルラリン、雑草防除
- 担当:中央農研・耕地環境部・畑雑草研究室
- 連絡先:電話029-838-8426、電子メールmasai@affrc.go.jp
- 区分:共通基盤・雑草、関東東海北陸農業・関東東海・水田畑作物
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
関東東海地域の麦作においてカラスムギの被害が一部地域で顕在・常態化しており,麦作振興上の大きな阻害要因となっている。安定多収栽培技術確立のため,慣行栽培体系における既存技術の組合せによる有効な防除手段として,トリフルラリン剤および播種期移動によるカラスムギ防除効果とその変動要因を解明し,防除技術を確立する。
成果の内容・特徴
- 麦作の既登録土壌処理・茎葉兼土壌処理剤では有効成分にトリフルラリンを含む除草剤の効果が高い(表1)。
- トリフルラリン有効成分量の増加に伴って防除効果が高まり,関東地域における普通播種期(11月上旬)におけるトリフルラリン剤の登録最大薬量(有効成分1.34kg/ha)処理でカラスムギ生残数はほぼ半減する(図1)。その場合でも,収穫期のカラスムギ種子生産量は初期の種子密度を大きく越える(図2)。したがって,トリフルラリン処理にのみ防除を依存した体系では次年度のカラスムギ増加が抑えられない。
- 麦播種期を遅延させると,播種前に発生して耕耘で死滅するカラスムギが多くなるため,播種後に発生して収穫期まで生存するカラスムギ密度が減少する。播種期をカラスムギ発生盛期(本試験では11月下旬)以降に移動することで密度が大幅に低下し,種子生産量は初期密度以下になる(図2)。播種期の遅延とトリフルラリン乳剤処理を組み合わせることで高い防除効果が得られる。
成果の活用面・留意点
- カラスムギの侵入した畑圃場および固定転換畑において麦類を栽培する場合,カラスムギの蔓延を防止するために有効である。
- 関東地域で麦作前に夏作物を耕起体系で栽培した条件を前提とした結果である。
- 暖冬年以外は晩播による減収が生ずるので,播種密度を増やすなどの対策をとる。
- カラスムギの出芽特性には種内変異があり,本試験で供試した集団より出芽の遅い集団の存在が確認されている。そのため,出芽の遅い集団に対しては,普通期のトリフルラリン剤処理,晩播それぞれ単独の効果が低下する可能性がある。
具体的データ
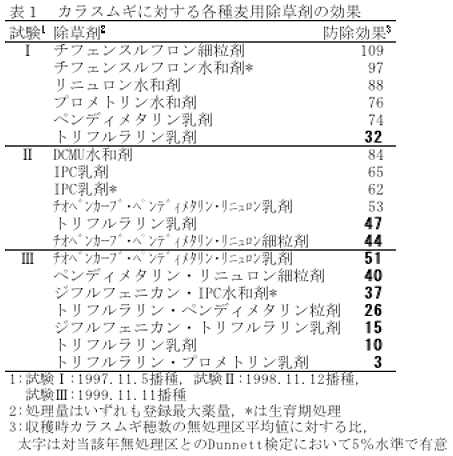
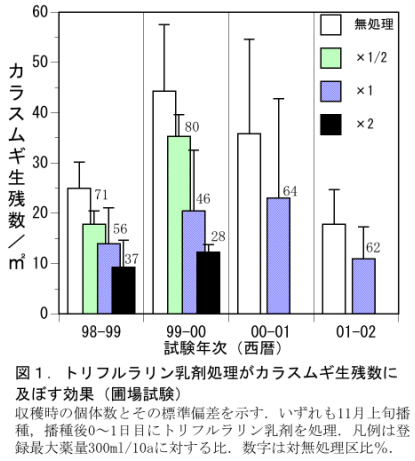
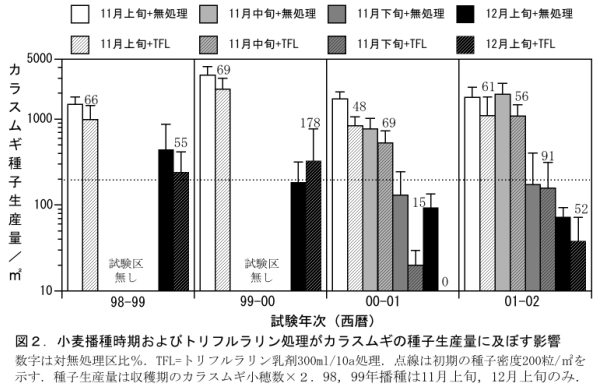
その他
- 研究課題名:麦作における強害イネ科雑草等の生態解明と防除技術の確立
- 予算区分:(麦緊急開発)21世紀プロ1系
- 研究期間:2001~2004年度
- 研究担当者:浅井元朗、與語靖洋
