畑化後の年数がダイズ子実のカドミウム濃度に及ぼす影響
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ダイズの子実中カドミウム濃度は水田を畑化した初年目に高く、2年目に低下して、以降は明確な増減傾向を示さない。
- キーワード:ダイズ、カドミウム、転換畑、土壌
- 担当:中央農研・土壌肥料部・土壌管理研究室
- 連絡先:電話0298-38-8827、電子メールsumi@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・関東東海・土壌肥料
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
CODEX委員会において、食品中のカドミウム(Cd)濃度について基準値が検討されており、農作物中のCd濃度を低減させる条件の解明と、必要な対策技術を開発することが求められている。このような中で水田転換畑のダイズ栽培は、ダイズ栽培面積の主体を占めており、転換畑の履歴、利用状況などがダイズ子実のCd濃度に及ぼす影響を明らかにすることが重要である。
そこで、畑化後のダイズ栽培年数が子実のCd濃度に及ぼす影響を調べた。
成果の内容・特徴
- 数種の灰色低地土、谷和原淡色黒ボク土、赤黄色土などにおいて水田を畑化し、ダイズ(主としてタチナガハ)を数年にわたって栽培して、畑化後のダイズ栽培年数と子実中のCd濃度の関係を調査した。供試圃場はいずれも非汚染土壌である。
- ダイズの子実中カドミウム濃度は、水田から畑に転換した初年には高い傾向が認められる。畑化2年目は初年目より低く、以降は明確な増減傾向を示さない。この現象は、異なる栽培年次(表1)、稲わら施用条件の異なる圃場(表2)、異なる土壌型の圃場(表3)、タチナガハ以外の品種(表4)においても共通して認められる。
- ダイズ子実中のCd濃度が高いことが想定されるような圃場においては、可能であれば畑化初年にはダイズの作付けを避け、2年目以降にダイズを栽培することによって、生産されるダイズ子実中のCd濃度が低くなる可能性があると考えられる。
- 土壌pHはダイズ子実中のCd濃度と関係があることが知られているが、この畑化後の年数との関係に関しては、土壌pHとの間に密接な関係は認められない(表1~3)。
- 風乾土壌から0.1N塩酸あるいはpH7酢酸アンモニウムで抽出される土壌Cd濃度は、畑化後年数の経過に関して格別の増減傾向を示さない。(表1)。
成果の活用面・留意点
- 転換畑にダイズを継続して作付けする場合には、黒根腐れ病、線虫など連作にかかわる障害が生じる可能性があるので注意を要する。
具体的データ
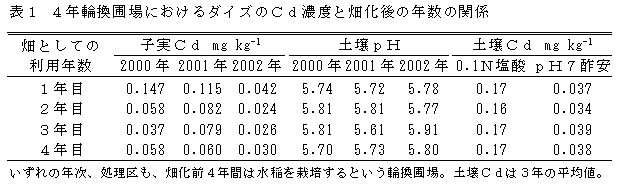
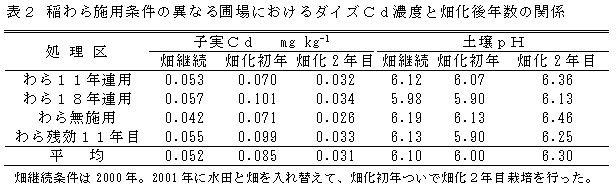
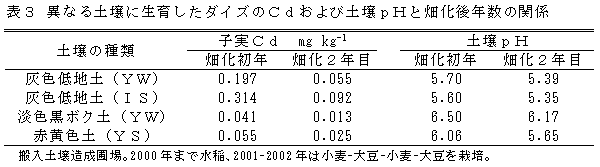
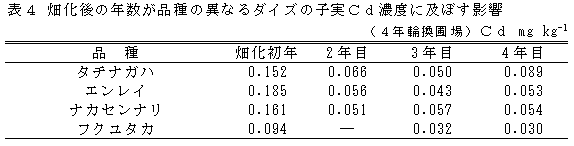
その他
- 研究課題名:カドミウム対策土壌の転換畑化によるリスク評価
- 予算区分:カドミウム
- 研究期間:2000~2002年度
- 研究担当者:伊藤純雄、近藤始彦、高橋 茂
