重粘土転換畑における作土粗孔隙の通気特性
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
重粘土転換畑の作土粗孔隙の気相率、相対ガス拡散係数、通気係数には、相互に直線関係が認められる。各回帰式の回帰係数は栽培される作物によって異なり、その値は毛管径などを用いた毛管モデルで説明できる。
- キーワード:相対ガス拡散係数、通気係数、気相率、毛管径、屈曲度
- 担当:中央農研・北陸水田利用部・水田整備研究室
- 連絡先:電話025-526-3233、電子メールadachi@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・北陸・経営作業技術
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
北陸地域は年間を通して降水量が多く、しかも、重粘土水田が広く分布する。そのため、重粘土水田で畑作物を安定的に栽培する場合、排水性を改善し、作物に適した土中酸素濃度を確保する必要がある。土中の酸素濃度は大気との濃度差で拡散によって、圧力差で移流によって交換される。これらガスの動きやすさを、ガス拡散係数と通気係数という。特に、排水性の悪い転換畑では、微細孔隙は水で満たされていることが多く、土中の酸素濃度等の推定のためには、大きな孔隙(粗孔隙)の水が排水された直後のガスの動き易さ等の通気特性の解明が重要である。
大豆ー大麦ーキャベツの二年三作が行われている四つの重粘土転換畑の作土を採取し、pF1.5(-3.1kPa)の含水比に試料を調整し(粗孔隙の水を排水し)、気相率、ガス拡散係数、通気係数を測定し、相互の関係を明らかにする。なお、相対ガス拡散係数は、大気中のガス拡散係数に対する土中でのガス拡散係数の比で表わされる。
成果の内容・特徴
- 重粘土転換畑の作土粗孔隙の気相率、相対ガス拡散係数、通気係数相互の関係は、それぞれ直線で表される((1)~(3)式)。大豆収穫後の通気係数と相対ガス拡散係数の一例を図1に、気相率と相対ガス拡散係数、通気係数の一例を図2に示す。
- 各直線の回帰係数は、大豆後、大麦後及びキャベツ後の土壌によって異なる(表1)。
- 毛管径が均一な毛管モデルに、ガス拡散現象にはフィックの法則を、移流現象にはハーゲン・ポアズイユの法則とダルシー式を適用すると、各関係式の回帰係数は毛管径、毛管の屈曲度、通気特性に関与しない間隙を用いて説明される((4)~(6)式)。同じ通気係数の土壌では、毛管径が大きな土壌ほど相対ガス拡散係数は小さな値となる。また、同じ気相率の土壌の場合、屈曲度が大きいほど相対ガス拡散係数、通気係数が大きくなる。なお、屈曲度は直管が1で、曲がりくねっている管ほど値は小さくなる。
- 大豆後、大麦後及びキャベツ後の土壌の通気特性は、毛管径、屈曲度、通気特性に寄与しない間隙量で説明される(表1)。
成果の活用面・留意点
- A圃場は転換後8年目で軽埴土(LiC)、B、C、D圃場は転換後4年目で、重埴土(HC)の結果である。
- 気相率と相対ガス拡散係数、気相率と通気係数の関係式は、重粘土転換畑の土壌中のガス交換の予測に用いられる。
- 通気特性の係数を用いて、毛管径、屈曲度及び寄与しない間隙などの粗孔隙構造の相対比較が可能である。
具体的データ
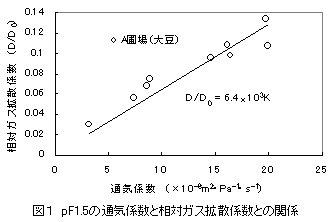
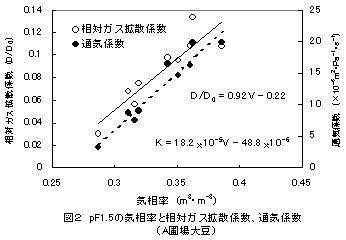

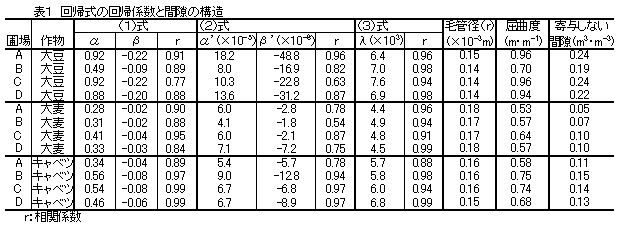
その他
- 研究課題名:重粘土転換畑の通気特性の解明
- 課題ID:03-11-05-01-02-02
- 予算区分:交付金
- 研究期間:1998~2002年度
- 研究担当者:足立一日出、吉田修一郎
- 発表論文等:1)足立・吉田・細川 (2001) 農土論集 215:49-55.
