個別担い手経営の規模拡大を可能にする集落営農システム
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
個別担い手経営の規模拡大のためには、集落営農を組織化し、土地利用調整を実施し農地を団地的に集積することが効果的である。そのためには、個別担い手経営以外の農家に対して、組織に参加することに伴う長期的な「誘因」を提供することが有効となる。
- キーワード:担い手、集落営農、意志決定、成果配分、長期的誘因
- 担当:中央農研・経営計画部・地域営農研究室
- 連絡先:電話029-838-8852、電子メールakihiro@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・関東東海・経営
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
水田農業において個別担い手経営の育成・確保は重要な課題である。そのためには、地域の農家を集落営農に組織化することを通じて、それら農家の協力のもとで、担い手の規模拡大を進めることが有効である。そのための集落営農システムの提示が求められている。
成果の内容・特徴
- これまでの集落営農は、個別担い手経営(以下、担い手)を含めた全ての農家を包摂し、集落全戸に共通する目的を達成する活動を行ってきたものが多い(図1)。しかし、こうした営農システムのもとでは、集落全体で共通してプラスの効果が発揮できる転作等の団地化は可能だが、特定の担い手のみに利益が生じる土地利用調整は困難である。
- 担い手に農地集積していくには、担い手以外の営農継続を希望する農家や農地貸付世帯に対して、各々の主目的に応じた「誘因」を集落営農を通じて提供し、担い手の農地集積や経営発展に向けた人的・物的支援を引き出すシステムを構築する必要がある。
- 調査事例では、担い手に農地を集積する一方で、営農継続を希望する兼業・高齢農家には、(1)組織化を通じた効率的・長期的な稲作の継続を支援し、(2)集落の転作は、担い手が担当し、(3)集落全体で機械を装備し、営農継続農家の組織に貸与している。また、農地貸付世帯には、(1)兼業に特化できるように、担い手を特定化し、安定的な農地貸借を保証し、(2)離農を前提とするのではなく、定年退職後の営農再開を営農継続農家の組織への参加によって保証するなど、各々が求める「誘因」が提供されている(図2)。
- これら「誘因」の提供により、担い手以外の農家から、(1)集落全体での土地利用調整による担い手への農地の団地的提供への合意と、(2)営農継続農家の組織は借地を実施しないことの表明、(3)農地貸付世帯まで含めた全戸からの出資・出役の提供により担い手への機械の貸与や共同育苗苗の提供が可能になっている。いわば、それら農家自身の優先度は相対的に低いが他者の目的達成に役立つ「貢献」が引き出されている(図1)。
- これら関係を構築しても、「誘因」と「貢献」のバランスが図れなければ、特定の農家の負担感が増加する恐れがある。しかし、調査事例では、農地貸付世帯に対してまでも、農地貸付の長期安定的な継続による兼業への特化や将来的な営農再開に対する期待といった長期的視点での「誘因」を提供し、集落営農に継続して参加することに伴うメリットを提供することで、たとえ、短期的には「貢献」負担(出資や出役)が生じても、それを容認する意識が形成できている(図3)。
- こうした長期的視点での「誘因」を内在した新たなシステムを採用することで、担い手以外の農家から、担い手の規模拡大や発展に向けた支援を引き出すことが期待できる。
成果の活用面・留意点
- 行政や普及組織が、担い手と地域の共存を図る組織化を進める際に有効な知見を提供できる。
- 農地貸付後も定住し世帯数が維持できる地域を想定している。従って、他出が進み、農家間の相互関係が長期的に維持できない地域では、別途の方策が必要である。
具体的データ
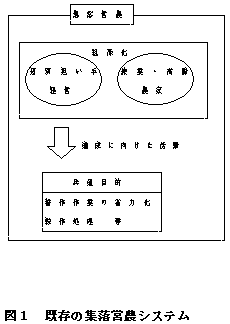
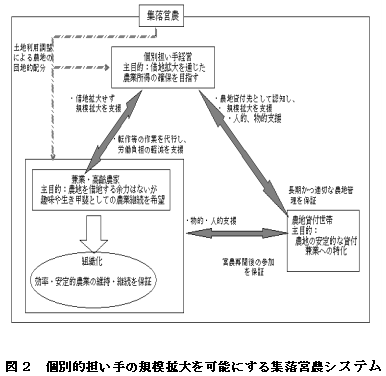
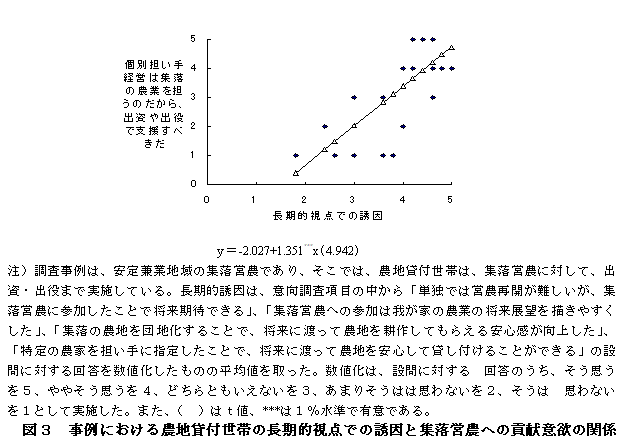
その他
- 研究課題名:地域条件に応じた集落営農組織と担い手との連携メカニズムの解明
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2000~2002年度
- 研究担当者:高橋明広
