狭ピッチ切断部による大豆コンバイン頭部損失低減効果
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
普通コンバイン用切断部の刈刃の切断角を小さく、受刃ピッチを狭くすることで、切断による茎の前方への飛び出しを抑えることができ、大豆の頭部損失を低減することができる。
- キーワード:大豆、普通コンバイン、切断部、切断角、頭部損失
- 担当:中央農研・作業技術研究部・機械作業研究室
- 連絡先:電話029-838-8813、電子メールumeda123@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・作業技術、共通基盤・作業技術
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
コンバインによる大豆収穫作業では、刈遅れや低主茎長による収穫損失が問題となっている。収穫損失の内訳は9割近くを頭部損失が占めており、その内刈残し損失の割合は低く、裂莢損失および落莢損失の割合が高いことが知られている。
そこで、高速度カメラによる普通コンバイン収穫時における茎の挙動の観察と室内での切断モデル試験によって頭部損失の発生要因を解析し切断部改良指針を明らかにする。さらに、その指針に従って切断部を改良し頭部損失の低減を図る。
成果の内容・特徴
- 圃場収穫時には、①切断される時に前方に押し倒された茎とリールが衝突し裂莢する、②切断されて前方に飛び出した茎がプラットフォームから落ちる等の現象が観察される。すなわち、切断による茎の前方への飛び出しが頭部損失の要因の1つである。
- 刈取り時の茎の動きを図1に示す。茎は刈刃と接触して(①)から切断される(②)までに側方と前方に押される。側方へ押された距離(作用距離)が短いほど、茎の重心速度は低い(図2)。また、標準刃(切断角35°)と細刃(切断角20°)では同じ作用距離の場合細刃のほうが重心速度は低い。すなわち、作用距離が短く切断角を小さくすることで茎は前方へ飛び出しにくい。
- 狭ピッチ切断部は自脱コンバイン用刈刃(切断角20°、50.8mmピッチ)と50.8mmピッチ受刃から構成されている(図3)。狭ピッチおよび標準切断部について作業速度を変えた場合の頭部損失を図4に示す。全試験区の平均は狭ピッチが1.1%、標準が2.2%で、狭ピッチの方が頭部損失が少ない。
成果の活用面・留意点
- 大豆水分が低く頭部損失が高い状況で有効である。
- 耐久性等について今後検討する必要がある。
具体的データ
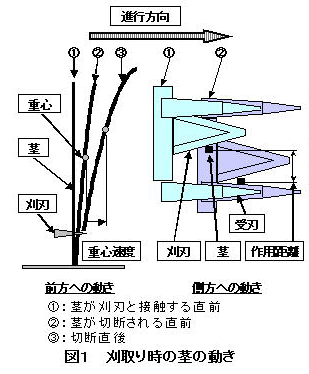
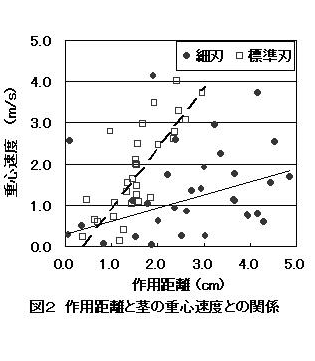
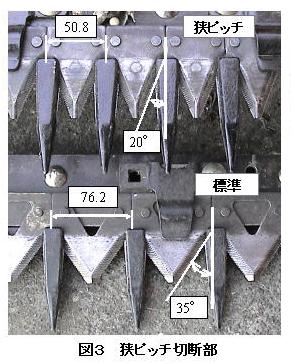
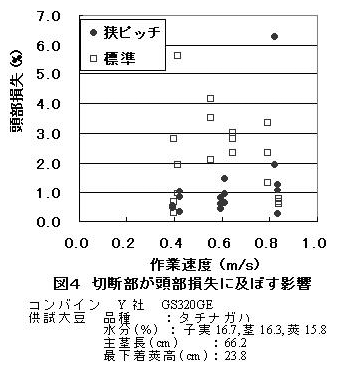
その他
- 研究課題名:汎用コンバインによる収穫ロス低減技術の開発
- 課題ID:03-01-01-01-12-03
- 予算区分:ブラニチ2系
- 研究期間:2002~2005年度
- 研究担当者:梅田直円、金谷豊、長坂善禎
