湿害大豆の形態的特徴と被覆尿素による湿害軽減技術
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
北陸地方の重粘土転換畑では、梅雨時の湿害を被った大豆は、下位分枝に着生する莢数の減少によって減収する。しかし、100日タイプの被覆尿素を基肥に施用することで、湿害大豆の莢数および収量は増加する。
- キーワード:ダイズ、湿害、重粘土転換畑、被覆尿素、梅雨、莢数
- 担当:中央農研・北陸総合研究部・総合研究第2チーム
- 連絡先:電話025-526-3235、電子メールmatsu@naro.affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・北陸・生産環境、共通基盤・土壌肥料
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
北陸の重粘土転換畑では、転換初期は排水性が悪く、高水分環境にあるが、そのような条件では湿害による減収が問題となる。湿害圃場の大豆は、梅雨時に葉色 が淡くなり、窒素欠乏が明らかとなる。そこで、根粒活性を阻害しにくい被覆尿素を用い、施肥で湿害を軽減する技術を開発する。
成果の内容・特徴
- 北陸地方の梅雨(6月下旬~7月中旬)は大豆の花芽分化期に当たり、湿害が発生しやすい時期となる。梅雨時に湿害を被った大豆では、収量・莢数などが減少し(図1)、莢数の減少は、特に第3単位(第2葉を含む植物単位)など、生育前半に発生し、莢数への寄与が大きい下位の分枝で著しい(図2)。
- 100日タイプの被覆尿素を施用すると、湿害を受けた大豆の収量、莢数、百粒重は増加する(図1)が、湿害が発生しない場合には被覆尿素の効果はみられない。被覆尿素による莢数増加は、主に下位分枝の莢数が増加することに由来する(図2)。
- 湿害を受けた大豆に対する被覆尿素の効果は、100日タイプ以外に40日(収量、百粒重の増加)、70日(固定窒素集積量の増加)にもみられる(データ省略)。40日~100日タイプの被覆尿素は開花始以前の溶出量が多い(図3)。重窒素法による窒素利用率は、100日タイプで26.3%と最も高く(40日11.9%、70日18.3%)、溶出窒素が効率よく吸収される100日タイプの効果が高い。
- 施肥方法では、100日タイプの5kgN/10a条施用では莢数の増加が著しく、10kgN/10a全面施用と同様の効果が得られる(図4)。従って、条施用することで被覆尿素の施用量削減を図ることができる。
成果の活用面・留意点
- 試験は重粘土転換畑において梅雨時の湿害を対象に行ったものであり、他の土壌、気象条件においては被覆尿素の効果が異なる可能性がある。
- 供試品種はエンレイ、播種期は5月下旬、播種密度は16,600本/10a、基肥窒素施用量は2kgN/10aであり、平畝で栽培した。約10cmの作土の下はグライ層となる。
具体的データ
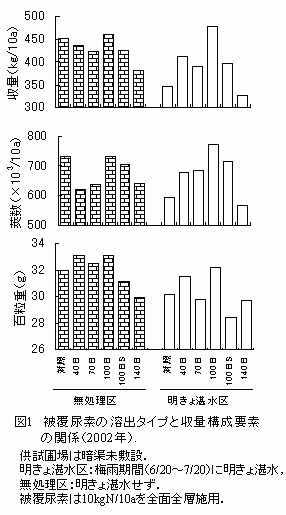
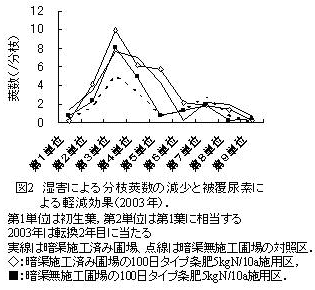
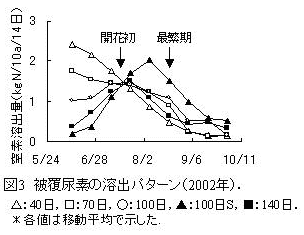
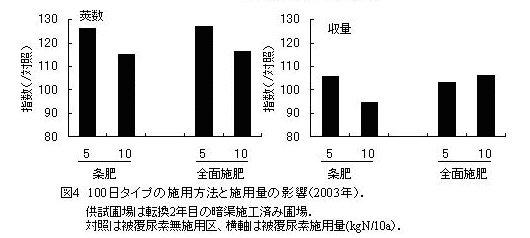
その他
- 研究課題名:転換初期における大豆の生育制御技術の開発
- 課題ID:03-02-02-01-07-03
- 予算区分:交付金(多雪地帯畑作)
- 研究期間:2001~2003年度
- 研究担当者:松崎守夫、高橋智紀、細川寿
