担い手経営の麦・大豆作による転作受託行動の予測
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
担い手経営が転作の受託拡大行動を起こすには、担い手への委託料金、続いて転作団地化が重要な動因となる。収量安定、麦・大豆価格各8,000円 /60kgの場合、委託料金0円であっても4haの団地であれば、調査農家の約8割にあたる12~13戸の農家で転作受託拡大行動が生じ、その際の転作受 託需要は約170haと推計される。
- キーワード:転作、団地、委託料金、受託拡大行動
- 担当:中央農研・経営計画研究部・地域営農研究室
- 連絡先:電話029-838-8566、電子メールnhira@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・経営、関東東海北陸農業・関東東海・総合研究、共通基盤・経営
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
新たな米政策では担い手経営への転作地の利用集積が課題のひとつとなっている。その際、大規模経営は、転作作物の販売収益、転作受託(肩代わり転作)を行 うことによる委託料金(あるいは助成金の耕作者配分)の取得、転作作業の効率性や収量性等を総合的に勘案した上で、転作受託拡大の意思決定を行っているも のと考えられる。そこで、下妻市を対象に行った調査データに基づき、大規模経営が転作地集積に乗り出す動因を主に選択型コンジョイント分析を用いて定量的 に解明するとともに、その結果を用いて受託拡大需要がどの程度生じるかを推計する。
成果の内容・特徴
- 担い手農家の転作受託拡大行動の動因(表1)。
ア)担い手農家の受託拡大行動の大きな動因となっているのは、「耕作者が受け取る委託料金」であり、続いて「団地転作」である。
イ)麦・大豆価格や収量安定性は、上記の2要因とセットの場合には受託拡大行動の主要な動因とはならない。 - 受託拡大行動の発生確率(図1)。
ア)委託料金が低ければ団地かバラ転かが発生確率に決定的に大きな影響を与える。この場合、委託料金が0円でも、団地化が実現していれば、受託拡大行動の発生確率は80%程度になる(図1の1)。
イ)バラ転であれば、委託料金の水準が決定的に大きな影響を与える。この場合、耕作者への委託料金が2万円であれば バラ転であっても、受託拡大行動の発生確率は90%程度になる。しかし、この場合は担い手に対する誘導経費がかかること、バラ点では受託面積の量的拡大に 限界があることが問題となる。 - 受託拡大需要面積の推計(表2)。
上記結果に基づき、収量安定、麦・大豆価格8,000円、団地という条件下で推計した新たな受託拡大需要は、委託金が0円の場合で174haである。こ れにより、調査対象農家の所属する3地区の転作割当面積の約3分の2をカバーすることができる。また、委託料金を2万円に変えて推計すれば新たな受託拡大 需要は213haとなるが、これは、3地区の転作割当面積の約8割に相当する。
成果の活用面・留意点
- 団地化が困難な場合には、委託料金を積めばバラ転のままでも担い手への転作利用集積が進む可能性が示されたが、量(面積)を確保するには困難が伴うと予想される。
- 茨城県の利根川中流域における分析であるので、転作困難度の高い地域や米作依存の著しく高い地域等での本結果の単純適用は避けるべきである。
具体的データ
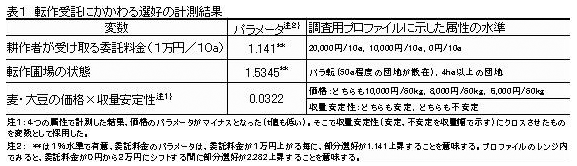
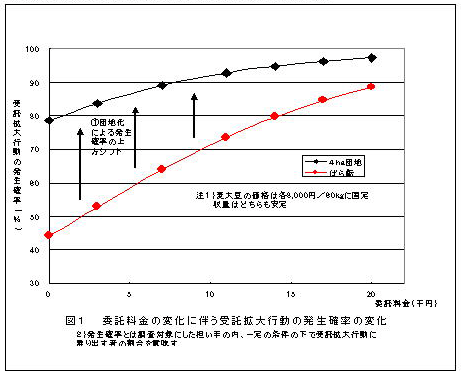
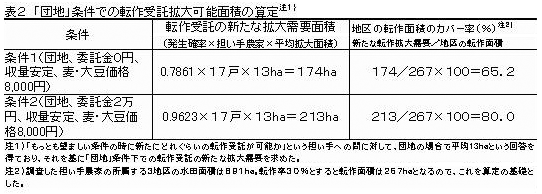
その他
- 研究課題名:大規模水田輪作営農確立のための農地利用システムの解明
- 課題ID:03-03-05-*-02-03
- 予算区分:地域総合
- 研究期間:2001~2003年度
- 研究担当者:平野信之、高橋明広
- 発表論文等:平野 (2003)「米関連対策に対する農家行動予測」日本農業経営学会個別報告
