消費者の安心を確保するために必要な青果物の情報伝達項目
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
青果物の生産者や流通業者の情報収集・管理は、川下の流通業者や消費者が必要としている情報からみると不十分であり、安全に関する情報項目は消費者に十分には伝達されていない。安心の確保という観点から、トレーサビリティシステムには、産地名、安全性等の認証、出荷日などの情報項目を盛り込む必要がある。
- キーワード:トレーサビリティシステム、情報ニーズ、生産履歴情報、流通履歴情報
- 担当:中央農研・経営計画部・マーケティング研究室
- 連絡先:電話029-838-8855、電子メールnarc-seika@naro.affrc.go.jp
- 区分:共通基盤・経営
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
トレーサビリティシステムの開発には、農産物流通における情報伝達の現状を把握した上で、各流通段階で必要な安全に関する情報項目の特定が重要になる。そこで本研究では、2004年6月に実施した農林水産情報交流ネットワーク事業全国アンケート調査「野菜の生産流通情報に関する意識・意向調査」を用いて、情報伝達の現状および各流通段階で必要な情報項目について分析した(同調査は、野菜の生産者602人、卸売業者53社、食品製造業者64社、外食業者182社、小売業者102社、20~69歳の女性の消費者911名が対象)。
成果の内容・特徴
- 80%以上の消費者が通常の購入時に必要と考えている情報項目は「産地名」、「安全性等の認証」、「出荷日」、60%以上は「品種名」、「栽培方法」、「農薬使用状況」、「販売業者名」、「収穫日」である(図1)。また、安全に関する不安・不満が発生した時は、「生産者の連絡先」、「温度履歴」、「栽培方法確認者名」、「生産者名」、「取引履歴」が、通常の購入時よりも10ポイント以上高くなっている。これらの情報項目は、小売業者が情報提供または保持しておく必要がある項目といえる。
- 消費者が購入時に必要と考えている情報項目の上位8項目をみると、販売時に提供できると回答した小売業者は平均で37%であり、情報ギャップは0.63である(図2)。同様に、小売業者と卸売業者の情報ギャップは0.50、食品製造業者、外食業者と卸売業者の情報ギャップは0.58、0.56である。一方、卸売業者と生産者の情報ギャップは0.37と最も小さくなっており、密接に情報交換が行われてきた結果を示していると考えられる。また、卸売業者段階、小売業者段階では、川上と川下で情報ギャップが大きくなっていることから、卸売市場や小売業者内部で情報の減衰が起きている可能性が高く、各流通主体内部の情報管理が重要であるといえる。
- 「安全性等の認証(認証マーク:安全性の代理指標)」、「出荷日(購入までの期間の把握:品質劣化の代理指標)」、「栽培方法(慣行栽培との違い:農薬等の使用量の代理指標)」等の消費者が必要であると考える安全に関する情報項目に対して、販売時に提供できると回答した小売業者業は半数未満になっている(表1)。同様に、小売業者や食品製造業者、外食業者が必要であると考えている安全に関する情報項目に対して、取引時に提供できると回答した卸売業者は少ない。また、安全に関する情報項目は生産者が発信しなければ伝達できないため、生産者はこれらの情報項目の情報収集と情報発信に取り組むとともに、卸売業者や小売業者は情報収集、伝達システムを構築する必要がある。
成果の活用面・留意点
- トレーサビリティシステム構築のための基礎資料となる。
- 消費者が必要な8項目を小売店舗の陳列棚に表示すると膨大なスペースが必要になるため、一部の情報を情報端末によって検索できるようにするなどの工夫が必要である。
具体的データ
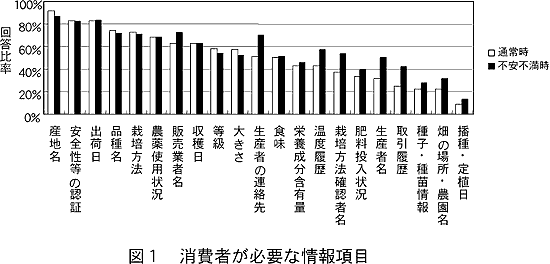
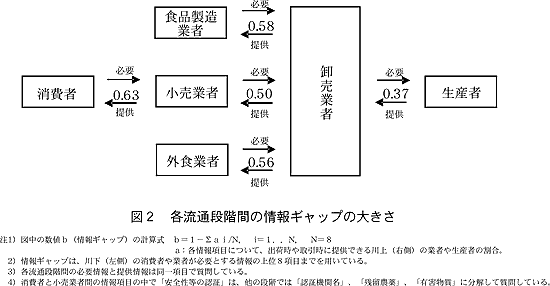
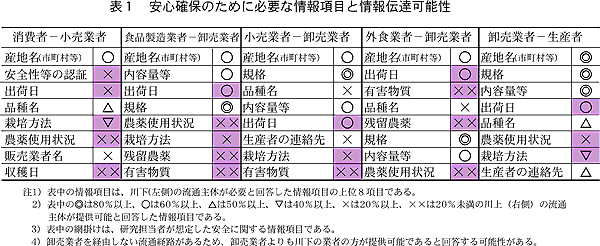
その他
- 研究課題名:流通履歴情報の体系化
- 課題ID:03-03-03-01-05-04
- 予算区分:高度化事業
- 研究期間:2003~2005年度
- 研究担当者:河野恵伸、大浦裕二、佐藤和憲(総研4チーム)、高橋克也(政策研)
