米を通年販売する稲作経営における米在庫管理の特徴
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
自社生産物のみ通年販売する稲作経営では、年度当初における所与の在庫量の下で、顧客に対する販売量を調整しながら在庫管理を行っている。他方、自社生産物に加えて仕入れ販売を行っている稲作経営では、販売状況に応じて仕入れできる体制の確立によって、顧客の需要に柔軟に対応し、かつ過不足を回避する在庫管理を可能としている。
- キーワード:マーケティング管理、在庫管理、稲作経営、米
- 担当:中央農研・北陸総合研究部・農業経営研究室
- 連絡先:電話025-526-3231、電子メールjsameft@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・経営、共通基盤・経営
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
米を通年で自力販売しようとする稲作経営は、商品在庫の過不足が生じないよう管理を行う必要があるが、在庫管理の実態や管理方法を分析した研究はほとんど行われていない。そこで、米の自力販売を行う稲作経営を、自社生産物のみ販売する経営とこれに外部から仕入れたものも加えて販売する経営の2つのタイプに大別し、両タイプの典型事例の分析を行うことによって、商品在庫管理の特徴を明らかにする。
成果の内容・特徴
- ここで取り上げるA社とB社のうち、前者は自社生産物のみ販売する先進事例、後者は自社生産物に外部から仕入れたものを加えて販売する先進事例として位置づけられる。両社の販売活動の概要は、表1に示すとおりである。
- A社における在庫管理の特徴は次のとおりである。
1)在庫量推移の実態:月によって販売量の変動が多少あるが、出来秋の9月から翌年8月にかけて毎月ほぼ一定量
ずつ減少している(図1、2)。
2)在庫過不足への対処方法:2000年産の品目a1の場合、12月と2月にやや多めの販売があったため、7~8月はほぼ
品切れ状態となった。このため、一部の顧客に対しては7月時点でやや過剰となった品目a2の購入を薦め、両品
目における在庫過不足の解消に努めている(品目a1、a2は「コシヒカリ」、a1はa2より上位品目)。また、A社では作業
効率や土地条件の面から各品目の生産面積を変更できないため、2001年産では、地主への地代の現物支給を在
庫不足の懸念される品目a1から品目a2に変更したり、金納にすることによって、年度当初に通年販売に割り当てる
在庫量を調整している(図1、2)。 - B社における在庫管理の特徴は次のとおりである。
1)在庫量推移の実態:月末在庫量の推移状況をみると、9月と翌年8月の数値を直線で結んだ水準に沿ってほぼ推移
している。すなわち、この水準を超過したり、割ったりすると、翌月にこの水準へ戻す動きがみられる(図3)。
2)在庫過不足への対処方法:在庫量の減少分を一定に保つのは、突発的な取引や販路開拓など様々な事態に対処
できるようにするためであるが、この水準は仕入量を調整することによって維持されている。特に4月以降は、保有
在庫量が少なくなる状況に対処し、仕入れへの依存度を上げ、過剰在庫が発生しないような方法が採られている。こ
のような在庫管理を可能にしているのは、販売状況に応じて仕入れできる体制及び食味計を用いた仕入品の厳しい
品質チェック体制を確立しているためである。
成果の活用面・留意点
- 本成果は、米の通年販売を拡大しようとする大規模稲作経営のマーケティング管理活動の参考になる。
- 外部からの仕入れを加えて販売する場合でも、収穫期のみに仕入れる場合は、その在庫管理方法はA社のように自社生産物のみ販売するものと同様になる。
具体的データ
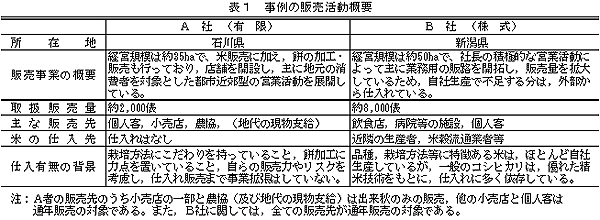
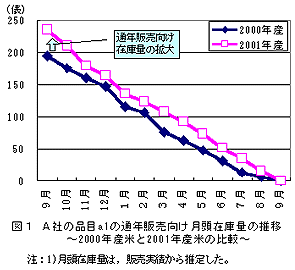 |
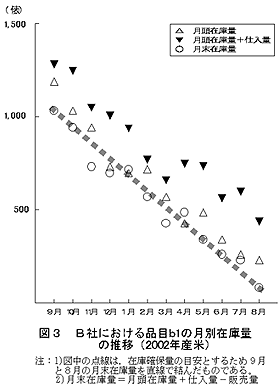 |
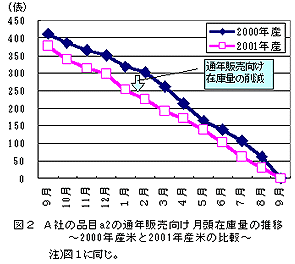 |
その他
- 研究課題名:稲作経営におけるマーケティング管理方式の解明
- 課題ID:03-02-03-01-04-04
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2002~2004年度
- 研究担当者:齋藤仁藏
