狭畦密植栽培によるナタネの自脱コンバイン収穫
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ナタネは狭畦密植栽培(条間30cm、株間5cm)することにより、莢が個体上部に集中するため、慣行法では困難であった自脱コンバインを用いた収穫が可能となる。この時、莢水分が50~60%で収穫することにより、頭部損失を10%以下に低減できる。
- キーワード:ナタネ、狭畦栽培、収穫、自脱コンバイン
- 担当:中央農研・作業技術研究部・農産エネルギー研究室
- 連絡先:電話029-838-8909、電子メールwataru@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・作業技術、共通基盤・作業技術
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
地域振興のための観光資源、バイオディーゼル燃料の原料あるいは環境保護活動のシンボルとしてナタネ栽培が見直されてきている。これらは休耕地の有効利用といった面を持つため、小規模分散圃場が多く、作業的にも経済的にも大型の普通コンバインの導入が困難となっており、現状では人力による収穫作業が中心となっている。そのため周辺に多く存在している自脱コンバインの利用が望まれている。そこで、自脱コンバインに改造を行うことなくナタネ収穫を可能にするための栽培技術を開発することで、ナタネ栽培の軽労化を図る。
成果の内容・特徴
- 慣行法のように条間が広いと個体間で分枝、特に最下分枝がからみつき、自脱コンバイン収穫においては引き上げ部で引っかかるため、収穫はほぼ不可能である。しかし、条間30cm、株間5cm程度の狭畦に点播することで、分枝が個体の上部に集中し、個体間での分枝のからみつきがなくなるため、自脱コンバインでの収穫が可能となる(表1、図1)。また、このような草型にすることで個体内での種子の熟度が均一化され収穫、調製、搾油および品質管理が容易となる(表1)。
- 狭畦栽培においては、施肥量を増加させることで慣行法とほぼ同等の収量が得られる。この時、施肥量、栽培法などによる含油量および脂肪酸含有率に大きな差は見られない(表2)。
- 莢水分50%以上で収穫することで、頭部損失を5~10%程度に低減させることが可能となる(図2)。ただし、莢水分が60%以上では、こぎ残しによる損失の増加および未熟粒の混入による品質低下が発生する。適期の目安として、莢が黄色く変色した頃から数日間とする。
- 自脱コンバインによる収穫時の作業速度はコンバインの機種、圃場状態に影響されるが、通常の1/4~3/4程度であり、莢水分が50%前後の場合、頭部損失に大きな影響は与えない。
成果の活用面・留意点
- 引き上げ部およびこぎ胴入り口で詰まらないように作業速度、刈取条数、刈取高さをコンバイン機種毎に適切に調整する必要がある。
具体的データ
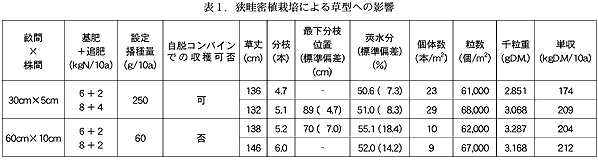
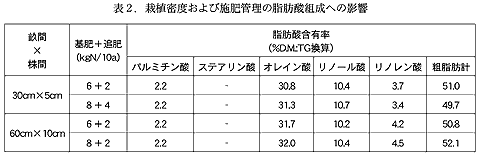
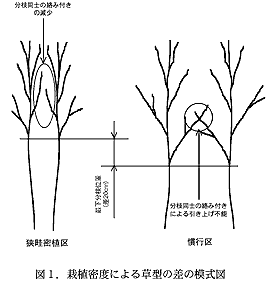
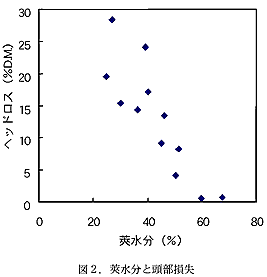
その他
- 研究課題名:油糧作物の機械化栽培・利用技術の開発
- 課題ID:03-10-04-01-01-04
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2001~2004年度
- 研究担当者:飯嶋 渡、小林有一、竹倉憲弘、加藤 仁、谷脇 憲
