JA有機栽培部会員が部会内新規参入者に与えるサポートの多重性
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
有機農業という共通の価値観で結びついたJA有機栽培部会の部会員は、新規参入者に対して、技術や販路面だけでなく、生活面や精神的なサポートなども与えている。また、参入者自身が次の参入者をサポートすることにより継続的支援が可能になる。
- キーワード:新規参入、有機農業、JA有機栽培部会、精神的サポート
- 担当:中央農研・経営計画部・地域営農研究室
- 連絡先:電話029-838-8852、電子メールjhara@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・経営、共通基盤・経営
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
非農家出身の農業への新規参入者には、有機農業を志向する者が少なくない。しかし、有機栽培技術の未確立による支援の困難や、従来の農業組織内に包摂されづらい経営形態などの要因により、就農相談センターや普及センターによる支援では十分対応できず、組織的な受け入れ体制の構築が遅れている。また、就農しても社会的に孤立する事例が指摘されてきた。従って、有機農業への新規参入者を多面的に支援する方策の提案が必要である。そこで、有機農業を志す新規参入者が多数定着しているY町を事例に、参入定着にあたってのサポートを誰から得ているのか、実態を明らかにする。
成果の内容・特徴
- Y町JAでは、生協との産消提携を契機として1997年に地元農家と新規参入農家とで組織された有機栽培部会が、有機農業新規参入者の受け入れ組織として位置付いている。JAが実施している就農研修(農場・農機具等の貸与、資金の貸与等)の修了生が部会員となる他、それ以外の新規参入者も部会員として受け入れている。
- 部会内の新規参入者にサポートを与える様々な主体の中で、有機栽培部会員は、中心的なサポートの与え手となっている。技術的な助言、販路についての助言だけでなく、地域社会慣習や子育てについての情報提供など生活上のサポートや、励ましや有機農業の価値の確認などの精神的なサポートの与え手としても、最も重要視されている(表1)。
- サポートの与え手ごとに新規参入者が受けたサポートの領域数の平均値をみると、有機栽培部会員が最も領域数が多い(多重的なサポート)。サポートの受け手の就農経緯別にみると、就農研修を受講して部会員となった場合(就農研修修了者)は、特に部会内で多重的なサポートを得ている。それ以外の新規参入者についても、部会設立後に参入した場合は、部会員から受けるサポートの多重性が高い(表2)。
- サポートの与え手側からの分析では、地元出身の部会員が最も多重的なサポートを与えているが、新規参入者についても、就農年数が短い場合でも重要なサポートの与え手となっている。これは、就農研修修了者がOB会として組織され後輩の支援役割を担うからである。このように、先行する新規参入者が新たな参入者をサポートする仕組みをとることで、支援システムの継続を支えている(表3・表4)。
成果の活用面・留意点
- すでに地域に定着している新規参入者を、新たな新規参入者受け入れ支援の担い手として活用する方策を探る上での参考となる。
具体的データ
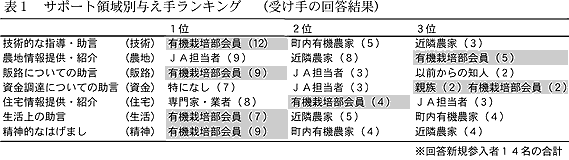
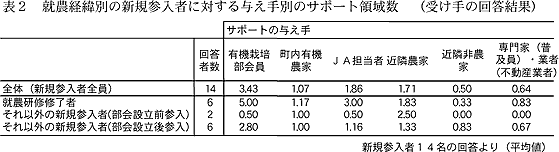
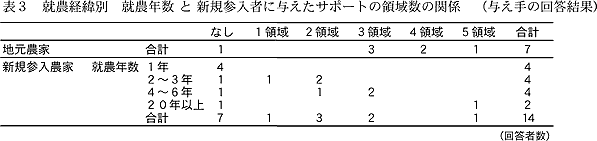
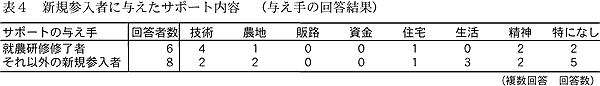
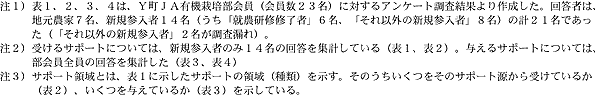
その他
- 研究課題名:新規参入者の参入形態に応じた地域社会関係形成のための支援方策の解明
- 課題ID:03-03-05-*-02-04
- 予算区分:(交付金)
- 研究期間:2002~2004年度
- 研究担当者:原 珠里
