飼料イネWCSを積極的に購入する酪農家の意向の特徴
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
飼料イネWCSの利用に積極的な酪農家は、助成金等の短期的視点だけでなく、長期的視点でのメリットや経営改善効果利用を期待している。それら効果を技術的側面から構築し、関係機関を通じて情報提供していくことが利用の拡大に向けて重要となる。
- キーワード:飼料イネ、酪農家、経営改善、意向
- 担当:中央農研・経営計画部・地域営農研究室
- 連絡先:電話0298-38-8852、電子メールnarc-seika@naro.affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・関東東海・総合研究、関東東海北陸農業・経営、共通基盤・総合研究、共通基盤・経営
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
飼料イネWCS(以下、飼料イネ)の利用を進めるには、どのような意向の農家が積極的に購入しているかを把握することが重要である。そこで、実際に飼料イネを利用した経験のある埼玉県の11戸の酪農家にアンケート調査を実施し、「飼料イネ栽培農家や圃場条件・生育情報獲得の有無」、「その情報の入手先」、「クレーム提示の有無」、「飼料イネを利用する契機」、「飼料イネ利用の開始理由」の整理を通じて、定着条件を分析する。
成果の内容・特徴
- 調査対象の酪農家は、飼料イネの購入実績から、「飼料イネの購入量を増加させている農家、及び、地域の取り組みを見聞きしつつ、数年経た後に新たに購入を開始したグループ(以下、増加グループ)」(5戸)と「購入数量が減少あるいは増加していないグループ(以下、減少グループ)」(6戸)に区分できる。前者は、平均購入数量が多く(表1)、また、飼料イネの品質に対する評価も相対的に高い(図1)。一方、成牛頭数規模と購入数量をみると、後者の減少グループでは、規模と購入数量に関係性はない(図2)。
- 増加・減少グループともに、半数以上の農家が、飼料イネを栽培する耕種農家や圃場を知っているが、「具体的な生育情報」は、増加グループで得ているものが多い。それら情報は普及センターや農協といった関係機関からである。飼料イネは、事前に生育情報(収量の予想、雑草の状況等)の提示が可能であり、それら情報を提示していることで、増加グループからのクレームはない(表1)。
- 飼料イネの利用開始の契機は、関係機関の勧めによるが、減少グループはそれを「助成金」をとするものが大半を占めている。一方、増加グループでは、助成金の利用は契機にはない(表2)。
- 「夏場の食欲が低下した際に利用できる有効なエサ」、「乳質・乳量が増加する」など、飼料イネの利用による耕種農家との長期的な連携関係の構築による波及効果や飼料イネの利用に伴う経営改善効果を期待しているものが多い。一方、減少グループの全農家で「給与実証等の助成金があり購入飼料より安価に入手できる」という、いわば短期的な効果・利益の獲得を主たる理由としている。
- 以上を考慮すると、酪農家の利用を図るには、関係機関による情報提供等が重要である。また、酪農家に対して、飼料イネ利用の誘因として、助成金といった短期的な視点でのみはなく、長期的な視点でのメリット(例:耕畜連携に伴うシナジー等)や経営改善効果を技術的側面から構築し具体的に提示していくことが重要である。
成果の活用面・留意点
- 酪農家への飼料イネ利用を図る上での参考となる。
- 埼玉県の11戸の酪農家の調査結果という限定がある。
- 増加グループの意向については、より詳細な追加的調査が必要である。
具体的データ
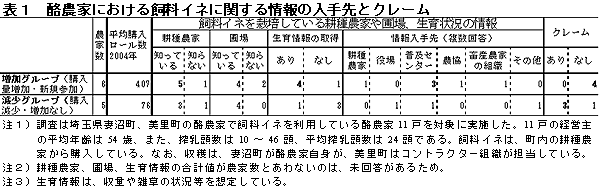
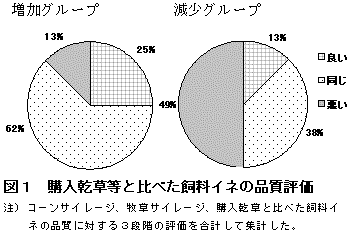
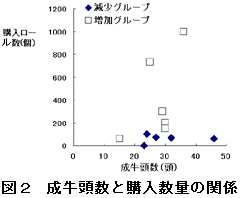
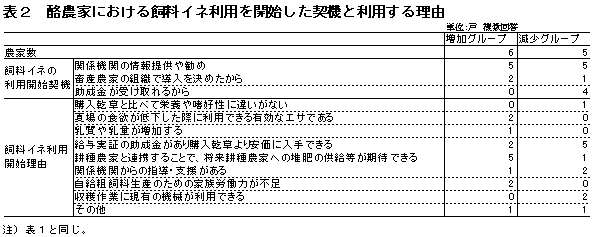
その他
- 研究課題名:飼料用イネ取引調整システムの確立
- 課題ID:03-03-05-*-03-03
- 予算区分:関東飼料イネ
- 研究期間:2004~2008年度(2004年)
- 研究担当者:高橋明広、平野信之、原 珠里
