アンローダ排出時間計測によるコンバイン収穫質量測定装置
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
コンバインのアンローダに設置した光電センサにより測定される穀粒の排出時間とGPSによる作業軌跡から、収穫質量・位置を自動記録する装置。収穫質量を5~10%程度の精度で推定する。市販コンバインに後付可能で、ほ場毎の収量データ収集に利用できる。
- キーワード:コンバイン、収量、GPS、GIS、ほ場管理
- 担当:中央農研・高度作業システム研究チーム
- 連絡先:電話029-838-8812、電子メールtatek@affrc.go.jp
- 区分:共通基盤・作業技術、関東東海北陸農業・作業技術
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
各農業経営者および団体が保有するほ場の規模、および筆数が拡大傾向にあり、効率的な管理を行うため、各ほ場の収量などの生産履歴を把握する必要がある。ライスセンタ等による荷受時計測ではほ場毎の収量把握が難しく、欧米で市販されている収量計測装置等ではコンバイン本体に改造が必要となる。そこで、既存のコンバインに容易に後付けすることができ、収穫質量および収穫位置を自動記録できる装置を開発する。
成果の内容・特徴
- 収穫された穀粒を外部に排出する機構(アンローダ)の排出速度は通常タンク下部に設置されたスクリューオーガの搬送量に依存する。排出時では、スクリューの回転速度および断面効率が一定であるため、穀粒のかさ密度がほぼ一定であれば搬送量は一定となる。そのため、排出時間より収穫した穀粒の質量を推定できる。
- 穀粒が近接(数cm)するとセンサ出力がONとなる拡散反射形の光電センサを2つ用いて排出時間を測定する。アンローダ出口の前方に設置されたセンサAにより排出状態を高精度に検出できる。アンローダ出口が詰まった場合に誤検出を防止するため、センサBを後方に設置し、ONの場合に測定時間をカウントしない(図1)。
- 収穫質量測定装置は光電センサおよび単独測位GPS情報をメモリーカードに1秒間隔で連続的に記録する(コンパクトフラッシュ、128MBの容量で約444時間分)。振動センサによる自動記録開始・終了機能を備え、内蔵バッテリで連続45時間以上稼働する。光電センサをアンローダカバー部へネジ止めし、アンローダ基部に本体をベルト固定するだけで装置を設置できるため、どのコンバインにも容易に外付けできる(図1)。
- 普通・自脱計4型式のコンバインによる水稲、小麦、大麦、大豆の収穫試験において、排出時間と収穫質量は比例関係にある(図2)。各収穫条件毎に総質量と総排出時間の比から平均排出速度を算出し、各排出時間との積から求めた推定質量と測定質量との誤差は5~10%程度である(表1)。
- メモリーカードに記録されたデータからコンバインの作業軌跡と排出位置・時間が得られる。排出前の作業軌跡とほ場の地番図等のGIS情報と組み合わせることで収穫面積が推定でき、ほ場毎の収量データ収集に用いることができる(図3)。
成果の活用面・留意点
- 大規模農家や受託農家において、収穫情報の測定手段、乾燥施設への情報提供手段、並びに広域ほ場管理の基礎データとして利用できる。
- 穀粒の種類、コンバイン機種毎に換算係数が異なるため、最低1回、荷受時等に質量計測を行い、排出速度を求めておく必要がある。
- 水分や品質によりかさ密度が大きく異なる場合、推定誤差が大きくなる。
- 複数ほ場を収穫して排出を行う場合は、収穫面積の比からほ場毎の質量を算出する。
具体的データ

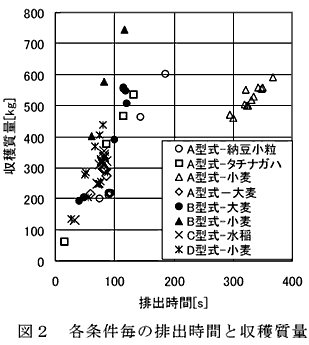
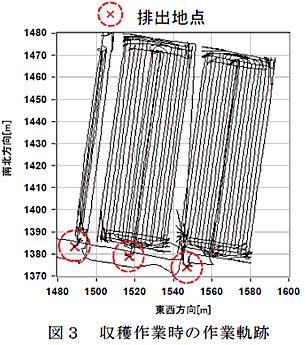
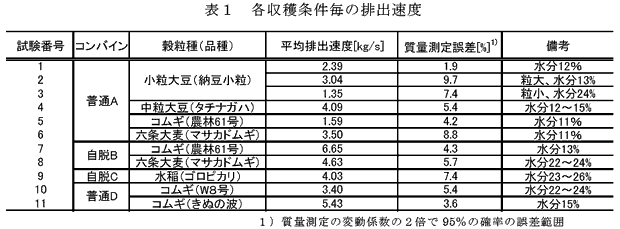
その他
- 研究課題名:農作業の高精度化・自動化等による高度生産システムの開発及び労働の質改善のための評価指標の策定
- 課題ID:223-a
- 予算区分:交付金プロ(精密畑作)
- 研究期間:2004~2006年度
- 研究担当者:建石邦夫、小林恭、宮崎昌宏、関正裕、長坂善禎、齋藤秀文
- 発表論文等:コンバインの収量計測装置、建石ら、特願2005-270018、2005.9
