北陸地域におけるイネWCS生産の低コスト化と導入促進条件
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
大規模水田作経営(経営耕地60ha程度)が専用収穫機(フレール型)1式を保有してイネWCS生産を行う場合、20ha前後の栽培が可能であり、10a当たり費用合計は6万円程度にまで低減できる。麦・大豆並の助成金が交付されるならば、麦・大豆単収の低い地域(県平均以下)でイネWCS生産の導入される可能性が高まる。
- キーワード:水田作経営、イネWCS、専用収穫機、コスト、所得、助成金、導入促進
- 担当:中央農研・北陸大規模水田作研究チーム
- 連絡先:電話025-526-3231、電子メールtomiko@affrc.go.jp
- 区分:関東東海北陸農業・経営、共通基盤・経営
- 分類:技術及び行政・参考
背景・ねらい
生産調整水田の有効活用や粗飼料自給率の向上を図るため、北陸地域においてもイネWCS生産の拡大が求められている。そこで、大規模水田作経営が専用収穫機を保有してイネWCSを低コスト生産する際に参考となる経営モデルを提示するとともに、導入を促進するための条件を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 大規模水田作経営(複数農家グループでも可)が飼料イネ専用収穫機1式を保有し、3割前後の転作率の下で一般水稲とイネWCSの低コスト生産を行うには、最低3名のオペレータと45~60ha程度の経営規模を確保し、8月中旬~下旬及び9月下旬~10月上旬に収穫するイネWCS生産を行う必要がある(表1)。その場合の飼料イネの10a当たり費用合計は図1の実線のようになり、5~15haまでは漸減し、20ha前後になるとほぼ一定値に近づく。 一方、表1の条件下で、過去10年間の気象データを用いて、降雨の有無による機械作業可能日を考慮した飼料イネの最大栽培可能面積を推計すると、平年の場合で20ha(多雨年では12ha、少雨年では25ha)となる(図1)。 これらのことから、飼料イネ専用収穫機1式を保有する大規模水田作経営では、20ha前後まで飼料イネを拡大でき、その場合の10a当たりコストも節減できる。
- 表1のモデル経営が18haのイネWCS生産を行った場合、10a当たり費用合計は6.4万円、全算入生産費は9.2万円となる(表2)。他方、10a当たり所得(助成無)は、乾物単収が1t/10a、販売価格が30円/kgの場合でも、2.2万円の赤字である。労働費や地代を確保するには10a当たり4~6万円の助成金が必要となる(図1、表2)。
- 飼料イネが導入されるには、同じ転作作物である麦・大豆並の収益性が確保される必要がある。麦・大豆と同等の助成金が得られる場合、20ha前後の作付規模で単収1tの飼料イネの10a当たり所得は、表1のモデル経営が新潟県市町村の麦・大豆最低単収を実現した場合の麦・大豆作所得に近い(図2)(この場合の1日当たり所得は飼料イネ2万円、大麦3.6万円、大豆2.1万円)。しかし、新潟県5ヶ年平均の大豆単収(176kg)の10a当たり所得に接近するには、1.7t以上の飼料イネ単収が必要である。 一方、飼料イネの場合、後作水稲にコシヒカリを選択できることから(麦・大豆後コシヒカリは倒伏の可能性大)、コシヒカリの作付けが増え、所得の向上(コシヒカリと他品種の10a当たり所得差×作付増加分)が期待できるため、これを加味すると、新潟県平均大豆単収の10a当たり所得に近い所得となる(図2)。 これらのことから、県平均以下の大豆単収しか実現できない地域で、飼料イネの導入が有利になる可能性がある。
成果の活用面・留意点
- 日本海側の水田地帯でイネWCS生産の導入・拡大を促進する際に参考となる。
具体的データ
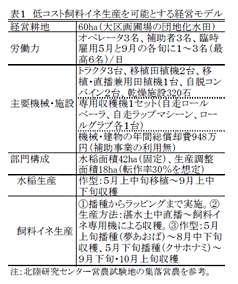
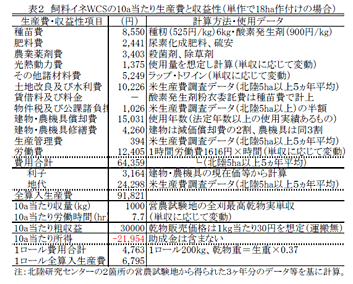
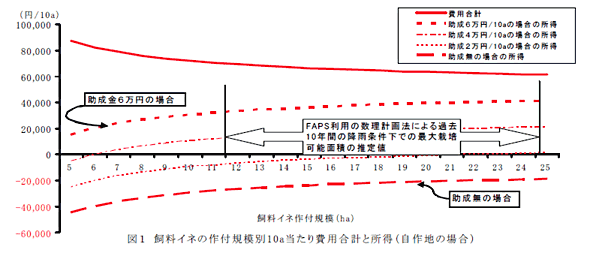
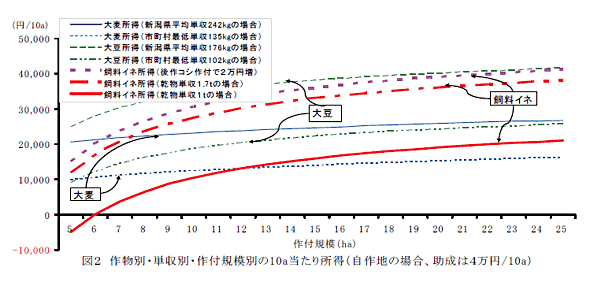
その他
- 研究課題名:北陸地域における大規模水田作の高精度管理技術と高品質飼料イネ生産技術の開発
- 課題ID:212-b
- 予算区分:基盤、北陸大麦飼料用稲輪作
- 研究期間:2003~2006年度
- 研究担当者:土田志郎
