麦収穫後の石灰窒素施用はカラスムギ、ネズミムギの出芽パターンを変える
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
麦類収穫後のほ場に石灰窒素肥料を表面施用するとカラスムギ、ネズミムギの出芽時期が前進・斉一化する。両草種の種子が地表面にある条件で施用すれば、出芽総数も減少させる。
- キーワード:カラスムギ、ネズミムギ、シードバンク、出芽挙動、石灰窒素
- 担当:中央農研・雑草バイオタイプ・総合防除研究チーム
- 連絡先:電話029-838-8426
- 区分:共通基盤・作付体系・雑草
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
麦作強害雑草カラスムギ、ネズミムギは既存の除草剤のみでは麦作中での防除が困難である。そのため近年、本州以南の固定転換畑の 麦作ほ場において特に両種の被害報告が増加している。石灰窒素肥料を活用したカラスムギ、ネズミムギの総合的防除体系を構築するため、石灰窒素肥料の施用 法と耕起方法の組合せがカラスムギ等の出芽挙動と種子動態に及ぼす影響を解明する。
成果の内容・特徴
- カラスムギの出芽時期には集団間に変異が存在し、土中種子の出芽時期は集団ごとに異なる(図1a)。出芽時期の早い集団(図1A)は越夏後の秋期に大半が出芽するが、出芽時期の遅い集団(図1D)は1年目冬期および2年目以降に断続的に出芽が続く。麦類収穫後、耕起してカラスムギ種子を土中に埋設した土壌に粒状石灰窒素(N20%)を施用(60kg/10a)すると、いずれの集団も出芽時期が早まる(図1b)。
- 地表面のカラスムギ種子に粒状石灰窒素(N20%)を施用(60kg/10a)すると、出芽促進、出芽総数および未発芽生残種子の減少といった効果があるが、その程度はカラスムギの集団ごとに異なる(図2)。出芽の早い集団は出芽総数が減少する(図2集団A:3→4)。中間的な集団に対しては、防除上問題となる土壌処理型除草剤の効果消失後(12/9以降)の出芽数は土中種子(耕起)より地表面種子(不耕起)で減少し(図2集団B:1→3)、石灰窒素の施用でさらに減少する(図2集団B:3→4)。出芽の遅い集団に対しては麦播種期以前(11/14まで)の出芽を促進し、未発芽生残種子数も減少する(図2集団D:3→4)。
- 4種の異なる土壌においても、石灰窒素肥料の施用による出芽促進効果によってカラスムギ土中種子(耕起)の冬期の出芽総数が減少し、地表面種子(不耕起)に対しては出芽総数および生残種子数が減少する。(図3)
- ネズミムギに対しても石灰窒素肥料の施用によって冬期の出芽数が減少し、施用量の増加とともに出芽総数が減少する(図4)。地表面の種子に施用した場合(11月耕起)、冬期の出芽は著しく減少し,出芽の早いカラスムギ集団(図2A)と同様の反応を示す。
成果の活用面・留意点
- 石灰窒素を基肥施用する麦跡不耕起大豆栽培などカラスムギ、ネズミムギの総合的防除体系の一要素となる。その場合、窒素肥料としての施用量・利用率も勘案する必要がある。農薬登録における石灰窒素の畑地一年生雑草への施用量は50~70kg/10aである。
- 実測した出芽率およびシードバンクの残存率はカラスムギ、ネズミムギの個体群動態のパラメータとして活用できる。
- 石灰窒素施用量の増加によるカラスムギ,ネズミムギの出芽総数の減少には種子の死滅効果が関与すると考えられる。
- 埋土されたカラスムギ種子に対して石灰窒素を施用した場合、出芽の遅い集団では麦類播種期以降~冬期の出芽総数が増加する(図1D)。この場合、当年麦作中のカラスムギ密度抑制には逆効果となる。
具体的データ
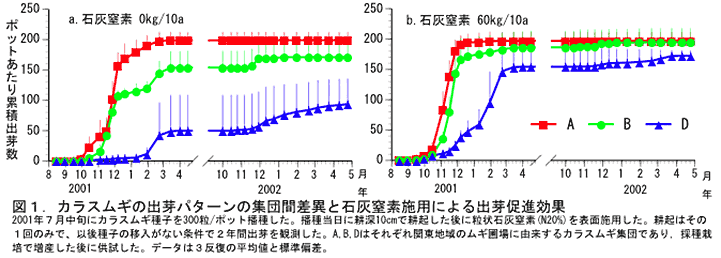
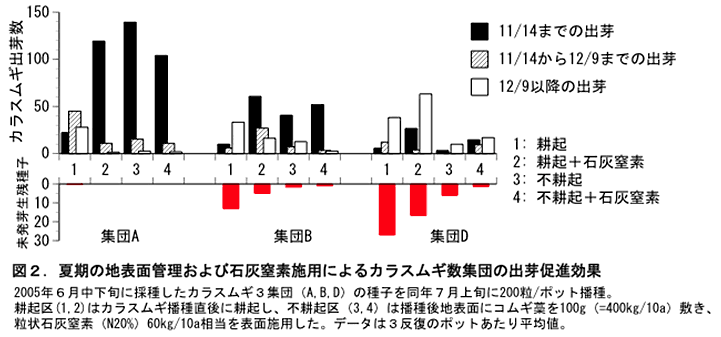
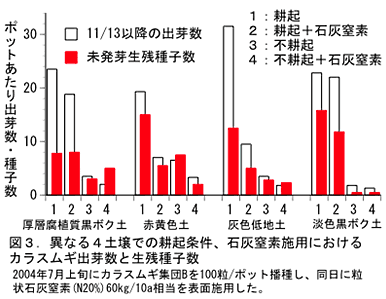
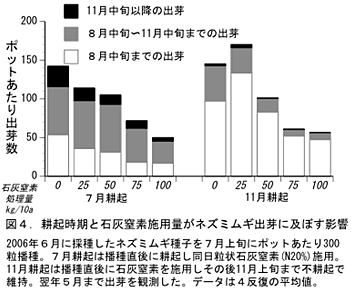
その他
- 研究課題名:難防除雑草バイオタイプのまん延機構の解明及び総合防除技術の開発
- 課題ID:214-b
- 予算区分:21世紀1系(2001~2002)、ブラニチ1系(2003~2005)、基盤研究(2006)、IWM(2007)
- 研究期間:2001~2007年度
- 研究担当者:浅井元朗、渡邊寛明、澁谷知子、與語靖洋(農環研)
- 発表論文等:浅井元朗(2007)麦畑に侵入するカラスムギ?出芽の不斉一性という生き残り戦略.種生物学研究30:71-93
