深水栽培による白未熟粒抑制技術
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
分げつ盛期から最高分げつ期の深水栽培は、有効茎歩合の増加と、シンクに対する出穂前の蓄積炭水化物の増加などによる登熟期のソース能力の向上によって、慣行と同等の収量を確保しつつ、白未熟粒割合を減少させる。この効果は、高温登熟耐性が弱い品種で、特に顕著である。
- キーワード:イネ、深水栽培、白未熟粒
- 担当:中央農研・稲収量性研究北陸サブチーム
- 連絡先:電話025-526-3241
- 区分:関東東海北陸農業・北陸・水田作畑作物、作物
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
近年の気候温暖化により、登熟期の気温が高まり、米粒外観品質の低下が問題になっている。この一因として、良食味米生産のための 窒素施肥量削減による地力の低下が、登熟期の稲体の活力低下を招き、品質低下を助長していることが指摘されている。そこで、草型の改変と窒素の有効利用が 期待できる栽培技術として、深水栽培による白未熟粒発生抑制の効果を検討する。
成果の内容・特徴
- 分げつ盛期から最高分げつ期にあたる6月中旬から7月上旬の20日間、水深約18cmで深水処理すると、高位の1次分げつと 2次分げつの発生が抑制され、穂数が減少するが、一穂籾数が増加して穂重型の生育を示し、有効茎歩合が高まるため、深水栽培でも慣行栽培と同等の収量が得 られる(表1、図1、表2)。
- 高温処理(オープントップチャンバー法 昼温0.5℃上昇)の有無にかかわらず、深水栽培によって白未熟粒割合は減少する(図2)。特に高温登熟耐性の弱い品種(初星、ササニシキ)で効果が大きい(図2)。
- 深水栽培では、籾数当たりの穂揃い期茎部非構造性炭水化物(NSC)量が増加する(表2)。また、穂揃い期の籾数当たりの葉身窒素量が高く、登熟期間を通じて葉面積が大きく保たれる(表2)。これらより深水栽培での白未熟粒の減少は、シンクに対する出穂前蓄積炭水化物と登熟期光合成量の増加による、ソース能力の向上に起因すると考えられる。
成果の活用面・留意点
- 深水栽培の適用は、深水管理ができる畦のある水田に限られる。また、深水栽培では中干し期間が慣行栽培より短くなるため、排水が良好な水田への適用が望ましい。
- 初期生育が不良で、茎数が少ない場合は、減収の可能性があるので、水深の減少や処理開始時期を遅らせる等の調整が必要である。
具体的データ
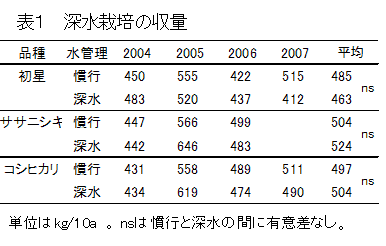
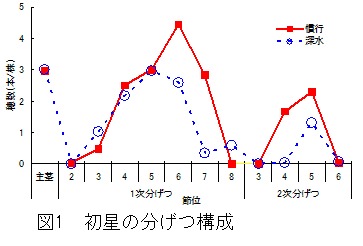
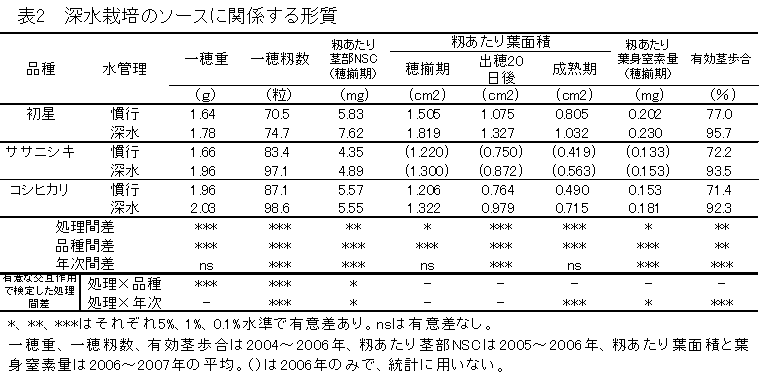
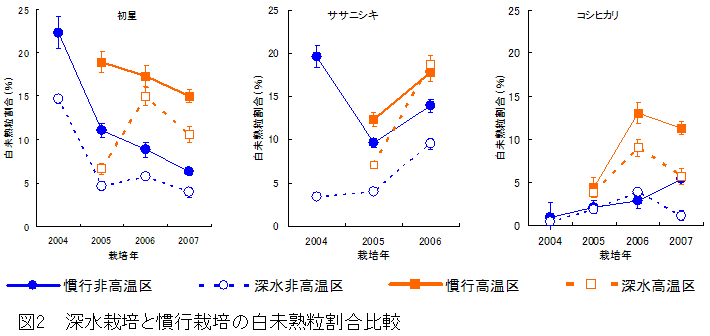
その他
- 研究課題名:イネゲノム解析に基づく収量形成生理の解明と育種素材の開発
- 課題ID:221-c
- 予算区分:気候温暖化
- 研究期間:2004~2007年度
- 研究担当者:千葉雅大、松村 修、寺尾富夫
