大豆の青立ち発生には成熟期の根系吸水力の維持が関係する
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
高茎水分による大豆の青立ち現象は、各種ストレスによる莢実減少などにより、登熟後半に根系へ光合成産物がより多く分配されて根系の吸水力が維持されることが関係している。
- キーワード:大豆、青立ち、茎水分含有率、茎窒素含有率、根系、吸水力
- 担当:中央農研・大豆生産安定研究チーム
- 連絡先:電話029-838-8532
- 区分:作物、関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
わが国では気候温暖化に伴い気象の変動が著しくなってきており、大豆では莢が成熟しても茎葉が青いままの「青立ち」現象等が多発 し、コンバイン収穫の困難化や品質低下、減収を招いており、青立ち発生機構の解明が求められている。コンバイン収穫時の青立ち株の問題は茎の高水分による 汚粒発生であることから、成熟期の茎水分の保持に着目した青立ち発生の生理的機構を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 北海道~九州地域の8主要品種を3播種時期で栽培した圃場実験では、青立ち程度は無~甚に広く分布し、茎の図1)。コンバイン収穫適期の目安となる成熟期茎水分が約50%以下では、茎の窒素含有率は1%以下、青立ちが「少」以下である。
- 子実肥大期には大豆の光合成産物の4割程度は莢実に分配され、根系への分配は少ない。しかし、摘莢処理により光合成産物の受容先(シンク)である莢実を減らすと光合成産物は根系や茎により多く配分される(表1)。
- 主茎の伸育型と青立ち発生程度は密接な関係にあることが知られている。有限伸育型品種(エンレイ)では、摘莢処理を行うと根 乾物重が増大して青立ちが著しくなるが、無限伸育型品種(Williams)は摘莢処理を行っても茎乾物重が増大するので根乾物重は増大せず、青立ちも促 進されない(図2)。黄葉期の根重が大きいと根系の吸水力の指標となる真空吸引下の出液速度が高く、成熟期の青立ち程度も著しくなる。
- これらのことから、光合成産物のシンクである莢実の減少が登熟後半における根系への光合成産物分配を増大させて成熟に伴う根系の吸水力低下を抑制した結果、成熟期の高茎水分を引き起こしていると推定される。
成果の活用面・留意点
- 青立ち発生を抑制する栽培技術、品種改良の参考になる。
具体的データ
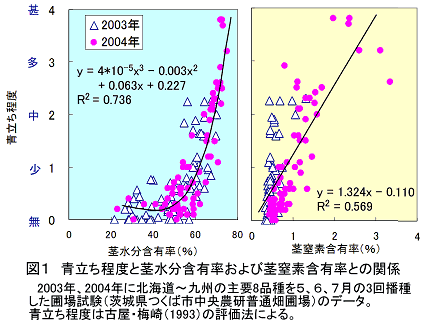
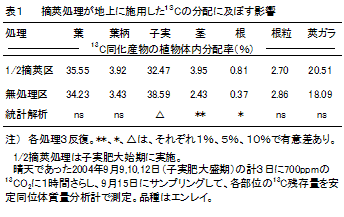
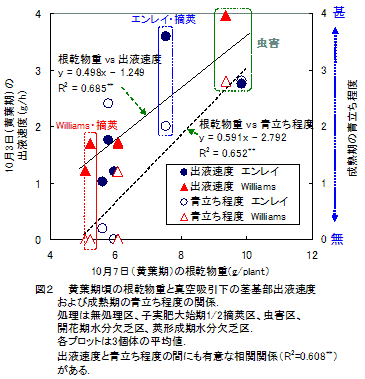
その他
- 研究課題名:気候温暖化で多発する大豆青立ちの発生要因の解明と品種抵抗性の解析
- 課題ID:211-c
- 予算区分:交付金プロ(気候温暖化)
- 研究期間:2003~2007年度
- 研究担当者:島田信二、大矢徹治(緑資源機構)、高橋幹、中村卓司、中山則和、山本亮、島村聡、金榮厚、服部誠(新潟農総研)、春口真一(熊本農研セ)、神崎正明(宮城古川農試)
