経済性と環境影響の可視化で判断する特別栽培の可能性
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
慣行栽培から特別栽培への変化の過程を対象に、経済性と環境影響を水稲作における農薬散布の事例について可視化すると、単収と環境影響はトレードオフの関係にあっても、粗収益と環境影響には双方を改善できる方向が示され得る。
- キーワード:特別栽培、慣行栽培、収量、粗収益、環境影響、農薬
- 担当:中央農研・環境影響評価研究チーム
- 連絡先:電話029-838-8874
- 区分:共通基盤・経営
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
環境保全型農業の一つの方向として、化学合成された農薬および肥料の使用を低減させることを基本とする特別栽培があり、認証シス テムの導入とともに各地で実施されている。しかし、たとえば農薬散布量の減少が、どの程度の環境負荷の低減につながり、単収や収益性にどのような影響をあ たえるかについては十分なデータと評価結果が得られていない。そこで、水稲作を事例として経済性と環境影響の評価を統合的に行うことによって、それらの関 係を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 農家単位のデータ(A県における8戸の水稲農家、2004年)を用いて、慣行栽培と特別栽培を比較し、転換過程における変化の傾向を明らかにした成果である。単位面積当たりの収量および粗収益と、環境影響(農薬の人間健康への影響)との関係を説明している。
- 農家ごとに慣行栽培から特別栽培への変化の方向をみると、単位面積当たりの収量と環境影響との関係については左下を向いており、単位面積当たりの収量と環境影響との関係については右下を向いている場合がほとんどである(図1)。
- 全体としての変化を、生産フロンティア(経済性が高く、環境影響が小さい効率的な農家の軌跡)によって検討すると、収量を経済性の指標とした場合にはフロンティアが左下に移動し、粗収益を指標とした場合には右下に移動している(図2)。
- 収量と環境影響の関係はウィン・ルーズ(トレードオフ)の関係にあるが、粗収益と環境影響の関係はウィン・ウィンの関係にある。後者の関係が実現できる場合であれば、特別栽培への取り組みが推奨される。
成果の活用面・留意点
- 特別栽培の推進を検討する際の基礎資料となる。
- あらゆる特別栽培が収益面で優れていることを示すものではない。
- DALY(障害調整生命年)はWHOと世銀が開発した総合的指標(苦痛や障害を考慮した寿命)であり、小さいほど望ましい。その計算には D. Pennington氏(Joint Research Centre, EU)より提供されたプログラム(マルチメディアモデル)等を利用している。
具体的データ
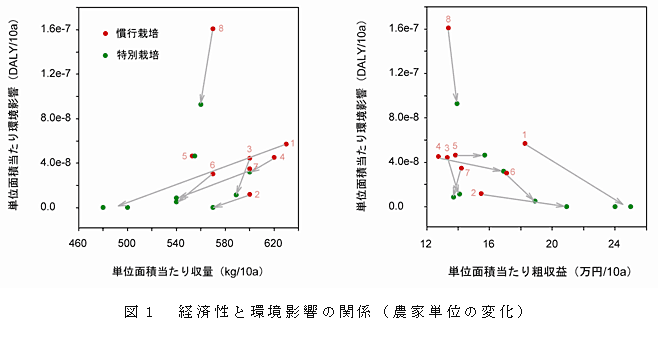
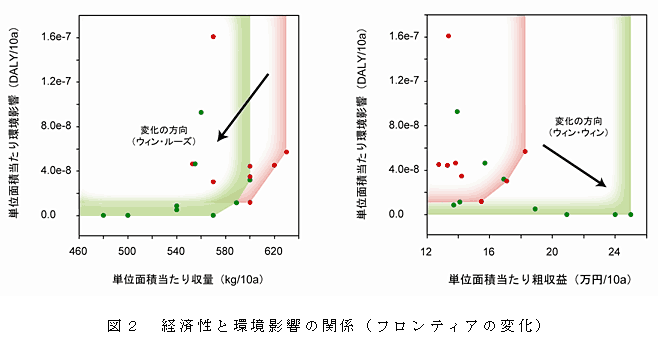
その他
- 研究課題名:環境影響の統合化と環境会計による農業生産活動評価手法の開発
- 課題ID:214-a
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2006~2007年度
- 研究担当者:林清忠、小野洋、中島隆博
