ダイズの石豆を解消する研磨機
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ダイズの選別工場等で利用されている研磨機の、研磨網突起形状を改良し、研磨部を通過したダイズの種皮表面に10μm程度の凹みをつけることによって、石豆(硬実)ダイズを吸水可能にする装置である。ダイズ組織への損傷は従来の研磨機処理と同程度である。
- キーワード:ダイズ、石豆、硬実、吸水
- 担当:中央農研・土壌作物分析診断手法高度化研究チーム
- 代表連絡先:電話029-838-8814
- 区分:作物、関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
ダイズの石豆は、品質指標上、裂皮粒やしわ粒と同じ障害粒に分類され、品種特性や栽培時のストレス等が原因で発生すると言われている。石豆の問題点は、水に浸漬しても吸水せず、吸水前の外観(目視)検査でも正常粒と区別できない点である。そのためダイズ加工においては、吸水工程で十分に吸水せず、小石のように硬いままなので製品の品質を落とす(納豆、煮豆など形が残る製品の場合)、磨砕工程で機械にダメージを与える、等の問題が発生している。石豆は吸水工程を経ないと確認できず、他の障害粒のように原料段階での選別除去は困難であるため、従来は剥皮や吸水後の工程での粒大選別が行われてきた。そこで、石豆の種皮表面に微細な凹みをつけて吸水可能なダイズに変換すると同時に、ダイズ組織への損傷を極力少なくして全量処理可能とする装置を開発する。
成果の内容・特徴
- 正常に吸水するダイズの種皮表面には、吸水に寄与する深さ10μm程度の小さな凹みが多数あるのに対して、石豆の表面はこの凹みが極めて少ないという特徴を持つ。標記研磨機は、研磨網の突起形状を大きくした網を取り付けることにより、石豆の種皮表面に深さ10μm程度の凹みを多数形成して、吸水性を回復させる装置である(図1、図2)。
- 上記の改造を施したA社製研磨機により、抜き取り検査で石豆混入が判明したロットを全量処理して、石豆混入のない加工用ダイズが得られる。ダイズ組織への損傷指標(浸漬水の電導度と溶出固形分量)では、従来型研磨網処理と改良型研磨網処理との間で有意な差はみられない(表1)。
- ダイズ卸商社の選別工場にある研磨機(最大処理能力;5000kg/h)により実機テストを行い、石豆混入が確認された小粒ダイズ900kgの処理では、処理後に石豆が検出されなくなることを確認している(表2)。
成果の活用面・留意点
- 石豆処理用の研磨機はA社が製造販売し、既存研磨機に対する改造にも対応する。
- 吸水・蒸煮工程を経た石豆は全て廃棄物となっていたが、当該装置の使用により、廃棄物の低減を図ることができる。
- 破砕粒の発生が従来の研磨処理よりも増える傾向があるため、過乾燥(水分10%未満)ダイズの処理は避ける。
- 本研磨機の適用は納豆原料用ダイズを対象とする。
具体的データ
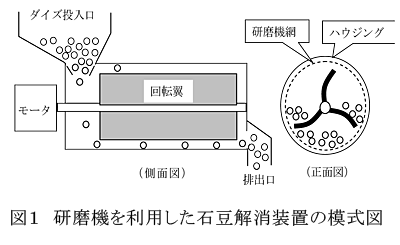
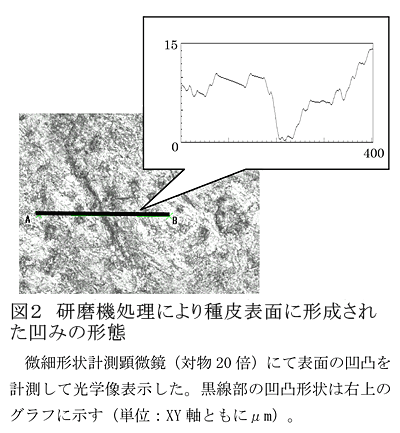
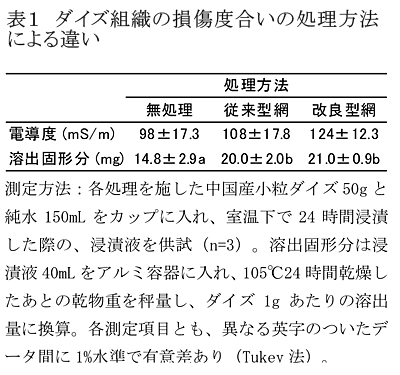
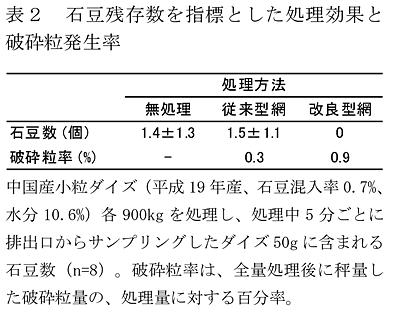
その他
- 研究課題名:ナノテクノロジーを利用した物生理計測・制御技術の開発
- 課題ID:521-a
- 予算区分:基盤
- 研究期間:2006~2008年度
- 研究担当者:乙部和紀、吉岡邦明(筑波大)、原田直輝(原田産業(株))、片寄都弘(三倉産業(株))
- 発表論文等:1)乙部「種子の吸水促進処理方法及び処理装置」特開2008-154464
