タンパク質の高次構造形成を触媒するプロテインジスルフィドイソメラーゼ
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ジスルフィド結合は、天然の状態でタンパク質に存在する唯一の共有結合であり、正しく架橋されることが高次構造形成と機能発現に必須である。この正しいSS結合の形成を触媒する酵素、プロテインジスルフィドイソメラーゼを高等植物(大豆)から初めて単離し、その構造と作用機構を解明した。
- 担当:食品総合研究所・食品理化学部・蛋白質研究室
- 代表連絡先:0298-38-8051
- 部会名:食品
- 専門:バイテク
- 対象:蛋白質一般
- 分類:研究
背景
細胞内では、タンパク質の生合成後、秒あるいは分単位で本来の高次構造形成が達成されるがその詳細な機構ついては明らかではない。また、遺伝子組み換えで生産されたタンパク質は本来のジスルフィド結合が形成できず不活性型になる場合が多い。 Protein Disulfide Isomerase (PDI)はジスルフィド結合を正しく掛け換えることでタンパク質の高次構造形成と機能の発現を促進させると推定されるが詳細は不明である。本研究では、主要作物である大豆から同酵素を単離して、その機能の解明を試みた。
成果の内容・特徴
- 大豆より精製されたPDIは活性中心部位において、他の生物のPDIと高い相同性を示し、その活性発現には、還元型のSH基が必要であり、酸化還元平衡は還元型に偏っているほうが望ましいことがわかった。
- 還元変性トリプシンインヒビターのトリプシン阻害活性は、180分間でPDI非存在下で10%、存在下でほぼ100%回復した。しかし、キモトリプシン阻害活性はPDI非存在下でほぼ0%、存在下で30%程度しか回復しなかった。この差は両活性ドメインの立体構造の再生の違いに起因するものと考えられる。
- 還元変性オボアルブミンの高次構造の再生過程をCDスペクトルで追跡したところ、PDIの構造再生に対する効果は、再生過程後期(20時間以降)に現れることがわかった(図1)。
- 種々の穀実種子中のPDI活性を測定した結果、種子のPDI活性とタンパク質含量には高い正の相関が認められた(図2)。
成果の活用面・留意点
- 米の食味がタンパク質含量と負の相関を持つことから、低いPDI活性を指標に低タンパク質の良食味米の育種と選抜が可能になると期待される。
- 穀物アレルゲンの抗原性発現にジスルフィド結合による高次構造形成が大きく寄与していることから、PDI活性を低減化した低アレルゲン穀物の作出が考えられる。
具体的データ
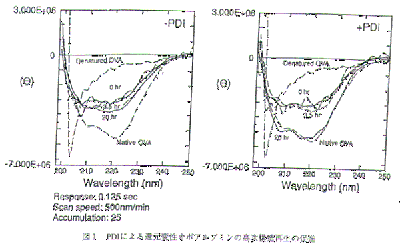
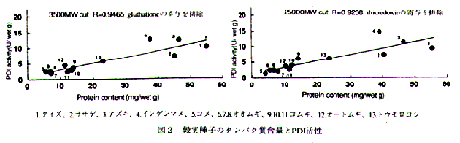
その他
- 研究課題名:蛋白質の高次構造形成と機能の解明
- 予算区分:フロンティア
- 研究期間:平成10年度(平成8~10年)
- 研究担当者:大倉哲也・河村幸雄
- 発表論文等:1)Kainuma, k., Ookura, T., Okamoto, A., Kitta, K., Manabe, M. and Kawamura, Y., Biosci. Biotech. Biochem. 62 369-371 (1998).
2)Samoto, M., Miyazaki, C., Kanamori, J., Akasaka, T. and Kawamura, Y., Biosci. Biotech. Biochem. 62(5), 935-940(1998).
3)Kawamura, Y., Ookura, T. and Kainuma, K., Protein Disulfide Isomerase from Soybean-Isolation, Structure and Function in Protein Folding,in 'Proline hydroxylase, Protein Disulfide Isomerase and Related Protein in Protein Folding'N.A.Guzsman ed. MercelDekkar, Washington D.C., 149-171(1997).
4)Ookura, T., Kainuma, K., Kim, H-J., Otaka, A., Fuji, N. and Kawamura, Y., Biochem. Biophys. Res. Commun. 213(3) 746-751(1995).
5)Kainuma, K., ookura, T. and Kawamura, Y., J. Biochem. 117 208-215(1995).
