ネオスポーラのELISAによる抗体検出法の開発
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
簡便で非特異反応のほとんど認められず蛍光抗体法との結果の一致率が高くすべての哺乳類のネオスポーラ感染を検査できるELISAを開発した。
- キーワード:ネオスポーラ,ELISA,死流産
- 担当:動衛研・免疫研究部・免疫病理研究室
- 連絡先:0298-38-7833
- 区分:動物衛生
- 分類:行政・普及
背景・ねらい
ネオスポーラ(Neospora caninum;以下N.c.)は1988年に確認された新種の原虫で,多くの哺乳動物で感染が確認されている。ウシにおける感染は死流産を引き起こす。ウシでは胎盤感染するため ,感染母牛の摘発は,感染を防御する手段として重要である。本疾病の血清診断法の標準法となっている間接蛍光抗体法(IFA)に代わる「簡便・高感度・短時間で検体を多数処理することのできるELISA」の開発が望まれている。現在までに ,報告されているN.c.のELISAは『陰性血清が擬陽性を示す例が多く陽性反応と明瞭に区別することができず,カットオフ値を設定することは困難である』,『IFAとELISAの結果の一致性が悪い』 ,『特異性が高いELISAでは操作が煩雑になる』等の問題点があった。簡便で非特異反応がほとんど認められず,蛍光抗体法との一致率の高いN.c.のELISAの開発が望まれている。
成果の内容・特徴
- ELISAは以下の通りである:培養N.c. JPA1株タキゾイトの精製抗原をTriton x-100で可溶化後,プレ-トに固定後,ニワトリ血清とブロッキング剤でブロッキングし ,希釈した検査血清を反応後,POD標識r-protein AG (PAG, Prozyme) を反応させ,ABTS発色液を分注し発色させ,5% SDS溶液で反応を停止後 ,吸光度を求めた。
- 陰性血清での有意な吸光度の低下が認められ (p<0.01) ,陽性血清ではOD値が上昇する傾向が認められた(図1)。この結果 ,陰性陽性が明瞭に区別された。
- ウシ野外例によりカットオフ値は0.36 ELISA 値で蛍光抗体価との陽性・陰性の判定結果と有意に一致していた (κ=0.885) (図2)。
- 蛍光抗体価とELISA値は正によく相関していた (correlation coefficient =0.866, index of linearity =0.979)。 (図3)
- ネオスポーラ関連の原虫に対する交叉反応はほとんど認められなかった(表1)。
成果の活用面・留意点
- 信頼性と実用性が高いN.c.のELISAが開発された。
- 本法を用いることにより,哺乳類のネオスポーラ感染を調査することが可能である。
具体的データ
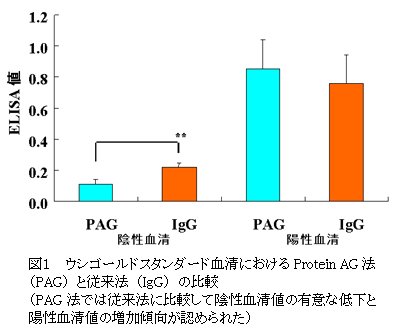
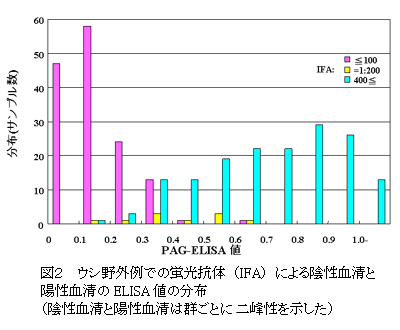
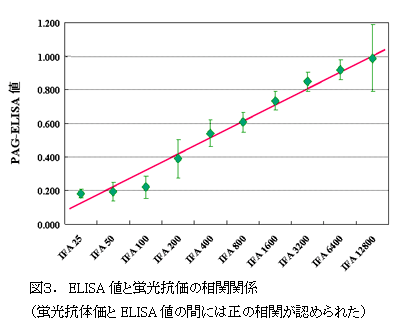
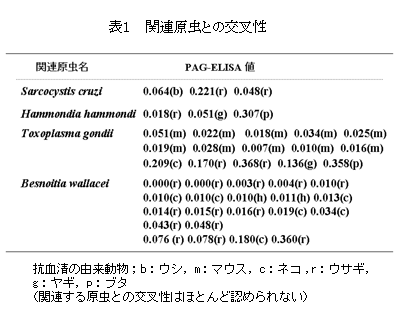
その他
- 研究課題名:ネオスポラの感染経路の解明
- 予算区分:交付金プロ(所内プロ)
- 研究期間:1999~2000年度
- 研究担当者:清水眞也,山根逸郎,國保健浩,衛藤真理子,志村亀夫,播谷 亮,濱岡隆文,猪島康雄,芝原友幸,小岩井正博
- 発表論文等:清水ら 特許第3016021号 『ネオスポーラ感染判別方法』
