抗原シフトが認められたチュウザンウイルスの発見と解析
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
これまで日本で分離されたチュウザンウイルスの詳細な遺伝学的・血清学的な解析を行ったところ、第2分節遺伝子が別種のD'Aguilarウイルスのものに入れ変わったウイルス(遺伝子再集合体)を見つけ、自然界におけるはじめての発見となった。
- キーワード:アルボウイルス、チュウザン病、ウシ、遺伝子再集合
- 担当:動物衛生研・九州支所・臨床ウイルス研究室
- 連絡先:電話099-268-2078、電子メールでの問い合わせはこちらから。
- 区分:動物衛生
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
チュウザンウイルス(CHUV)は1985年に日本ではじめて分離されたアルボウイルスの一種で、血清学的に相互に反応する近縁なグループ(パリアム血清群)にD'Aguilarウイルス(DAGV)やNyabiraウイルス等がある。10分節あるウイルス遺伝子の中で、中和反応に関わっている抗原は第2分節にコードされ、同じ血清群であっても種間の遺伝子の相同性はあまり高くない。一方、血清群共通抗原をコードする第7分節は同一血清群内でよく保存されている。
2001年から翌年春にかけて九州で盲目や大脳、小脳の一部が欠損する新生子牛の分娩が多くみられ(いわゆるチュウザン病)、分娩した母牛のCHUVに対する中和抗体を調べたところ、抗体は検出されたものの非常に低かったため、パリアム血清群の別種のウイルスが原因と考えられた。そこで、2001年に日本で分離した株を含めCHUV9株とオーストラリアおよびアフリカで分離されたパリアム血清群ウイルスとの詳細な血清学的および遺伝学的解析を行った。
成果の内容・特徴
- 第7分節の相同性解析および分子系統樹解析により、CHUV9株すべてが遺伝学的に単一であることを確認した。
- CHUV9株のうち、2001年に分離されたKSB-29/E/01株は、抗CHUV血清だけでなく、抗DAGV血清でも中和され、むしろ、DAGVに高く反応した(表1)。
- 第2分節の相同性解析および分子系統樹解析により、CHUV9株のうち、2001年に分離されたKSB-29/E/01株や1987年に分離されたKY-115株を含め5株がDAGV B8112株(オーストラリア分離株)やNyabiraウイルス792/73株(アフリカ分離株)に極めて類似していることが明らかとなった(表2および図)。
- 以上のことから、自然界においてCHUVとDAGV間での遺伝子再集合が起きていたことが証明され、2001年には遺伝子再集合ウイルスによるチュウザン病の発生が確認された。
成果の活用面・留意点
- 自然界に遺伝子再集合ウイルスが存在していることが明らかとなったことから、より的確で効果的なアルボウイルスの流行予測が可能となる。
- 今後とも国内における流行状況の監視を強化するとともに、これまで分離されたウイルスについて遺伝子再集合の観点からの再評価・再同定が必要となる。
具体的データ
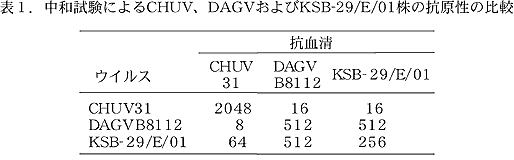
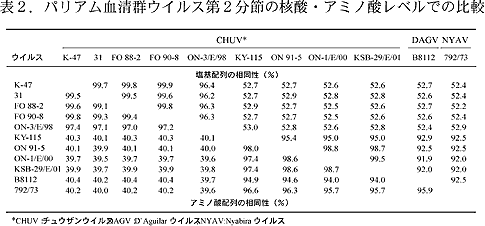
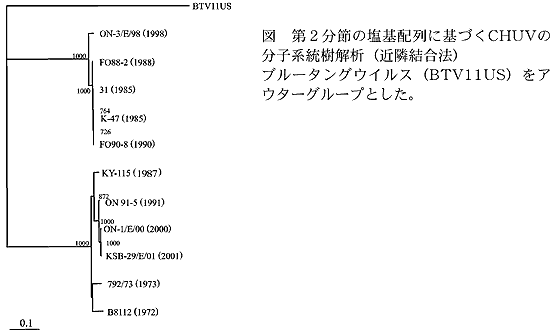
その他
- 研究課題名:ウイルス感染による胎子の形態形成阻害機構の解明
- 課題ID:13-02-01-*-78-04
- 予算区分:交付金プロ/形態・生理(3305)
- 研究期間:2001~2007年度
- 研究担当者:大橋誠一、山川 睦、梁瀬 徹、加藤友子、津田知幸
- 発表論文等:Ohashi et al. (2004) J. Clin. Microbiol. 42:4610-4614.
