組換え型ブタリゾチームの大量生産法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
新たな抗菌物質として期待されているブタリゾチームの遺伝子を人工合成し、昆虫細胞で発現させることにより大量に培養液中に生産できるシステムを開発した。さらに、培養液の浸透圧を調整することによって生産量を大幅に増やすことができる。
- キーワード:ブタリゾチーム、昆虫細胞、バキュロウイルス発現系、至適浸透圧、薬剤耐性菌
- 担当:動物衛生研・次世代製剤開発チーム
- 連絡先:電話041-321-1441、電子メールwww-niah@naro.affrc.go.jp
- 区分:動物衛生
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
近年、抗生物質の多用が薬剤耐性菌の発生を促し、抗生物質が効かない耐性菌が人の体内へ侵入することが懸念されている。特に養豚における飼料添加物としての使用量は非常に多く、抗生物質に代わる抗菌剤の開発が望まれている。ブタリゾチームは天然の抗菌性蛋白質であり、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)のような抗生物質耐性菌に対しても効果が高いことから、抗生物質の有力な代替薬として期待されている。しかしながら天然のブタリゾチームを豚体内から回収して精製するにはコストが莫大なものになるため、生物工学的な手法による量産化が望まれている。
一方、バキュロウイルス発現系を用いた組換え型蛋白質の生産は近年盛んになって来ているが、昆虫細胞の培養方法など周辺技術にはまだ改良の余地がある。特に昆虫細胞用の市販の培養液は細胞の増殖に主眼を置いて開発されたものが多く、生産量のさらなる向上のためには蛋白質の生産性を重視した新しい培養液の開発が望まれている。そこで培養液の浸透圧調整による分泌生産量の増強を図ることによって、組換え型ブタリゾチームの効率的な生産方法の開発を試みている。
成果の内容・特徴
- ブタリゾチーム遺伝子をSPR法およびPCR法によって人工合成し、パン酵母、カイコ系昆虫細胞、ヨトウガ系昆虫細胞で生産して細菌(Micrococcus lysodeikticus)に対する溶菌活性を解析すると、いずれにおいても活性が認められるが、ヨトウガ系昆虫細胞での生産量が有意に高い(表1)。
- 培養液中の抗菌活性成分を精製して、質量分析とN末端アミノ酸配列解析を行うと、分子量がブタリゾチームのアミノ酸配列から予想されるものと一致し、N末端の5残基のアミノ酸配列も一致していることから、培養液中に分泌されている抗菌性蛋白質は天然型のブタリゾチームと同一であることがわかる。
- SF+細胞を培養する昆虫細胞培養液の浸透圧を市販原液(321mOsm/kg)より低い220~309mOsm/kgに調製するとブタリゾチームの分泌量が有意に高い。特に至適浸透圧である296mOsm/kgでは市販原液の1.5倍の生産量に達している(図1)。この手法によってリゾチームに限らず他の様々な有用蛋白質においても生産性を向上させることができ、実用化が可能となる(図2)。
成果の活用面・留意点
- ブタリゾチームを安全に安価に大量生産することが可能となる。特にSF+細胞を用いて低浸透圧(220~309mOsm/kg)で培養した時の生産性は高く、大幅なコストダウンが可能である。
- ブタリゾチームは抗菌性物質や食品保存剤などとして広範な利用が考えられる。
具体的データ
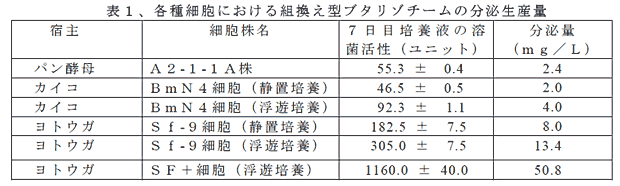
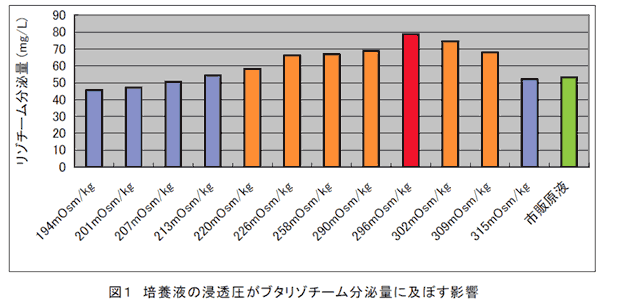
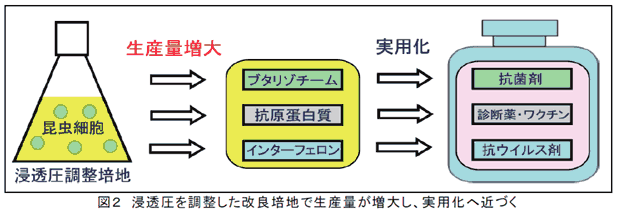
その他
- 研究課題名:生体防御能を活用した次世代型製剤の開発
- 課題ID:322-i
- 予算区分:交付金(共同研究)
- 研究期間:2004~2006年度
- 研究担当者:土屋佳紀、平川雄三(西川ゴム工業)、大礒勲(西川ゴム工業)、森岡一樹、白井淳資、吉田和生
- 発表論文等:1) Tsuchiya et al. (2005) Peptide Science 2004, 557-560.
2) Tsuchiya et al. (2006) Nucleic Acids Symposium Series 50: 275-276.
