牛コロナウイルス日本分離株の分子疫学的解析
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
近年の日本における牛コロナウイルス感染症発生例からの分離株は遺伝学的多様性を示す。塩基配列に基づく系統樹を用いた分子疫学的解析結果は、本ウイルスの流行動態の解明に活用される。
- キーワード:ウシ、牛コロナウイルス、遺伝子型、S遺伝子
- 担当:動物衛生研・環境・常在疾病研究チーム
- 連絡先:電話011-851-2132、電子メール niah@naro.affrc.go.jp
- 区分:動物衛生
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
牛コロナウイルス(BCV)は子牛や成牛の下痢、そして呼吸器病の原因となる。本ウイルスはわが国に広く常在しているが、分離が困難であったためその遺伝学的解析については報告がない。そこで近年の流行株の遺伝学的特徴を明らかにするため、既に報告のある国外株とともに分子系統樹解析を行う。
成果の内容・特徴
- 北海道を含む6道府県における発生例の下痢および鼻汁材料を培養細胞(HRT-18)に接種し、これを継代観察することにより55株のウイルスを得た。(表1)。
- ウイルスの病原性や宿主域に関与するエンベロープ糖タンパクS遺伝子中において遺伝子多様性を示すと報告のあるpolymorphic region (411base)の配列を用い、既に報告のある国外株とともに分子系統樹を作製し、遺伝子型を決定した。
- 国外株と分離株は4つの遺伝子型に分類される。Group1は1976年の日本初発例の掛川株および国外の腸管病原性株(Mebus、Quebec、F15およびLY-138株)で形成される。Group2には呼吸器病原性株(LSUおよびOK株)および韓国株とともに一部の分離株が属している。Group3には分離株の多くが属し、高い遺伝子相同性を示す。2005年以降の分離株は全てGroup4に属する。(図1)。
- 近年の国内流行株は多様な遺伝学的特徴をもち、さらに過去に国内外で分離されたウイルス株とは異なる遺伝学的系統を示す。
- BCVは成牛に持続感染し、北海道からの牛の移動に伴いウイルスも伝播することが推測されるが、今回の成績から他地域に常在し独自に進化する可能性がある。
成果の活用面・留意点
- わが国におけるBCVの遺伝学的特徴が明らかとなったことから、本領域を用いた分子疫学的解析は本ウイルスの流行動態を解明するのに活用できる。
- 病原性や抗原性などのウイルスの生物学的性状と遺伝子型との関連について解析を進める必要がある。
具体的データ
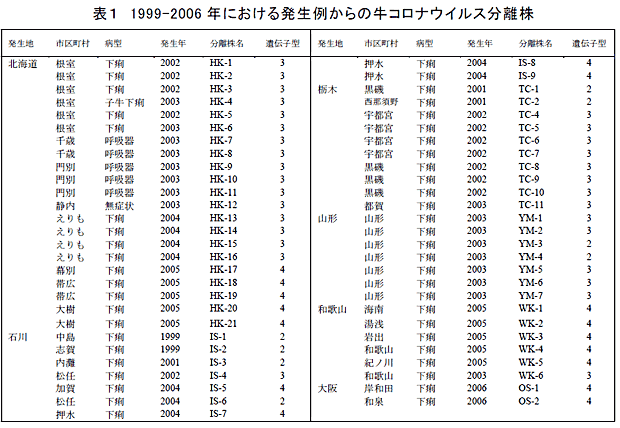
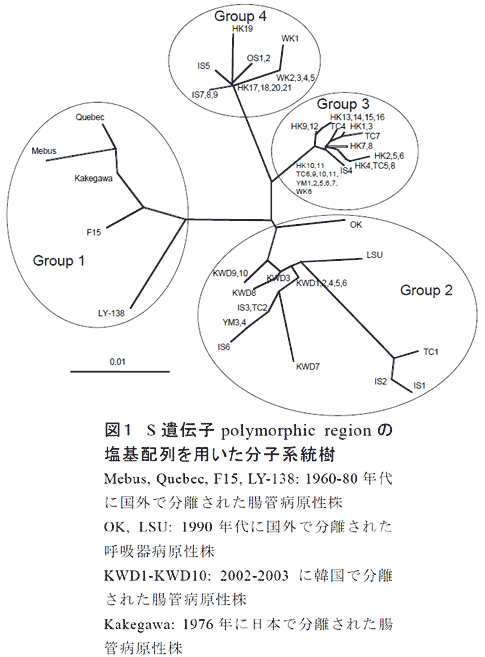
その他
- 研究課題名:環境性・常在性疾病の診断と総合的防除技術の開発
- 課題ID:322-g
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2006~2008年度
- 研究担当者:菅野 徹、畠間真一、石原涼子、内田郁夫
- 発表論文等:Kanno et al. (2007) Molecular analysis of the S glycoprotein gene of bovine coronaviruses isolated
in Japan from 1999 to 2006. J. Gen. Virol. 88:1218-1224
