短日遅延性が大きく暖冬でも出穂が安定する早生大麦系統の作出
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
日長反応性のうち短日遅延性を大きくした大麦の早生系統を作出した。この系統は出穂期の年次変動が小さく、暖冬でも茎立が早くないため凍霜害の発生が少ない。
- キーワード:オオムギ、温暖化、日長反応性、短日遅延性、安定早生、凍霜害
- 担当:作物研・大麦研究関東サブチーム
- 連絡先:電話029-838-8862、nics-seika@naro.affrc.go.jp
- 区分:作物、関東東海北陸農業・関東東海・水田作畑作
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
近年、気候温暖化に伴う暖冬化の影響を受けて、麦類の早生品種では、出穂の異常早進に伴う凍霜害の発生と栄養生長期間の短縮によ り、収量が減少することが懸念されている。麦類の出穂期には純粋早晩性、春化要求性、日長反応性が関係しているが、早生品種ほど日長反応性が弱いとされ、 日長にかかわらず気温が高いと出穂が促進されやすいと考えられる。そこで、日長反応性のうち短日では幼穂分化や茎立が遅延する性質(短日遅延性)を付与す ることで、生育や出穂期の安定した早生品種育成に資する。
成果の内容・特徴
- 短日遅延型早生系統(M/G-3、-6、-133)は、早生の「ミサトゴールデン」と晩生の「ゴールデンメロン」の交配組合 せに由来する組換え自殖系統で、人工気象室を利用して純粋早晩性と短日遅延性が「ゴールデンメロン」並に大きい系統を選抜し、さらに圃場栽培で「ミサト ゴールデン」並の早生となる系統を選抜したものである。本系統は、純粋早晩性と短日遅延性が大きいが出穂期は早生となる(表1)。
- 幼穂分化から発育の期間に当たる1~3月の気温が平年並みの年(2005年)では、短日遅延型早生系統の出穂期は、早生の 「ミサトゴールデン」と同程度であるが、この期間が高温である年(2006及び2007年)では「ミサトゴールデン」よりも出穂の早進程度が小さく、出穂 期の年次変動が小さい(図1、表1)。
- 短日遅延型早生系統は、暖冬年であっても茎立が早くなり過ぎず(図2)、凍霜害の発生が少ない(図3)。
成果の活用面・留意点
- 本系統は安定早生大麦品種育成のための新たな育種素材として利用できる。
- 本系統が持つ日長反応性遺伝子については未解明である。
具体的データ
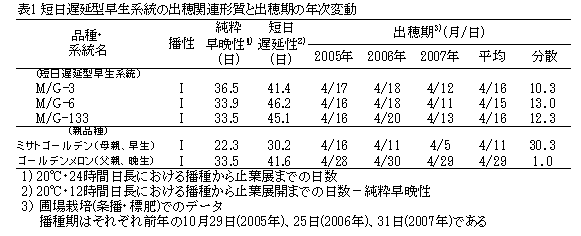
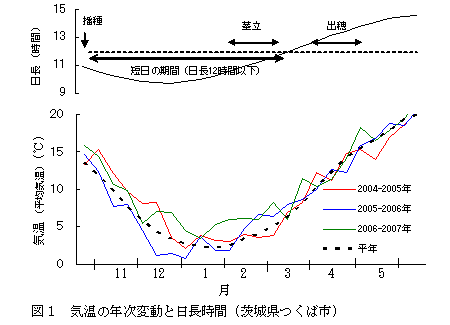
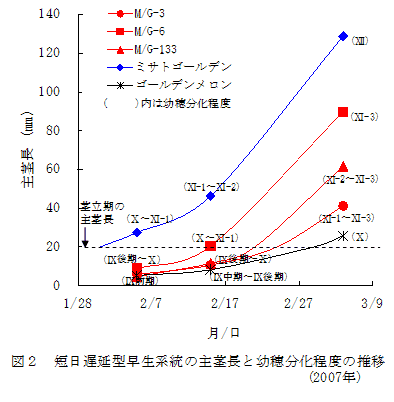
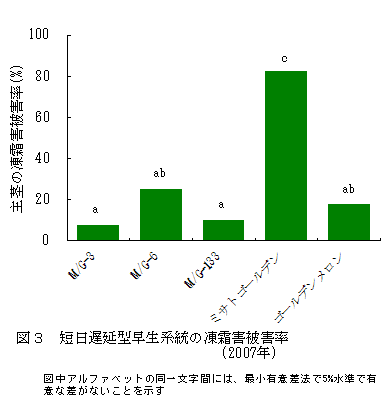
その他
- 研究課題名:大麦・はだか麦の需要拡大のための用途別加工適性に優れた品種の育成と有用系統の開発
- 課題ID:311-d
- 予算区分:交付金プロ(気候温暖化)
- 研究期間:2003~2007年度
- 研究担当者:塔野岡卓司、吉岡藤治、青木恵美子
