牛の第一胃に浸漬した雑草種子の発芽率
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
雑草種子を牛の第一胃に入れ、経時的に発芽率を調査した結果、3日間の浸漬でも全ての草種で発芽力を持つ種子が存在した。発芽が促進された種も多く、第一胃の消化作用で雑草種子の発芽力を低下させることは困難である。
- 担当:草地試験場・放牧利用部・草地管理研究室
飼料生産利用部・栽培生理研究室 - 連絡先:0287-36-0111
- 部会名:草地・生産管理
- 専門:雑草
- 対象:作物全般
- 分類:研究
背景・ねらい
輸入飼料の増加に伴い、今まで日本ではあまり問題にされていなかった新しい雑草の発生が草地及び飼料畑で大きな問題になっている。そのような海外から持ち込まれる雑草の侵入経路として輸入飼料中の雑草種子が考えられるが、牛の第一胃の消化作用で、どれだけ発芽力を低下させ得るのかを明らかにし、侵入経路の特定と遮断に資する。
成果の内容・特徴
- 15種の雑草種子をイネ科主体乾草を給与したフィステル付きホルスタイン育成牛の第一胃に入れ、1、2及び3日間浸漬した後、取り出し、20/30°C(12時間ずつ、高温時明条件)の変温条件で10日間培養し、発芽率を調べた。対照区として無処理の種子を同じ条件で培養し、発芽率を調査した(表1)。
- アメリカオニアザミ(図1a)及びイヌタデは、通常の滞留期間とされる1日間で、発芽率が低下した。
- アメリカセンダングサ(図1b)及びイチビは2日間以上浸漬すれば対照区より発芽率が低下した。また、メヒシバは、処理区の発芽率が対照区を上回るものの、浸漬時間が長くなるにつれて発芽率の低下が見られた。
- オオブタクサ(図1c)は、全区の発芽パターンがほぼ同じであり、処理による発芽率の低下は見られなかった。
- イヌビエ(図1d)は、処理期間が長くなるほど常に累積発芽率が高く、第一胃浸漬に休眠覚醒効果があったことが明らかである。ホソアオゲイトウ、ハリビユなども処理による休眠覚醒効果が明らかであった。
- 第一胃浸漬処理の影響は以上の4つに大きく分けられたが、いずれの種においても浸漬後も発芽力を有する種子が残るため、第一胃の消化作用で雑草種子の発芽力を低下させることは困難である。
成果の活用面・留意点
- 現在、草地、飼料畑で増加している帰化雑草の侵入経路を研究する上で有効である。
- 浸漬時間及び第一胃のpH等の条件が種子の生死に及ぼす影響の定量的な把握については、明らかになっていない。
具体的データ
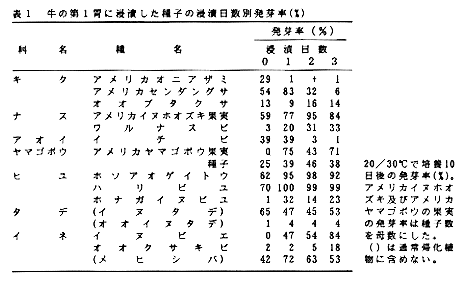
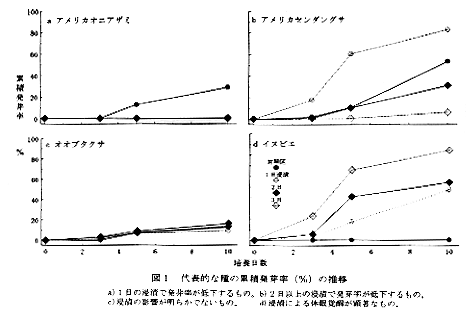
その他
- 研究課題名:草地への強害新帰化植物の侵入・定着・拡散機構の解明
- 予算区分 :特別研究(帰化雑草)
- 研究期間 :平成5年度(平成5年~8年)
- 発表論文等:草地、飼料畑への外来雑草種子の侵入経路とその遮断、自給飼料、20号、
1994
