採草地における土壌貫入抵抗の推移
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
採草地で水平保持機構付き土壌硬度測定装置で土壌貫入抵抗を多数点、一定間区で経年的に測定し、その推移を明らかにした。機械作業による土壌貫入抵抗の増加程度は、表層が顕著であった。又、その増加程度は新しく造成した草地と経年草地とでは前者が大きい傾向を示した。
- 担当:草地試験場・山地支場・作業技術研究室
- 連絡先:0267-32-2356
- 部会名:草地・飼料利用
- 専門:機械
作業 - 対象:牧草類
農業工学 - 分類:研究
背景・ねらい
採草地では、施肥作業や収穫作業で、トラクタ等が繰り返し走行する。そのため、それによる草地土壌のち密化が牧草生産へ与える影響が懸念される。しかし、ち密化の実態は、十分明らかとはなっていない。そのため、現地圃場の土壌貫入抵抗の年間および、年次的変化を調査する。
成果の内容・特徴
利用・履歴の異なる3つの採草地(表1、3)において、当研究室が開発した水平保持機構付き土壌硬度測定装置(草地飼料作 研究成果最新情報 第8号 P59~60参照)で土壌貫入抵抗を、多数点(100点余り)、一定間区(10mメッシュ)で経年的に測定し以下の結果を得た(図1、表2)。
- 地表面から最大貫入抵抗に至るまでの貫入抵抗の増加傾向は、造成間もないA圃場では急で、造成後20数年を経たB、C圃場では、緩やかであった。すなわち、造成後2年間における表層の貫入抵抗の増加が著しかった。
- 平均貫入抵抗は、春先は低く、1番草、2番草収穫作業後に高くなり、最終番草収穫作業後の秋は、春先に次いで低くなった。この間の貫入抵抗の増減には、土壌水分および、機械作業が関係していると推察された。
- 施肥作業前(1994年4月)と最終番草収穫作業後(1994年10月)とを比較すると、A圃場では作業前より収穫作業後が土壌水分が高いにもかかわらず、表層から5cmまでの部分が、測定時期の土壌水分がほぼ同じB圃場では表層から12cmの部分が平均貫入抵抗が増加していた。これらは、いずれも機械作業による現象と推察された。
- A、C圃場では、最終番草収穫作業後(1993年10月)から翌年の施肥作業前(1994年4月)までの越冬期間中に、表層部分の貫入抵抗が減少していた。これは、冬期の土壌凍結に起因する現象と推察された。又、表層部分の貫入抵抗の減少割合は、A圃場では大きくC圃場では小さかった。
成果の活用面・留意点
- 採草地のち密化の過程を明らかにするための参考資料として有効である。
- この結果は土壌が表層多腐植質黒ボク土のものである。
具体的データ
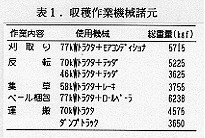
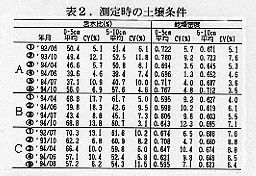
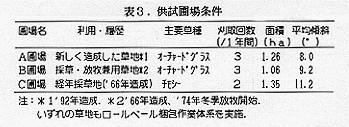
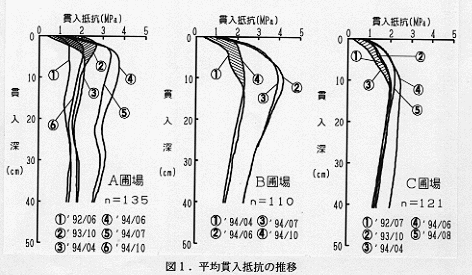
その他
- 研究課題名:機械作業が傾斜草地に与える物理的影響
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :平成6年度(平成3年~6年)
- 発表論文等:1) 傾斜草地土壌における貫入抵抗測定に関する研究I、草地試研報
50p43~52(1994)
2) 草地におけるトラクタ走行と土壌踏圧の関係 53農機学会年次大
会講要p483~484(1994)
