都府県酪農におけるふん尿処理・利用方式のデータベース
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
公的機関の調査協力を得て作成した本データベースは46都府県の酪農家762戸、調査内容は8項目からなっている。地域、また飼養頭数といった調査項目別に農家のふん尿処理・利用方式を類型化できる。また、農家の抱える問題点についても項目ごとの類型化が可能である。
- 担当:草地試験場 放牧利用部 施設工学研究室
- 連絡先:0287-37-7814
- 部会名:畜産
- 専門:農業施設
- 対象:乳用牛
- 分類:行政
背景・ねらい
我が国の酪農経営においては家畜ふん尿を農地に還元して有効に利用するのに必要な耕地を十分に有していない場合が多いため、家畜ふん尿を良質な堆肥 に調製し、広域流通を促進する必要がある。しかし、処理施設が大型化する傾向にあり、コストや処理作業の面で多くの問題を抱えている。そこで、酪農におけ るふん尿処理・利用に関するアンケート調査を行い、収集した情報をデータベースにまとめる。それをもとに経営体におけるふん尿処理・利用の実態を解析し、 今後の研究開発、行政施策に資する。
成果の内容・特徴
国公立試験研究機関、行政機関の協力を得て、46都府県を[対象]に酪農におけるふん尿処理・利用に関するアンケート調査を行った。農 家の選定は各都府県に一任し、作成した調査表をもとに面接方式で行った。762戸の酪農家からアンケートを回収し、それをもとにふん尿処理・利用に関する データベースを表計算ソフト上で作成した。データベースからは飼養頭数別、地域別に項目(表1)毎の必要なデータを抽出できる。
調査[対象]の農家規模は、飼養頭数が30~40頭である農家が最も多い。飼養頭数は最小2頭から最大720頭の範囲にあり、平均は52頭である。飼養方式は飼養頭数が増加するほど放し飼い方式を採用する農家の割合が高くなる(図1)。
飼養頭数別にふん尿処理施設の稼動状況を見ると堆肥舎を使用する割合が最も高い。また、堆肥盤は飼養頭数に関係なくほぼ一定水準に あるものの、堆肥舎、開放型攪拌堆肥化施設、ふん尿乾燥施設は飼養頭数が増加するほどその稼動割合も高くなる。スラリー貯留施設に関しては50~80頭でピークとなり、80頭以上になると稼動割合は減少する(図2)。
飼養頭数80頭以上の大規模農家、80頭以下の中小規模農家に区分けして農家の抱える問題点を比較すると、大規模農家で問題を抱えている割合が高い。大規模、中小規模農家ともに「建設費が高い」ことに対して強い関心を示し、次いで大規模農家では「処理能力が不足」を、中小規模農家では「ほ場面積が不足」、「臭気対策ができない」となっている。(図3)。
成果の活用面・留意点
- 本データベースは今後のふん尿処理・利用に関わる研究開発、施策の際の指針に利用できる。なお、公的機関の希望に応じてFD等による配布が可能である。
- 北海道におけるデータは今回のデータベースには含まれていない。
具体的データ
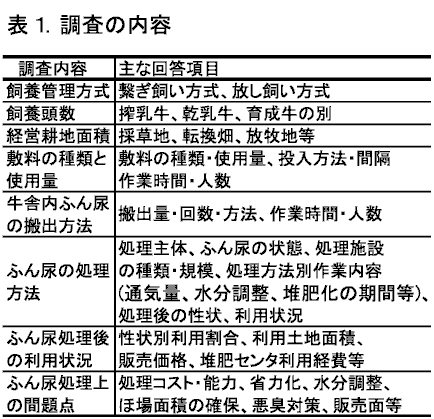
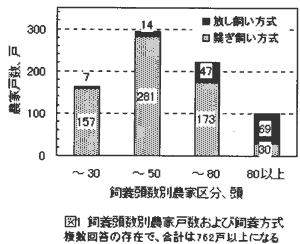
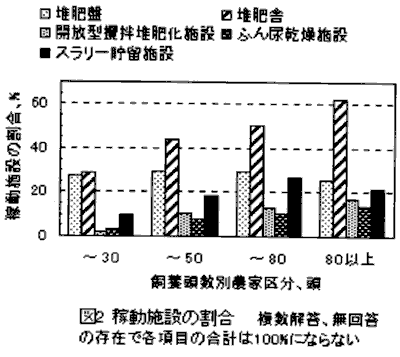
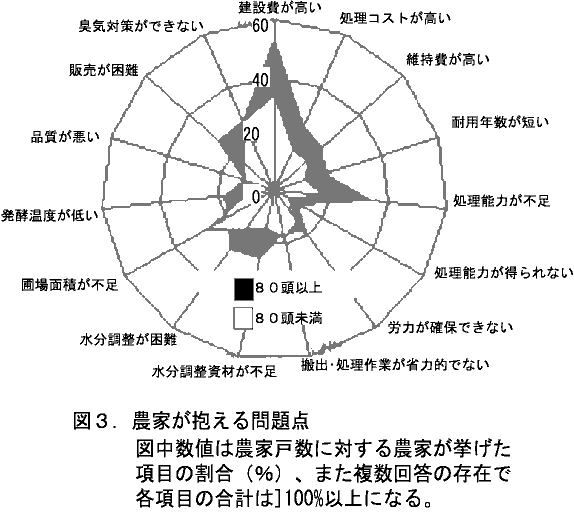
その他
- 研究課題名:既往の家畜排泄物処理・利用システムの評価及び実証
- -酪農における処理・利用の評価-
- 予算区分:総合的開発(家畜排泄物)
- 研究担当者:阿部佳之、伊藤信雄、梅田直円、加茂幹男
- 発表論文等:
1.酪農におけるふん尿処理の実態、1999年度農業施設学会講演要旨集
2.施設工学研究室、わが国の酪農におけるふん尿処理の実際一酪農におけるふん尿処理実態調査報告書-、1999 (国公立試験研究機関、行政機関に配布済み)
