放牧条件下における同期化処置を用いた繁殖管理に関わる作業性向上
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
放牧条件下において、排卵ならびに発情同期化処置は発情観察に要する時間、1頭のAIに要する時間ならびに受胎牛1頭に要する人数、時間を減らすことができる。
- キーワード:家畜繁殖、肉用牛、排卵同期化、発情同期化
- 担当:畜産草地研・山地畜産研究部・家畜飼養研究室
- 連絡先:電話0267-32-2356、電子メールguchi@naro.affrc.go.jp
- 区分:畜産草地
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
肉用牛繁殖農家の規模拡大による労力や畜舎コストの負担増加を抑える方法として、放牧飼養の導入が重要になっている。 一方、放牧では監視に多大な労力や時間が必要であることから、放牧飼養では省力的な繁殖管理がより強く求められる。そこで、放牧条件下において、排卵ならびに発情同期化処置を活用した繁殖管理について検討する。
成果の内容・特徴
- ホルモン剤投与ならびに人工授精(AI)作業については、群または対象牛を放牧地から作業場まで誘導するための必要人数を3人としている。発情観察は、原則として1人が朝夕の1日2回行う。朝、発情が見られた場合は、AI適期を判断するため、昼も発情観察を行う。AIは全頭で行い、1頭につき1回実施している(図1)。
- 発情同期化は直腸検査を行い、黄体の存在が確認された個体のみ供試する。黄体が確認できず、処置しなかった個体は11日後に同じ処置を行う。排卵同期化は発情周期に関係なく開始する。
- 各作業時間は、放牧地から作業場までの誘導作業が25分、1頭あたりのホルモン剤投与は排卵同期化では5分、発情同期化では15分(直腸検査が10分)、1頭あたりのAI作業は10分、1回の発情観察は25分(放牧地までの移動時間が10分、観察時間が15分)としている。
- 排卵同期化では処置開始の10日後にAIを実施するが、その間の作業回数は、3回のホルモン剤投与ならびにAI作業の4回で済む(表1)。
- 発情同期化では、発情が集中するため、発情観察に要する時間を少なくすることができ、1頭のAIに要する時間が少なくて済む(表2)。
- 受胎率は排卵同期化法がもっとも低くなったが、1頭の受胎に要する時間は、排卵同期化法が対照区の30.3%であり、もっとも少なくて済む(表2)。
成果の活用面・留意点
- 放牧条件下における肉用繁殖牛の繁殖管理が容易になる。
- ホルモン剤コストと労働費のバランスを試算するための基礎データとして用いる。
- 誘導に要する人数、作業時間は、放牧地の地形や牛の操作性などによって変更し、試算し直す。
具体的データ
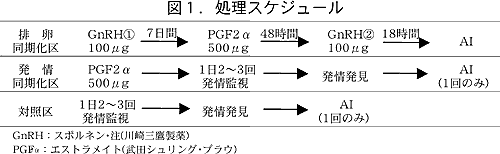
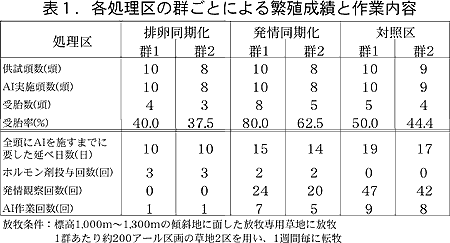
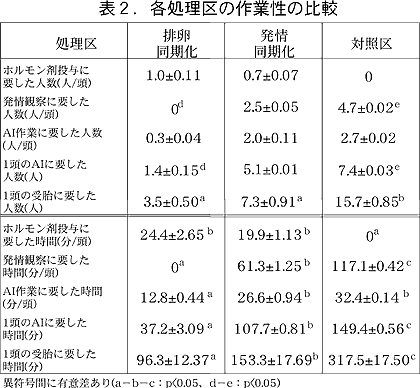
その他
- 研究課題名:山地傾斜地放牧における肉牛繁殖技術の効率化に関する検討
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2003~2004年度
- 研究担当者:山口 学、林 義朗
