飼料用トウモロコシの2003年冷害の発生様式
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
関東北部における2003年夏季の低温、及び日射量の不足は、飼料用トウモロコシの収穫までに至る栽培日数を延長させ、雌穂の乾物収量に大きな被害を与えた。その被害の様相から登熟遅延型の冷害であった。
- キーワード:トウモロコシ、冷夏、相対熟度、雌穂乾物重、草地生産管理
- 担当:畜産草地研・飼料生産管理部・栽培生理研究室
- 連絡先:電話0287-37-7802、電子メールsoichi@affrc.go.jp
- 区分:畜産草地
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
我が国において冷夏は約10年に一回の頻度で襲来し、作物栽培に多大な被害を与えている。夏作物であるトウモロコシにおいても同様に被害の事例はあるが、被害の発生様式についての報告は少ない。そこで、極早生~晩生の44品種を用いた栽培・乾物収量調査の結果から2003年に発生した冷害被害の発生様式について明らかにし、さらに今後の被害回避のための知見とする。
成果の内容・特徴
- 栃木県北部(西那須野町)において、2003年の5, 6月の平均気温、日射量は平年並みであったのに対し、トウモロコシの絹糸抽出期にあたる7月の日平均気温は19.3℃と平年比 -3℃、日射量は12.7MJ/m2と平年比-3.7MJ/m2であり、8月中旬においても気温で-3.9℃、日射量で-6.4MJ/m2と低下が見られる(表1)。
- 2002年と2003年を比較すると、7月初旬(播種45日後)の初期生育は両年で差が見られず、低温期間以前の気象に差はない(表2)。
- 2003年の収穫時における生育量(草丈、稈径)、および茎葉の乾物収量は2001、2002年と比較して差が見られない(表2)。
- 一方、雌穂の乾物収量は、早晩性にかかわらず低下が認められた(図1)。また2003年の絹糸抽出は2002年より平均6.7日、2001年より平均11.4日遅れ、この遅れがそのまま収穫適期である黄熟期に至る栽培日数の延長につながっている(表2)。同時に日当たり雌穂の生産速度も低下している(図2)。
- しかしながら相対熟度別では、早生品種が最も高い雌穂乾物収量と日生産速度を示しており冷害発生の際にも減収程度が比較的少ない(図1, 2)。
- 以上の結果から、2003年冷夏はすべての熟期のトウモロコシに対し絹糸抽出の遅れと登熟遅延を引き起し、子実の充実不足を招いて減収に至ったと結論される。
成果の活用面・留意点
- 飼料用トウモロコシ栽培における作付け時期、及び品種選定のための基礎情報となる。
- 冷害の起こり易い地域においてはトウモロコシの栽培にあたり早播きの励行、堆肥の積極的施用等に努め、被害の発生をできるだけ少なくするような技術的対策を常に意識しておく必要がある。
具体的データ
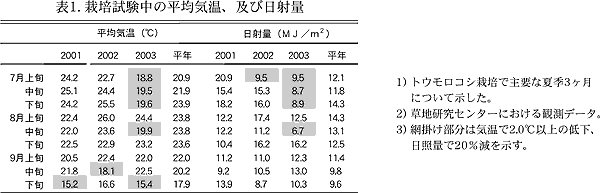
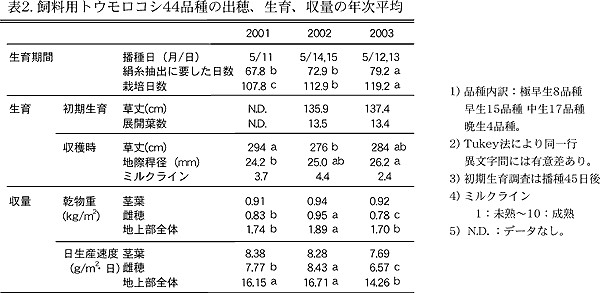
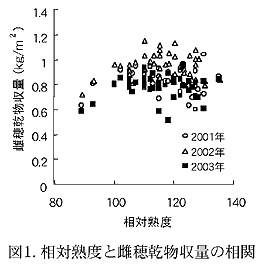
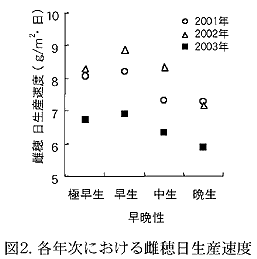
その他
- 研究課題名:サイレージ用トウモロコシの気象変動等に対する収量安定性の評価
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2003~2005年度
- 研究担当者:森田聡一郎、吉村義則、黒川俊二
