北海道の草地における土壌炭素蓄積量の分布図
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
北海道の草地について、植生および土壌に関する既存のデジタルデータを用いて、土壌群ごとに地表から75cmまでに蓄積されている炭素量を算出し、炭素蓄積量の分布図を作成した。
- キーワード:永年草地、土壌、炭素蓄積量、分布図、デジタルデータ
- 担当:畜産草地研・草地生態部・草地資源評価研究室
- 連絡先:電話0287-37-7246、電子メールshojim@affrc.go.jp
- 区分:畜産草地
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
草地生態系は陸域生態系の約4分の1を占めており、地球全体の炭素収支に及ぼす影響が大きいため、その炭素吸収能を評価することは極めて重要である。世界的に見て草地生態系は炭素の吸収源になっているという報告が数多くなされている。しかし、わが国においては、草地の持つ炭素吸収能の評価に必要な土壌炭素蓄積量についてほとんど明らかにされていない。そこで、全国の草地面積の約80%を占める北海道地方について、植生と土壌に関する既存のデジタルデータを用いて、草地における土壌炭素蓄積量の分布図を作成する。
成果の内容・特徴
- 草地における土壌炭素蓄積量分布図の作成手順は以下の通りである(図1)。
1)使用したデジタルデータ:(1)植生調査ベクタデータ(自然環境情報GIS;自然環境保全基礎調査(1983~98年)によ
る)、(2)土壌断面データ(土壌情報データベース;施肥改良事業・地力保全基本調査(1959~79年)による)、(3)土壌図
ベクタデータ(土壌情報データベース)、(4)土地分類メッシュデータ(国土数値情報)の土壌分類データ
2)作成の手順:(1)植生調査ベクタデータから草地に分類できる部分を抽出し、草地分布図を作成する。(2)土壌断面
データより土壌の炭素蓄積量を土壌群ごとに算出する。(3)土壌図ベクタデータと(2)のデータを対応させることによ
り、土壌炭素蓄積量分布図を作成する。土壌図ベクタデータの存在しない地域については、土地分類メッシュデータ
と(2)のデータを対応させて1kmメッシュの土壌炭素蓄積量分布図を作成する。(4)土壌炭素蓄積量分布図から草地
分布図と重なる部分を抽出し、草地における土壌炭素蓄積量分布図を作成する。 - 単位面積あたりの炭素量を地表から25cm刻みで土壌群ごとに算出したところ、深度が大きくなるに従って炭素データの存在する断面数は少なくなるが、多くの土壌群で75cmまでのデータが得られた(表1;0~25cmは略)。
- 草地における地表から75cmまでの土壌に蓄積されている炭素量の分布図を作成した(図2)。75cmまでのデータが存在しない土壌群については50cmまでのデータを用いた。この範囲に蓄積されている炭素量は10~30kg m-2 の地域が多く、炭素蓄積量の分布の差は小さい。しかし、北海道東部や北部の黒ボク土、黒泥土、泥炭土地帯では多くの炭素が蓄積されている。
成果の活用面・留意点
- 草地の炭素蓄積量を評価するための基礎的なデータとなる。
- 断面数の少ない土壌群についてはデータの信頼性が低い。
- 使用した土壌断面データの調査地点の地目は様々であり、草地とは限らない。中井(農業技術、2003)によると、炭素蓄積量は他の地目より草地の方が多い傾向にある。このことから、実際の草地の炭素蓄積量は本成果より多いものと考えられる。
具体的データ
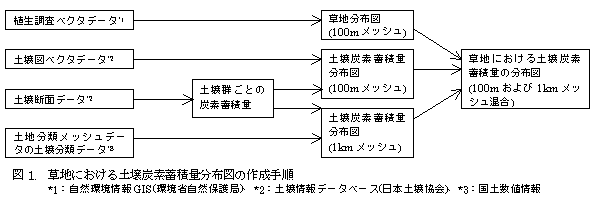
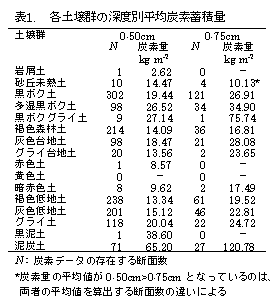
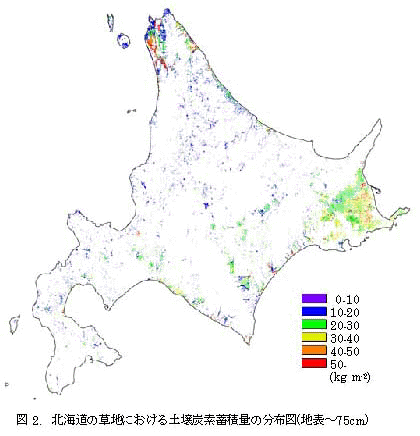
その他
- 研究課題名:草地土壌中の炭素蓄積量マップの作成
- 予算区分:草地畜産種子協会
- 研究期間:2004年度
- 研究担当者:松浦庄司、神山和則、佐々木寛幸
