貯水池群における最適な貯水量管理手法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
貯水池群の利水運用特性を明らかとし、これらを考慮して線形計画法等を適用し、貯水池間の最適貯水量関係を求める近似解法を開発した。
- 担当:農業工学研究所・農村整備部・施設管理システム研究室
- 代表連絡先:0298-38-7666
- 部会名:農業工学
- 専門:基幹施設・環境保全・農村整備
- 対象:維持・管理技術
- 分類:指導
背景
水資源の逼迫等により複数貯水池を最適に運用して水資源を有効に利用する技術が必要となっている。最適な利水運用方法を求める手法としては、動的計画法があるが、計算量が大きく計算過程が不明である等の欠点がある。このため、貯水池群の利水運用特性を明らかとし、計算量の少ない最適利水運用方法の近似解を求める手法を開発した。
成果の内容・特徴
複数の貯水池を有する地区では地区全体として貯水量をバランス良く保ち運用を行うことが望ましい。このために貯水池間の最適な貯水量の関係を知ることが必要であり、これを求める近似解法を作成した。その特徴は次の通りである。
- 貯水量が貯水池への流入量と貯水池からの取水量の2つの変動する要素によって定まるために利水運用計算は複雑となる。そこで、流入量を0とした計算と取水量を0とした計算の2つに分けることにより計算量を低下させる。前者による解(利水運用方法)は渇水被害を均一にする働きがあり、後者で求められた解は水資源を有効に利用する効果がある。この2つの解は矛盾する場合があることを明らかとした。矛盾しない場合は線形計画に、矛盾する場合は2次計画になるがいずれもシンプレックス法または修正シンプレックス法で解くことができる。この近似解法によって図1に示す地区で貯水量間の最適関係を求めた例を確率的動的計画法による解とあわせて図2に示す。また、これによる水資源が有効化された例を図3に示す。
- 動的な貯水運用の検討に使用する確定量の算出方法としては渇水要貯水量曲線法または渇水持続曲線法が適当であることは既に明らかであるが、この時採用する非超過確率によって近似式の精度は影響を受ける。一般的には潅漑計画に使われている1/10の様な小さな確率値、いわゆる渇水状況を想定して計算することにより解の精度は高くなると言われている。渇水被害を均一にする運用法の算出にはこれが適切であることが明らかとなった。しかし、水資源を有効にする運用法の算出にはこれは適切でなく、場合によってはいわゆる豊水状況を想定して計算することによって解の精度が高くなることが明らかとなった。
成果の活用面・留意点
ため池群の様な複数の貯水池が多数連携している地区において総合的な運用が行われる場合に運用指標としてこの近似解法は有効である。但し、受益地の分類方法には経験を要すること、確定量の作成方法に地区特性があることなどに留意しなければならない。
具体的データ
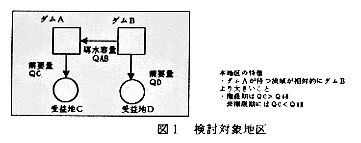
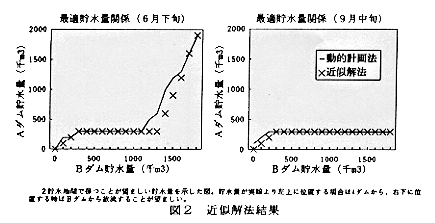
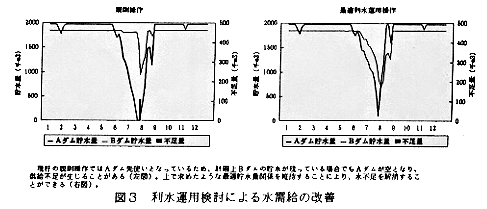
その他
- 研究課題名:貯水池群利水運用特性の解明
- 予算区分:経常・依頼・受託
- 研究期間:平成6年度(平成4~6年)
- 発表論文等:貯水池群の分類と利水運用特性、応用水文5、PP.67-72
