自動転倒ゲートとフィン群による河ロミオ筋の維持・拡大工法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
低水時においても掃流力増強が行える自動転倒ゲートシステムと矢板状フィン群による局所洗掘を組み合わせた新たな河口改良工法は、河口前面のミオ筋の維持・拡大に有効である。
- 担当:農業工学研究所・水工部・河海工水理研究室
- 代表連絡先:0298-38-7543
- 部会名:農業工学
- 専門:基幹施設
- 対象:農業土木
- 分類:研究
背景
河口閉塞には、塩水の遡上を抑制する機能もあるが、洪水時の湛水被害や平水時の排水不良、その結果もたらされる水質悪化の原因にもなり、治水、利水の両面からその対策の確立が迫られている。従前の導流堤や暗渠などの対策工法やポンプ排水、あるいは高架水槽(ヘッドタンク)による人為的にフラッシュする工法があるが、低水時の閉塞回避、また維持管理と大量のフラッシュ水の確保に問題がある。一方、千鳥状に杭群を河口近傍の流れに沿って配置する工法は、たえず洗掘が生ずるような波が作用している状況であれば、極めて有望な河口閉塞対策工法となり得るが、洪水と波に依拠しているので、その効果は自然の不確実性に左右されると云う側面を有していることも否めない。これの不確実性を克服しすることを念頭に置いて、新たな河口改良工法を提案した。
成果の内容・特徴
河口近傍のミオ筋の維持が問題になるのは、流量が少ない低水時である。この少ない流量を有効に利用し、自動的にミオ筋を開削し維持していく上で自動転倒ゲートシステムが有効である。(図1)ミオ筋を開削できない程度の流量でも、河道などに貯留し、瞬間的に放流すれば、掃流カの大きな流れを発生できる。しかし、掃流カを増強するだけでは、沖まで達するミオ筋は形成されない。これを克服するために、流れに沿って二列に配列したフィン群(河口延長線上の前浜に直線的に矢板状のボトムパネル群を配置、フィンは常に水面に出ている)の設置が有効である(図2)。以上を移動床模型で実験的に確認し、様々なフイン群の配置法(図3)の効果を検討した。
- 左右フィン群間隔Dt(横断方向配列法)は、河口左右岸の延長線より外側に直線状に配置したII、IIIの配列が有効である。(図4)
- 流れ方向のフィン間隔DfがDf/B≒1程度でも(Bは河口幅)、明瞭なミオ筋が形成される。しかし、フィン周りの流れと砂移動との局所現象が相互に干渉する程度であればフィン群の効果がより大きい。
- フィン幅bは、b/B≒0.1程度であっても、フィン群の効果は十分発揮させ得る。
- 放流流量を増加させても、形成されるミオ筋の規模は飛躍的に拡大しない。一回の放流の継続時間を長くする方がミオ筋維持する上で有利である。
成果の活用面・留意点
干潟などを対象にする場合は、底質の泥土と今回実験に用いた砂との流送機構の差異による影響を十分考慮する必要がある。現地の状況によっては、波や潮汐の影響も問題になる場合もある。さまざまな条件で現地試験を行い、工法の効果と実験では予測できなたった問題点を把握し、現地への適用を行う必要がある。
具体的データ
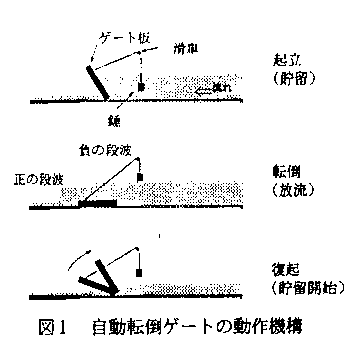
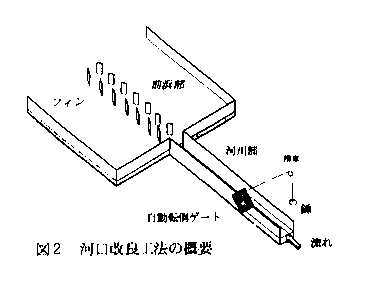
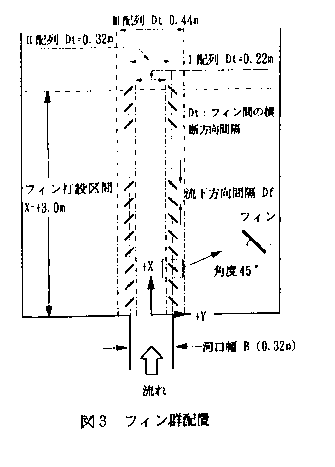
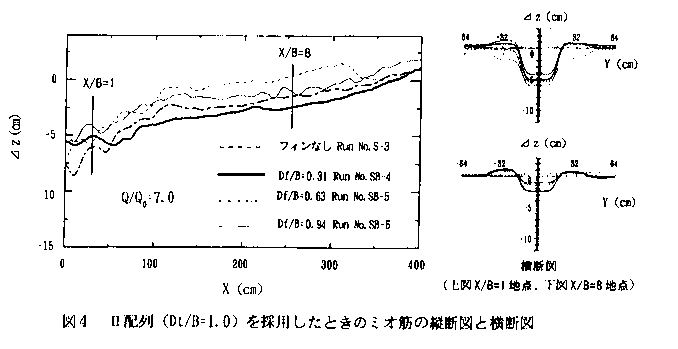
その他
- 研究課題名:非線形性を考慮した浅海域波動場の解析技術の高度化
- 予算区分:経常(依頼)
- 研究期間:平成7年度(平成6年-10年)
- 発表論文等:掃流力増強と局所洗堀による河口澪筋の維持
-自動転倒ゲートシステムと矢板群の組み合わせ工法の可能性-、
農土学会論文集(184)掲載予定
