農業用ダムの堆砂実態と堆砂要因
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
全国53地区の農業用ダムの堆砂ダータを他用途のダムと比較したところ、農業用ダムはC/I比と比堆砂量が大きいという特徴がある。比堆砂量を増加させる堆砂要因としては、貯水位変動や流域の比流量の大きさが考えられる。
- 担当:農業工学研究所・水エ部・河海工水理研究室
- 代表連絡先:0298-38-7567
- 部会名:農業工学
- 専門:基幹施設
- 対象:農業工学
- 分類:普及・行政
背景
戦後、食料の安定供給のために土地改良事業によって多数の農業用ダムが建設されたが、新規水需要に対する新たなダム建設は年々困難になっている。既存ダムの有効利用は不可欠であるが、堆砂によって有効貯水量が減少する問題がある。従来、堆砂研究は発電用ダムを中心に行われてきたが、農業用ダムの堆砂実態・堆砂要因は殆ど調べられていない。ダムの堆砂要因は流域の環境が支配する要因と貯水池の環境が支配する要因に分けられ、無数に存在するが、堆砂対策を立てるためにはダムごとに堆砂要因を特定する必要がある。ダムのC/I比(ダムの貯水容量C(m3)とダムヘの年間総流入水量I(m3)との比)を主な指標として、農業用ダムの堆砂対策を目的とした堆砂実態・堆砂要因の巨視的な調査・分析を行った。
成果の内容・特徴
全国の53地区の農業用ダムの堆砂量、貯水容量、流域面積、年間貯水位、年間流入水量等のデ-タを収集し、他用途のダムのデータと比較して、以下のことが明らかになった。
- 農業用ダムの貯水容量に対する流域面積は他の用途のダム(主に発電用ダム)に比べて小さい(図1)。このため農業用ダムはC/I比が大きいという特徴を持つ。
- 農業用ダムの比堆砂量(単位流域面積、単位年数あたりの堆砂量)は他用途ダムに比べて大きく(図2)、特にC/I比が0.1近傍の農業用ダムに比堆砂量の大きいものが多いという特徴がある。
- 農業用ダムの年間貯水位実積曲線の最高値と最低値の差の数年間の平均値(m)をダムの有効水深(m)で除した値を「貯水位の変動の大きさ」と定義すると、比堆砂量が1000m3・km-2・year-1に達するような農業用ダムほどこの値が大きい(図3)。これは、貯水位変動が大きくなると貯水池上流端の堆砂の移動が促進されるためであると推察できる。
- ダムヘの年間総流入水量I(m3)をダムの流域面積F(m2)で除した値I/F(以下I/F比と呼ぶ)は比流量と同種の値である。農業用ダムのI/F比は、発電用ダムに比べて小さくない(図4)。既往の研究から、流域の比流量が大きくなると浮遊砂輸送量が増加することがわかっているので、農業用ダム流域の比流量は土砂の流入量を大きくする要因の一つと推察できる。
- 上記の実態に基づき、現地の堆砂対策選定の指針として、下記の提案ができる。すなわち、農業用ダムのC/I比が大きいこと(1)から、貯水池は密度成層化している可能性があり、大量の貯水を消費しない泥水密度流による淘水放流策は有効である。貯水位変動が大きいこと(3)からは、低水位の期間を短くするなどの貯水位運用、貯水位の低下による堆砂の再侵食を抑制する土砂留め工等が有効である。比流量が大きいこと(4)からは、流域の浮遊砂輸送量を抑制するための護岸・被覆工等の発生原対策が有効である。
成果の活用面・留意点
農業用ダム管理や数あるダム堆砂要因の特定作業に際しては、本成果で示したC/I比、貯水位変動の大きさ、I/F比を堆砂指標として堆砂の動向を調査し、堆砂対策を立てる参考とできる。
具体的データ
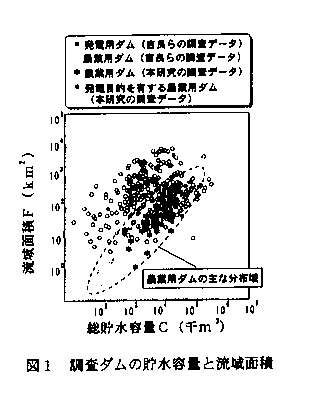
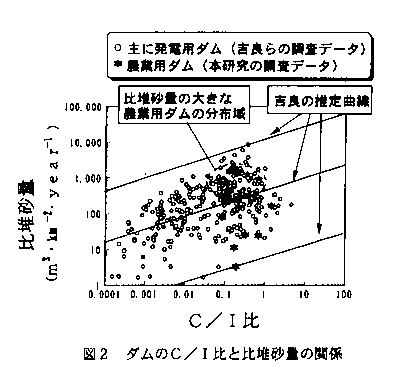
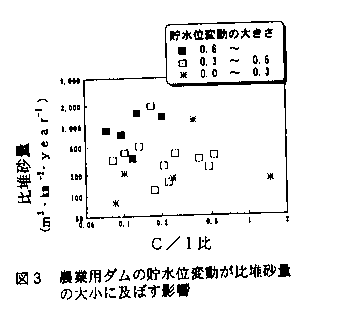
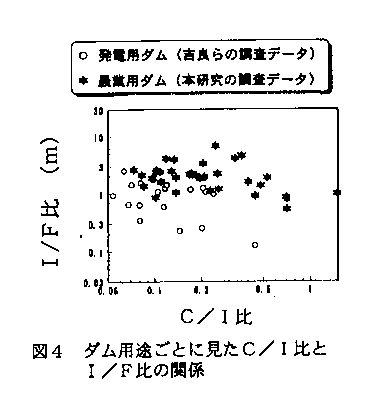
その他
- 研究課題名:河口堆砂の予測・制御技術の開発
- 予算区分:経常・依頼[本省設計課]
- 研究期間:平成7年度(平成6-10年)
- 発表論文等:貯水池の堆砂捕捉率に関する考察、農土学会年講要旨、1995
農業用ダムの堆砂要因に関する考察、農土学会誌、1996,掲載予定
