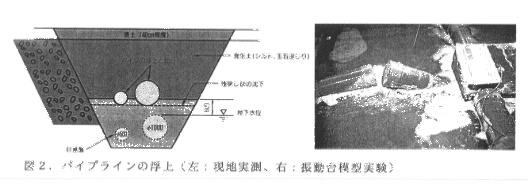北海道南西沖地震によりため池、パイプラインに発生した大規模被害の原因解明
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
北海道南西沖地震により、堤高15mのため池(丹羽生嶺ダム)では堤頂部を中心に大きな亀裂と沈下が、また農業用大口径パイプラインでは大規模な浮上、蛇行などの被害が発生した。現地実態調査、動的解析、振動台実験により、これらの被害の原因が液状化であることを明らかにした。
- 担当:農業工学研究所・造構部・構造研究室,土質研究室 企画連絡室・研究技術情報官
- 代表連絡先:0298-38-7570
- 部会名:農業工学
- 専門:基幹施設
- 対象:現象解析技術
- 分類:研究
背景
1993年北海道南西沖地震は、約800箇所150億円に及ぶ甚大な被害を、農地及び農業用施設にあたえた。本研究では、これらの中から、大きな変形を伴い構造物としての機能不全に陥った二つの施設、ため池とパイプラインに目標を絞り、その大規模被災の原因解明を行った。
成果の内容・特徴
- 丹羽生嶺ダムの被災原因の検討では、堤体開削調査および堤体材料の土質試験から堤体下部から堤体基礎に広がる砂質土の液状化あるいは強度低下が懸念された。そこで、土中の水圧上昇と強度低下を個別に評価できる地盤モデルを採用した地震応答解析を実施した。解析の結果、過剰間隙水圧はまず堤体上流法先で上昇し、堤体中央部に拡がっていく状況が再現された。また堤体変形のパターンは、実際の被害と比較的良い対応を示した(図1)。これらの解析的検討により、丹羽生嶺ダムの破壊メカニズムは、基礎及び堤体下部の過剰間隙水圧上昇による強度低下(液状化)であることが明確となった。また、緩い飽和砂質土が液状化しやすいという傾向も再確認できた。
- パイプラインの被害は、北桧山町の真駒内第一幹線水路で顕著であり、パイプラインの浮上、蛇行、離脱などの現象が現れた(図2左)。この原因は、土質調査及びパイプライン模型の振動台実験の結果、埋め戻し砂の液状化であることが明らかになった(図2右)。
- 地震被害の画像(写真)は、構造物の耐震性検討の基本資料である。本地震の調査で蓄積された大量の写真をフォトCDに収録し、工種、被害形態等による検索機能を備えた画像データベースのプロトタイプを構築した。
成果の活用面・留意点
昨年の兵庫県南部地震を契機として、各種構造物の耐震性見直しの必要性が強く指摘されている。行政部局において、農業用施設の耐震性を再考するとき、本研究により得られた知見を活用することができる。
具体的データ
その他
- 研究課題名:北海道南西沖地震による農業用施設の被災原因の検討及び被災情報の体系化
- 予算区分:経常・依頼
- 研究期間:平成7年度(平成6年-7年)
- 発表論文等:Damage to buried pipeline due to liquefaction induced performance at
the ground by the Hokkaido-NanseiOki Earth-quake in 1993,
1st lnt.Conf.Earthquake Geotech.Engng,.Vol.1,1995
Consideration of filldan behavior during the 1993 Kushiro-Oki Earthquake
and the 1993 Hokkaido-Nansei-Oki Earthquake,
1st Int.Conf.Earthqnake Geotech.Engng.,Vol.1,1995
平成5年(1993年)北海道南西沖地震による農地・農業用施設の被害調査報告,
所報告, p.111-142 (1996)