地下水汚染解析の基礎となる帯水層中の不均一移流現象の解明
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
地下水汚染は均一理想媒体中の現象として取り扱われているが、自然帯水槽中には速い流れに関与しない間隙が存在する。そこで、不攪乱砂試料を用いたトレーサ試験を行い、地下水と共に移動する汚染物質が透水係数による試算値より高速で移流する事実を示した。
- 担当:農業工学研究所・地域資源工学部・地下水資源研究室
- 代表連絡先:0298-38-7540
- 部会名:農業工学
- 専門:資源利用・環境保全
- 対象:現象解析技術
- 分類:研究
背景
地下浅部の地層や地下水の汚染を防止するためには、汚染物質の移流現象を解明しなければならない。これまでは、汚染物質を移動させる地下水流動が均一な理想媒体中の現象として取り扱われてきたために、汚染物質の移流速度は過小評価されている場合が多かった。このため、不攪乱砂試料を用いたトレーサ試験によって、地下水が限られた間隙のみを移流する現象の解明を目的とした。
成果の内容・特徴
深さ約3mのトレンチから採取した不攪乱砂試料を直径15cm、高さ42cmの円柱状に整形し、カラムに充填した。飽和状態にした後、上下端とも大気圧に開放し、上端から浸透パルス長が浸透路長の約5%となる量のトリチウム水をトレーサとして供給し、下端からの流出水を分画採取して水量とトリチウム濃度を測定した(図1)。また、現地で同時に採取した100mlの定積サンプラの土壌試料を用いて、基準化された方法で物理性を計測した。以上の結果から次のことが明らかになった。
- 透水実験では、試料の総間隙容積(PV)の約13%相当の水が流出した時点からトレーサの透過が認められ、同約42%という極めて早い時点で濃度ピークが出現した(図2)。粒状媒体では、PVがほぼ100%となる直前にトレーサの濃度ピークが出現する場合が多いことと比較して、野外で採取した不攪乱試料には速い流れに関与しない間隙が多く存在することが示された。
- トレーサの収支から、流出水がPV90%に達するまでにトレーサの約60%が回収され、移流現象が間隙容積の約42%を占める粗間隙を通じて行われているものと考えられた。
- トレーサの分散を移流拡散過程で考察し、流出曲線の前半が混合パラメータ(軸分散係数/平均流速*距離)を0.1とした理論曲線に近似し、標準砂で行った場合よりも1桁大きな軸分散傾向を示した。その原因は間隙規模の不均一性にあるものと考えられた。
- 3検体の小試料による変水位透水試験で得た透水係数は、10-3cm/sのオーダで、間隙率が近似しているわりに変動幅が大きかった(表)。これに対し、大試料による定水位透水試験では1×10-2cm/sの透水係数を得た。これによって、不攪乱試料の透水構造が不均一であること、基準化された小試料による透水実験では地下水汚染解析の基礎となる透水特性を得ることが困難であることを示した。
成果の活用面・留意点
これは、帯水層となっている典型的な砂層を対象として得た実験結果である。間隙構造の不均一性は地層ごとに異なる。この成果は、従来法で得た透水係数から短絡的に物質移動速度を論じることの間題点を指摘するものである。
具体的データ
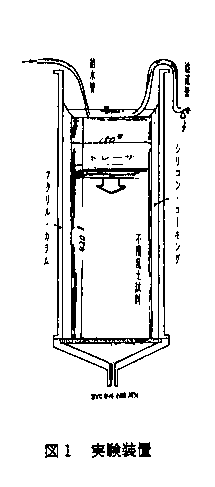
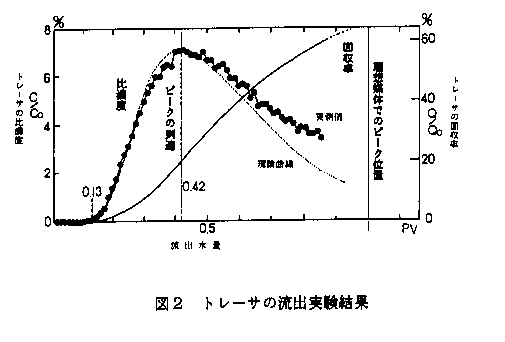
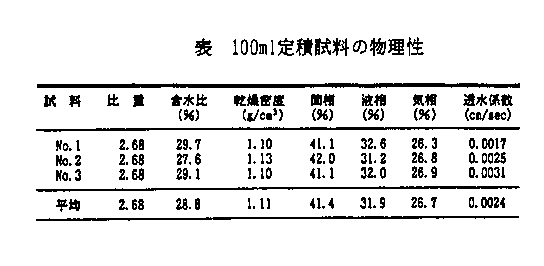
その他
- 研究課題名:飽和帯における汚染地下水の不均一移流現象の解明
- 予算区分:公害防止(浅層地下水)、経常
- 研究期間:平成7年度(平成3-7年)
- 発表論文等:地下水資源管理技術と土壌物理、農業土木学会第33回土壌物理研究部会研究集会論文集、pp.11-18、1994
トレーサを用いた飽和地下水の不均一移流現象のカラム実験、第31回理工学における同位元素研究発表会要旨集、p.111、1994
