ため池改修のための合理的設計法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ため池の改修のための設計技術を整理し、ため池に適した設計技術資料として、ため池設計技術資料「ため池整備」の制定のための水理・構造に関する技術開発及び技術の体系化を行った。
- 担当:農業工学研究所・造構部・上席研究官・構造研究室・施設研究室・土質研究室、水工部・水源施設研究室
- 代表連絡先:0298-38-7574
- 部会名:農業工学
- 専門:基幹・施設
- 対象:農業工学
- 分類:普及
背景
ため池の設計改修技術をまとめたものに「ため池便覧(昭57)」があるが、大規模フィルダムの基準に準拠した内容も多く、ため池には必ずしも適切ではないものもある。このため、新しくこれに代わる技術参考資料的なものを作成することを目的として本研究を行った。本研究では、ため池改修のための設計施工基準を想定して、1.一般事項、2.調査、3.設計洪水流量、4.堤体の設計、5.洪水吐の設計、6.取水施設の設計、7.その他の設計、8.施工等の関する技術的問題を検討した。技術検討の方法は、過去の災害調査、文献資料の調査、実験、及び解析等である。
成果の内容・特徴
- 許容漏水量を、浸透破壊の観点から「30リットル/min/100m*以下」、貯水効率の観点から「総貯水量の0.05%/day以下」の2つの条件の両方とも満足することとした(図1参照)
- 堤体及び基礎地盤の漏水防止策としてのグラウト工法について、その適用上の留意点と適用事例を整理した。
- 同様の目的で採用されることが多い遮水シート工法について、材料の特質から施工法、施工上の注意までを、実験結果を踏まえて総括的にまとめた。
- 洪水吐の形式として、ラビリンス堰も採用できるよう設計諸元を明示した(図-2参照)。
- ため池の簡易耐震判断基準を作成した(表-1参照)。
*ため池の堤軸方向の長さ100m当たり
成果の活用面・留意点
- 近畿農政局建設部発行一設計技術資料「ため池整備」(1996)..に研究成果が反映され、実務に適用出来ると期待される。
- 基礎地盤が軟弱な場合の底樋構造および、堤体の滑り安全性を考えるときの地震力の大きさなど、残された問題を検討する必要がある。
- ラビリンス堰の適用条件は限定されているので今後さらに検討する必要がある。
具体的データ
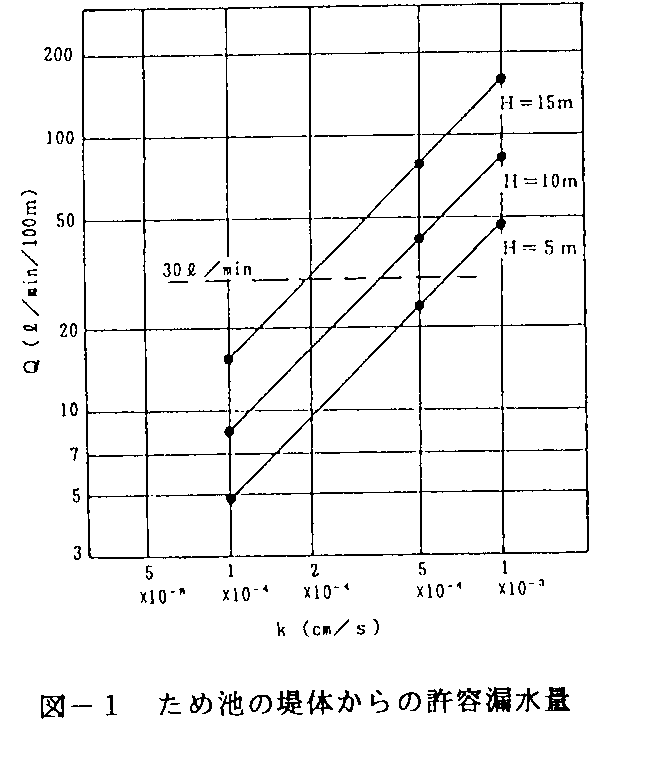
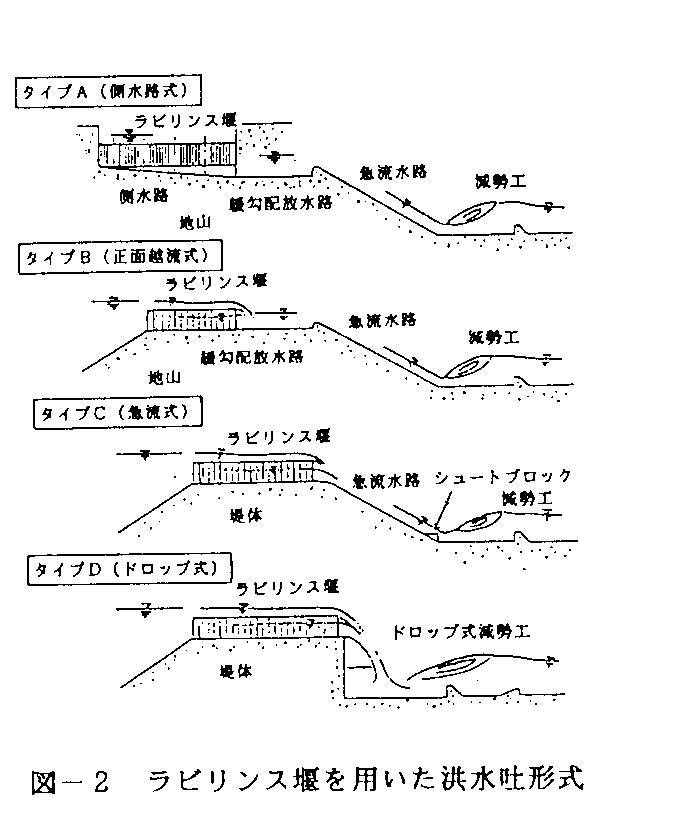

その他
- 研究課題名:ため池改修時の合理的設計法
- 予算区分:依頼
- 研究期間:平成8年度(平成6~8年)
- 研究担当者:ため池研究グループ(中島賢二郎・谷 茂・安中正実・長束 勇・中 達夫・常住直人)
- 発表論文等:設計技術資料「ため池整備, 近畿農政局建設部, 1996
