テラス型圃場整備計画のための区画規模・配置決定手法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
中山間地域における茶園再整備を対象に、テラス型圃場の区画規模・配置を植栽面積あたりの土工量が最小となるように自動決定する手法を開発した。
- 担当:農業工学研究所・地域資源工学部・土地資源研究室
- 代表連絡先:0298-38-7671
- 部会名:農業工学
- 専門:農地整備
- 対象:計画・設計技術
- 分類:研究
背景
中山間地域の急傾斜茶園では、茶業従事者の高齢化や後継者不足に起因する耕作放棄が進行しつつあり、労働力軽減、作業能率向上のための機械化が重要な課題となっている。茶園生産管理の高度機械化には、圃場を緩傾斜化する基盤整備が不可欠であるが、急傾斜面に立地する茶園では多額の土工費が必要な上、法面による植栽面積の減少等の問題が生じる。本研究では、レール走行式茶園管理機導入のための茶園再整備を対象に、茶園の区画規模・配置を、植栽面積あたりの土工量が最小となるように最適化する手法を開発した。
成果の内容・特徴
- 既存の圃場整備・農地造成計画システムは、単に土工量の算出や整備後の出来形の視覚的な表示を行うのみであり、整備コストや圃場作業性を左右する圃場配置・区画形状の決定は、設計者の技能に依存している。本手法は、こうした人間の判断に依存していた処理を最適化問題として定式化することにより、圃場設計の一部を自動化した。
- レール走行式茶園管理機の導入要件から、(1)区画形状は矩形、(2)圃場は畝間移動レールに沿って配置される、(3)圃場間の段差高は2m以内等の条件設定を行い、圃場の規模・配置の定式化を行った。定式化した圃場配置モデルを 図1に示す。
- 各圃場の短辺長(Wi)を茶畝(幅1.8m)の倍数、隣接する圃場との標高差(Hi-Hi-1)を10cm刻みの整数値とすることで、短辺長と標高を変数とする組み合わせ最適化問題を構築し、これら変数の組み合わせに対する目的関数(土工量/植栽面積)を最小化する解を求めた。最適化手法としては、複雑な現象を容易にモデル化できる遺伝的アルゴリズムを使用した。図2に区画規模・配置決定のフローチャートを示す。
- 本手法を事例地区に適用した結果の縦断図を図3に示す。世代を重ねるごとに目的関数(土工量/植栽面積)の値が減少し、より適正な区画規模、配置の設計案が作成される。
成果の活用面・留意点
本手法では、畝間移動レールの敷設位置を設計者の判断で決定しなければならないため、完全な自動設計ができるわけではないが、既存の圃場設計支援システムに組み込むことによって、設計作業の効率化と土工費の低コスト化が期待される。
また、本手法は、他の樹園地や水田の整備に対しても、整備圃場が満たすべき要件を反映した定式化を行うことにより、拡張して適用することも可能である。
具体的データ
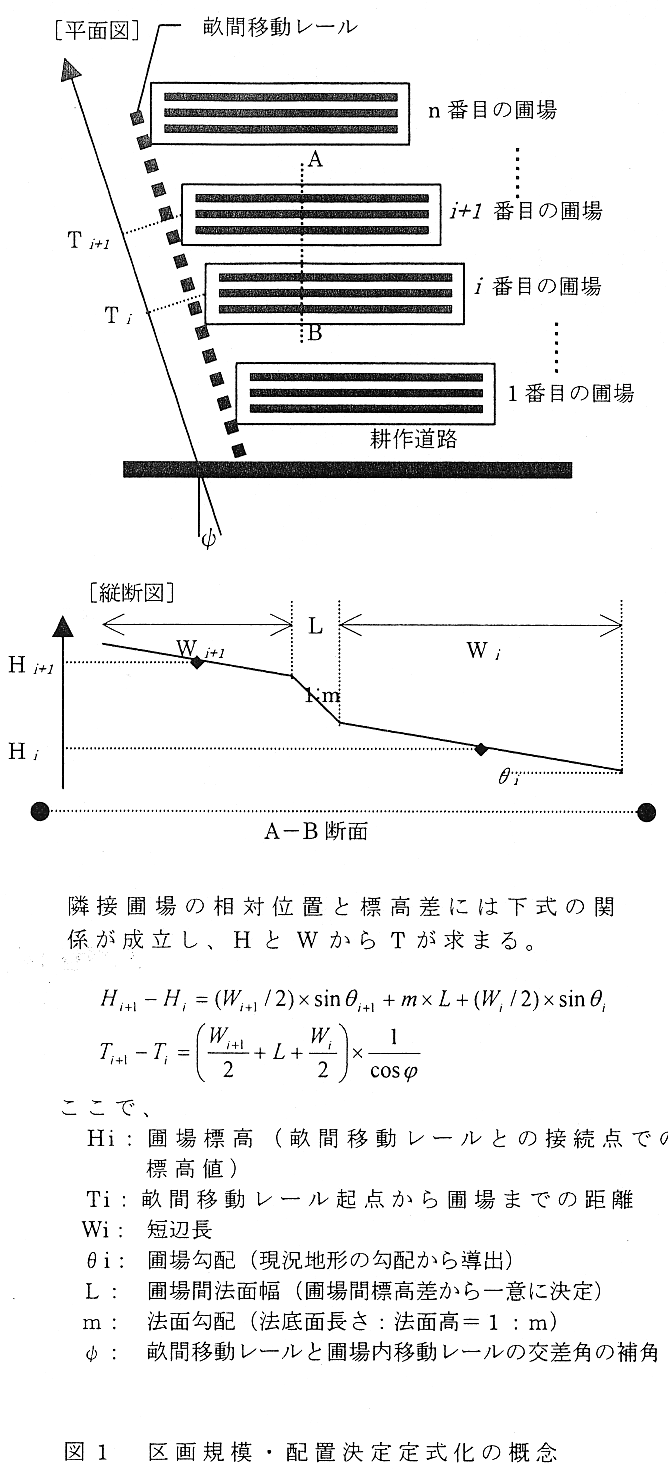
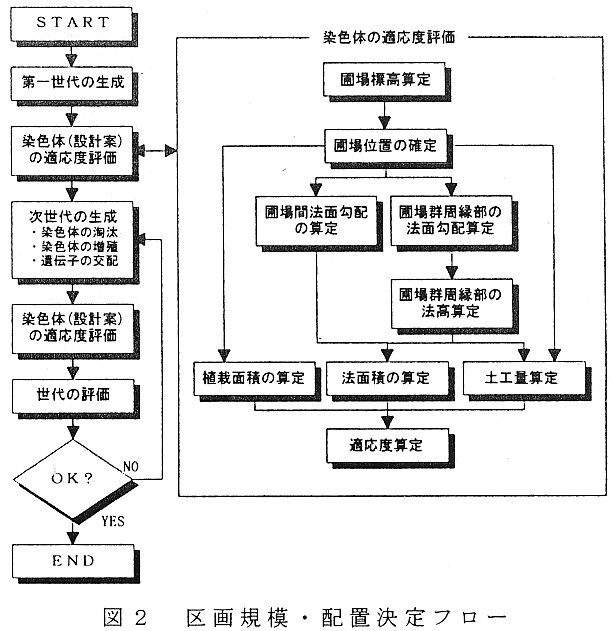
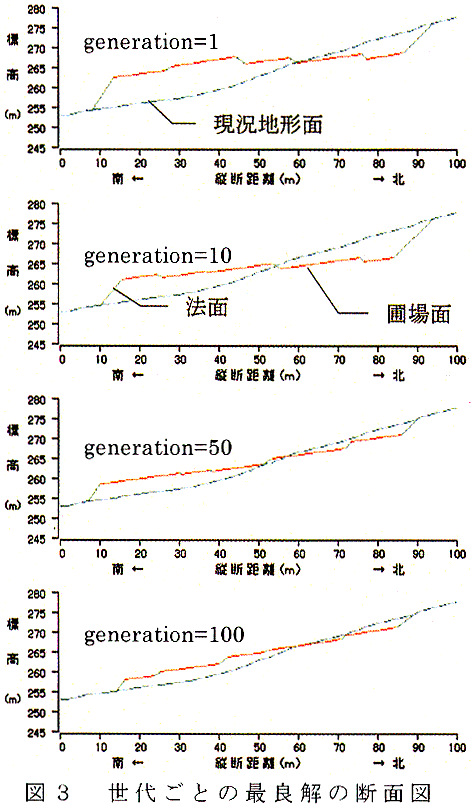
その他
- 研究課題名:GISを用いた圃場区画の最適配置設計手法の開発
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成11年度(平成9年~11年)
- 研究担当者:上村健一郎、奥島修二、福本昌人、塩野隆弘
- 発表論文等:上村健一郎・多田敦、「茶園再整備における圃場配置の最適化―レール走行式茶園の区画形状・配置自動決定手法の開発―」、システム農学会秋季シンポジウム研究発表会要旨、26-27、1999
