農業水利システムを通じた水循環と水質環境の評価
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
農村地域の河川水質データを用いて、水質変動に及ぼす降雨以外の要因を多変量解析により抽出することによって、都市化が進行している河川では、農業用水の水循環が水質改善に寄与していることが明らかになった。
- 担当:農業工学研究所水工部水環境保全研究室
- 代表連絡先:0298-38-7545
- 部会名:農業工学
- 専門:基幹施設
- 対象:計画・設計技術
- 分類:行政
背景
農業水利システムは、水循環を通じて水域の水質環境と密接な関わりを有している。健全な水循環の構築の観点から、この関わりを適切に評価することが求められているが、現実には評価に必要な河川流量等のデータ収集に多大な時間・労力を要する。
そこで、愛知県内9ヶ所の水質自動観測地点 (表1)の水質データを用いて、多変量解析(因子分析)により河川の水質変動に与える影響要因を分析し、農業水利システムと水域水質環境の関係を評価した。
成果の内容・特徴
- 分析の内容
1)観測地点の集水域に大規模な農業水利システムがある(5)、(6)、(8)の地点では、潅漑期と非潅漑期に大きな水質変動を繰り返しているが(図1:(5)地点の河川)、他地点では同様の季節変動はみられない。
2)水質変動を降雨の影響を除いて評価するため、因子数を2とする因子分析を行った。因子負荷量から第1因子はT-N、T-P等の水質指標、第2因子は濁度の指標である。第1因子と第2因子の因子得点の大きさにより、9ヶ所の観測地点は、図2に示すように山林面積が卓越するAグループ、都市的土地利用が多くかつ集水域に大規模な農業水利システムがあるBグループ、A、Bに属さないCグループに分類される。
3)第1因子と第2因子の分散構成比、因子得点と月平均日降水量の相関及び因子得点の平均値と土地利用面積率との相関から、第1因子は降雨に対する応答が弱い因子、第2因子は降雨に対する応答が強い因子である。
4)降水量と無相関の変動要因を把握するため、各因子を降水量で回帰したときの残差変動をみた。第1因子は、Bグループの地点で非潅漑期に大きな残差変動、潅漑期に負の残差変動を示し、他のグループでは変動があまりみられない。Bグループでは第1因子に降雨以外の水質変動要因として、農業水利システムによる水循環が影響しているものと判断された。(図3) - 結果の内容
1)因子分析によって、河川流量など集水域情報が十分でない水質観測地点で、水質変動に及ぼす降雨以外の影響要因を抽出することにより、自然度の高い河川、都市化の進行が水質に影響している河川、農業水利システムによる水循環の影響がみられる河川など、水質環境の相対的な比較・評価が可能である。
2)都市化が進行している河川では、農業用水の水循環が水質改善に寄与している。
成果の活用面・留意点
容易に得られる水質データを用いた統計解析手法は、水循環と水質環境の関係の評価を進展させる1つの方法として有効である。
具体的データ
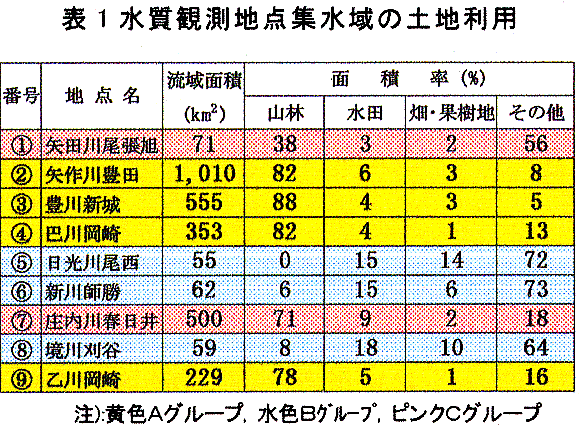
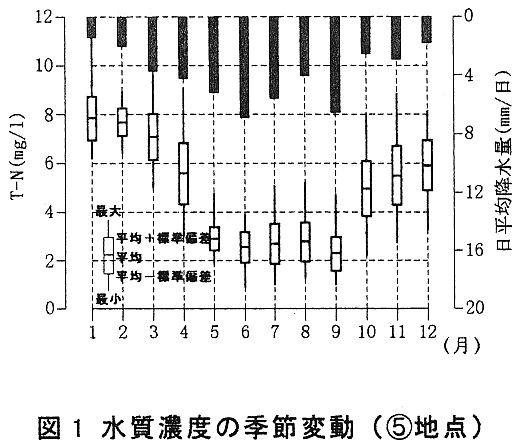
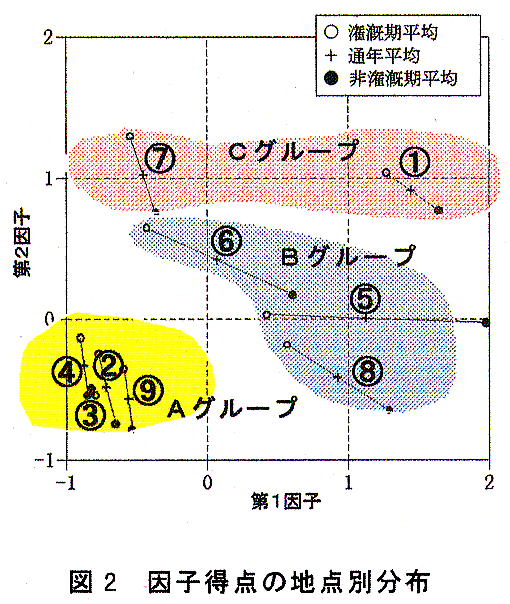
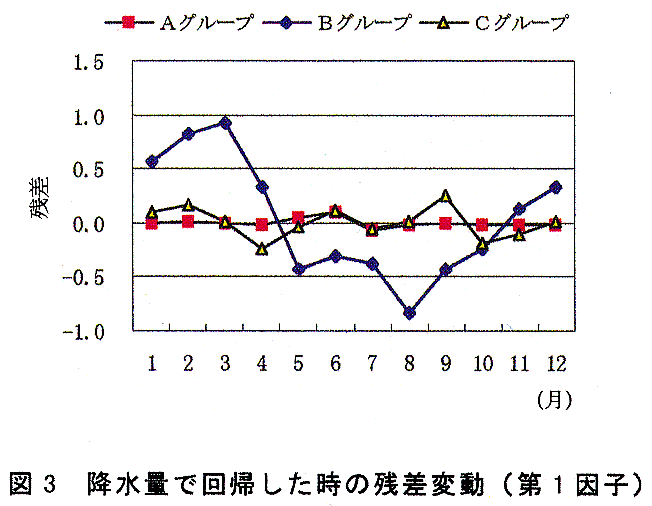
その他
- 研究課題名:水田地帯の農業水利システムが有する水質形成機構の解明
- 予算区分:経常・依頼
- 研究期間:平成11年度(平成9~11年度)
- 研究担当者:高橋順二、白谷栄作、吉永育生
- 発表論文等:高橋順二・白谷栄作・吉永育生:農業水利システムによる流域の水循環と水質環境、農土誌67(9)、61-68(1999)
