流速増大時のメダカの避難行動
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
絶滅危惧種に指定されたメダカを対象に流速と遊泳行動の関係を調べ、流速増大時に水草などの背後の流れの緩やかな部分に避難することなどを明らかにした。群れの過半数が避難するのは流速18~22cm/s(全長の6~7倍程度)であり、メダカにとって移動などのための安全な流速は15~20cm/s以下であると考えられた。
- 担当:農業工学研究所・農村整備部・集落排水システム研究室
- 代表連絡先:0298-38-7534
- 部会名:農業工学
- 専門:環境保全
- 対象:現象解析技術
- 分類:研究
背景
近年絶滅危惧種に指定されたメダカは、わが国では最小の魚類であり遊泳能力が低いと考えられる。本研究ではメダカの保全に配慮した農業水路の設計を目的として、模型水路(図1)を用い種々の流速を与えたときのメダカ(全長2.6~3.0cm、平均2.8cm)の遊泳行動、及び擬似水草(OHPシート)を設け流速が増大する過程での避難行動を分析した。
成果の内容・特徴
- 流速と個体の向き
流れが緩いとメダカは流れを認識しつつも様々な方向に自由に泳ぐ。しかし、速くなると流れに直面せざるを得なくなり、自由な遊泳を制限(図2のA方向)される。
平均流速1cm/sでA方向を向く時間(実験時間3分)が45%を占め、20cm/sでほぼ100%に達した(図3)。30cm/sでは3分間の遊泳に耐えたのは5尾のうち1尾のみであった。また、B方向からB方向へ自由に移動した距離は、20cm/sでほぼゼロとなった(図省略)。 - 流速と群れの形
流れのない状態から流速の増大に伴い、分散型→交互型→縦列型→直線型と群れの形が変化した(図4)。流れに対し群れとしての体制を整えた典型的な形である交互型は、平均流速10cm/sでピークに達した後、20cm/sで急減した。 - 群れの避難行動
流速が増大してこのままでは流されると感じた時、メダカは流れの緩い場所に避難する。7尾を投入し流速を徐々に大きくしたところ、流心部の流速18cm/s(全長の6.4倍)で過半数が水草の背後に侵入した(図5)。さらに、体格による違いを比較するため、平均全長3.3cmのメダカを用い実験した結果、22cm/s(全長の6.7倍)で過半数が侵入した。 - 適正な流速
メダカにとって移動などのための安全な流速は15~20cm/s以下と考えられる。また、流れに制限されず様々な方向に自由に遊泳するのは流速1~3cm/s以下の場合である。
成果の活用面・留意点
メダカの保全を考慮した水路の計画・設計に際しては、水路内に流速15~20cm/s以下の空間を確保する必要がある。また、休息などのためには流れの極く緩やかな部分(1~3cm/s以下)も必要である。
具体的データ
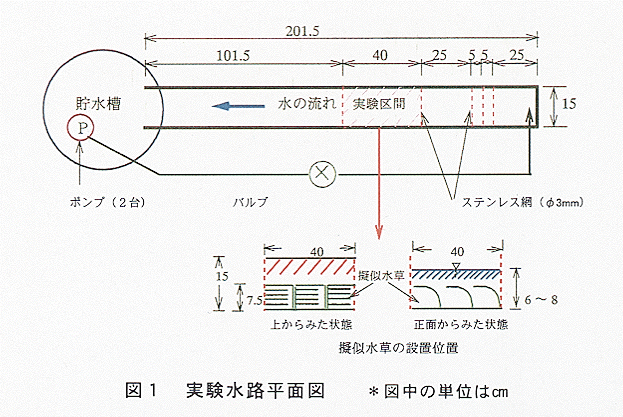
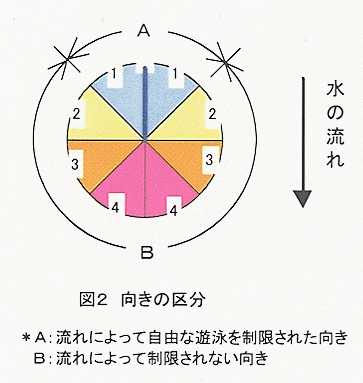
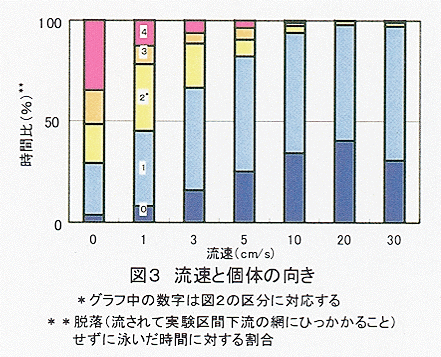
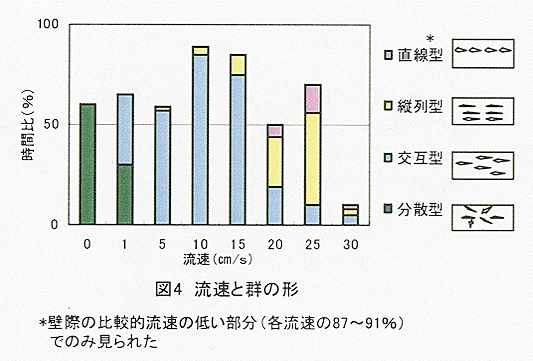
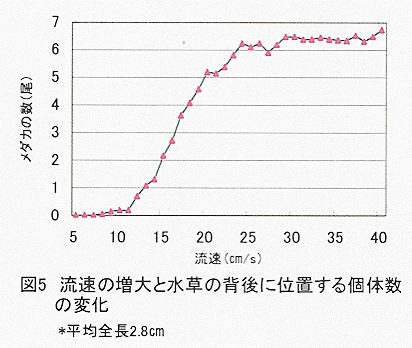
その他
- 研究課題名:魚類の移動・生息に配慮した農業水路の工法的研究
- 予算区分:経常・依頼・受託
- 研究期間:平成12年度(平成11~13年度)
- 研究担当者:端 憲二、本間新哉、中 達男
- 発表論文等:端、竹村、本間、佐藤、流れにおけるメダカの遊泳行動に関する実験的考察、農業土木学会誌、平成13年9月号掲載予定、2001.
